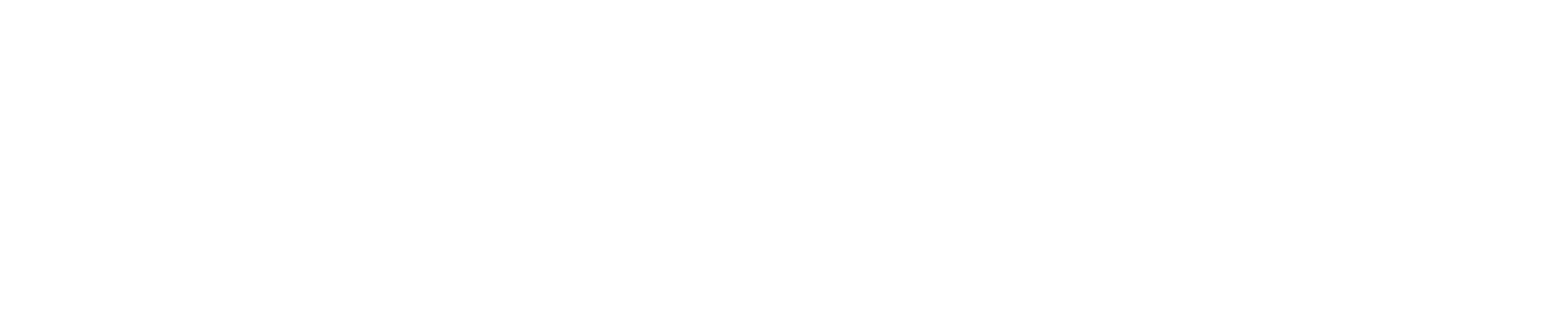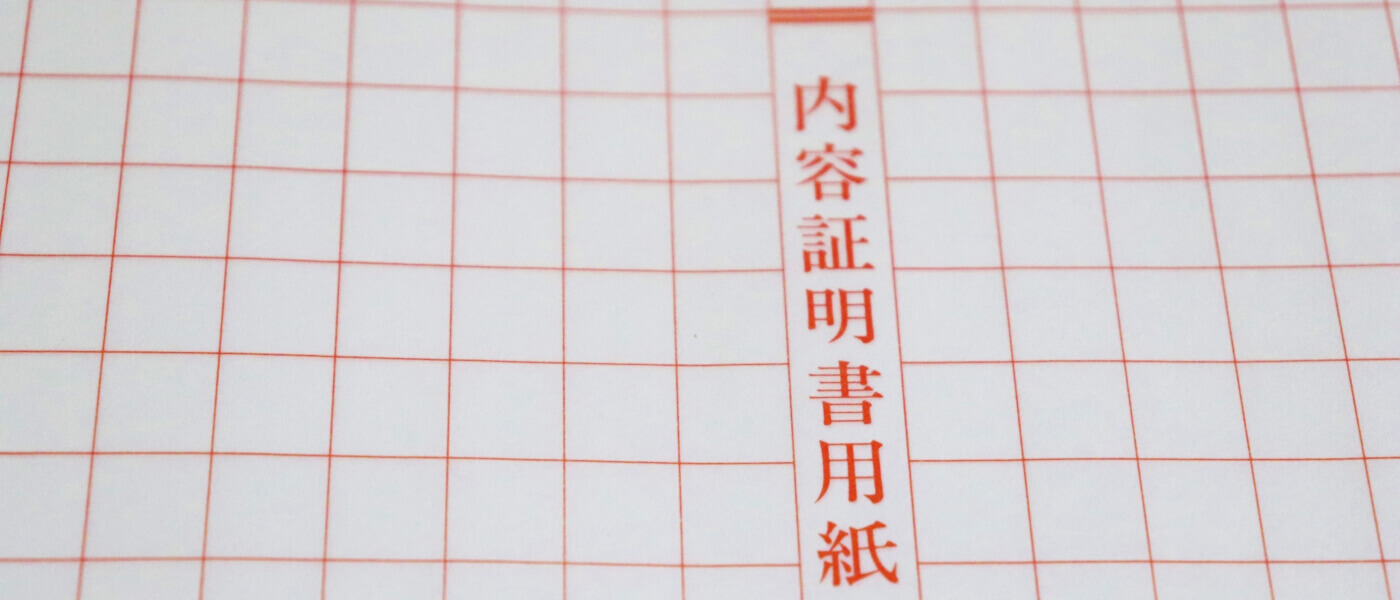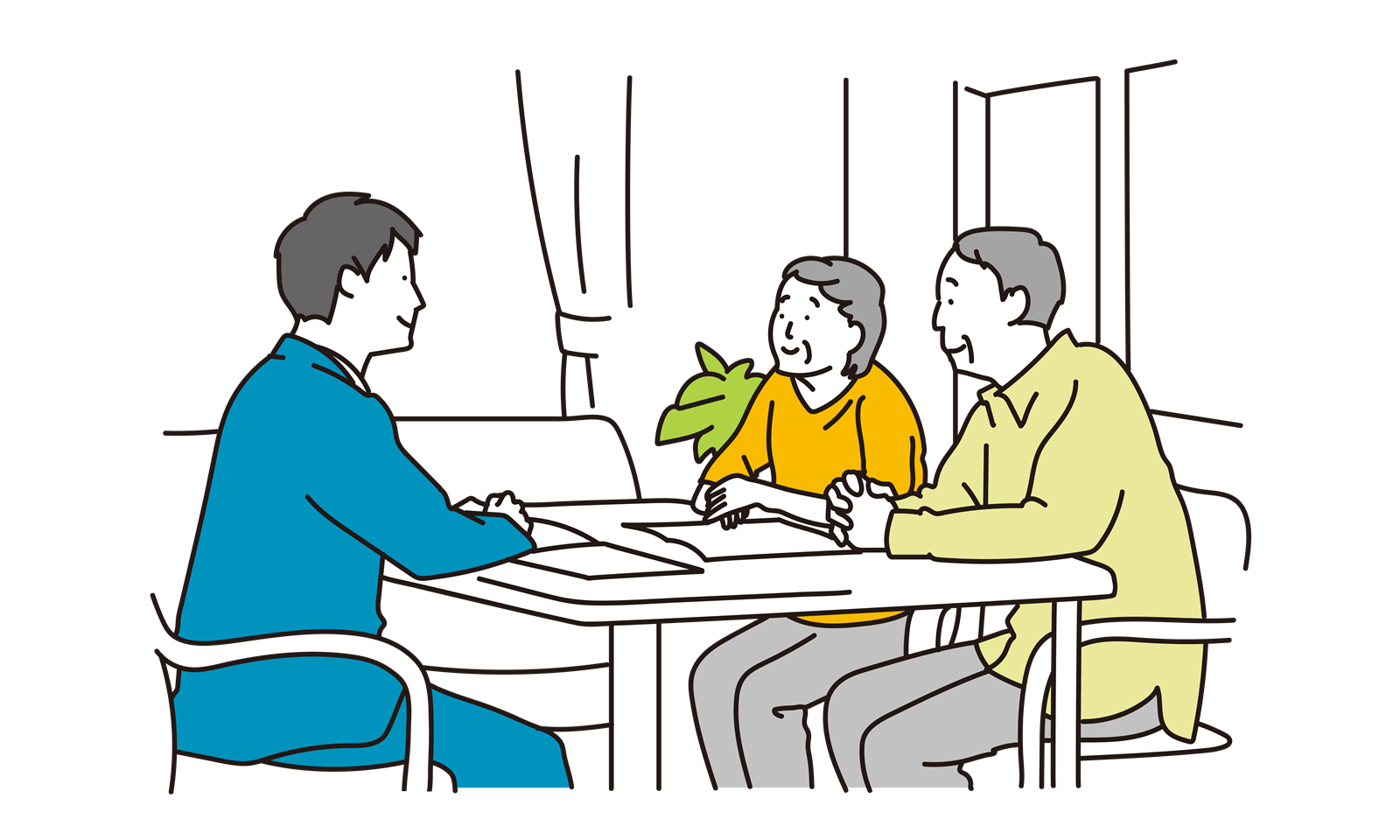内容証明の業務
内容証明の作成
内容証明専用の様式で作成・印刷をして郵便局本局から差し出します。郵便局の差し出し手続きに時間がかかる場合があり、スピードが命のクーリングオフには不向きかもしれません
電子内容証明の作成
文字数制限が軽減されるwordで作成します。電子内容証明の方が濃い内容で作成できて差し出しも早いため、特にご希望がないならこちらで承ります
-
STEP
- 初回無料相談
無料相談は時間無制限です。報酬額お見積りも可能です
-
STEP
- ご依頼(委任)
行政書士業務委任契約の締結、ヒアリング等
-
STEP
- 内容証明の作成と差し出し
内容証明の原案を作成して内容確認の上で差し出します
-
STEP
- 委任業務完了
内容証明の差し出しが完了したことをご連絡して完了です
内容証明については、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください
内容証明に関する
無料相談は時間無制限
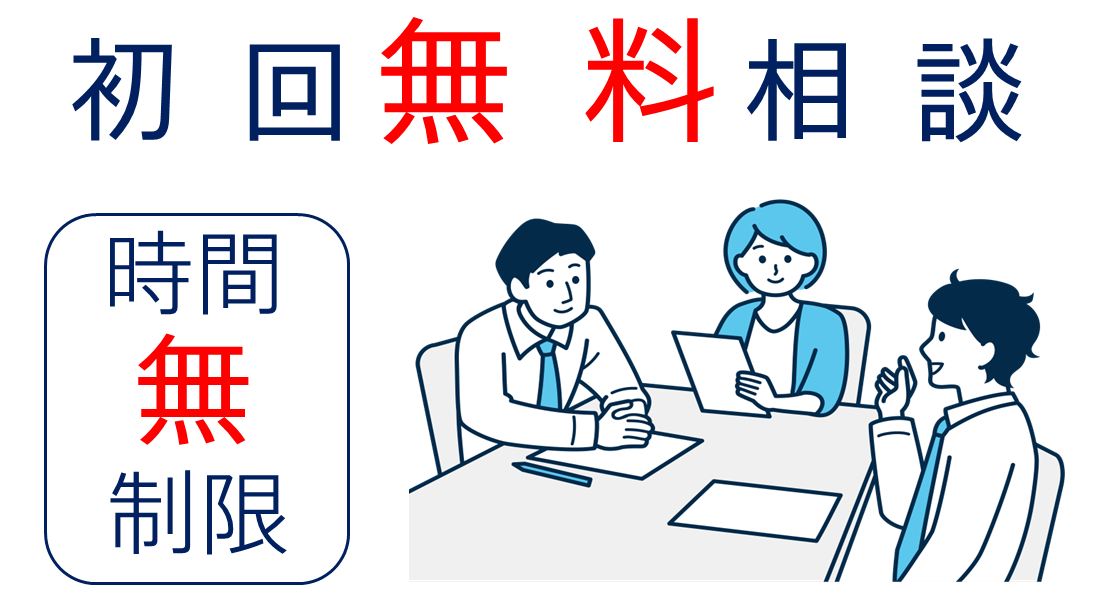
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
もちろん、他の事務所の無料相談を利用した上で比較検討していただいても一向に構いません。無料相談を利用したからといって必ず業務を委任しなければならないわけではありませんのでお気軽にお申し込みください。
内容証明の専門家
『 最高のサービスをいつも通りに 』
当事務所の経営理念です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人様に対して、常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。

はじめまして、特定行政書士の川瀬規央です。当職は営業出身ならではのコミュニケーション力と、難しいことをわかりやすくお伝えできる話術が大きな武器です。
士業にありがちな堅苦しい対応とは違い、士業らしからぬ明るく気さくな対応で好評いただいています。
| 代表 | 特定行政書士 川瀬規央 |
|---|---|
| 出身 | 滋賀県彦根市生まれの長浜市育ち |
| 最終学歴 | 神戸学院大学経済学部卒 |
| 登録番号 | 第16251964号 |
| 所属 | 滋賀県行政書士会 |
| 所在地 | 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
| 電話番号 | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
|---|---|
| 定休日 | 土日祝(お役所と同じ) |
| 受任エリア | 長浜市と彦根市を中心に滋賀県内 |
| 付随資格1 | 特定行政書士(不服申立て代理) |
| 付随資格2 | 申請取次行政書士(ビザ申請) |
| 付随資格3 | CCUS登録行政書士(建設業許可) |
| 付随資格4 | 著作権相談員(著作権登録) |
①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません
内容証明の
ご相談・お問い合わせ
内容証明の
業務事例・よくある質問

【依頼】家族が訪問販売で高額な教材を申し込んだがキャンセルしたい
【結果】訪問販売につきクーリングオフの対象。すぐにご依頼をいただいたので期限に間に合った。内容証明でクーリングオフを申込み、配達証明も付けた
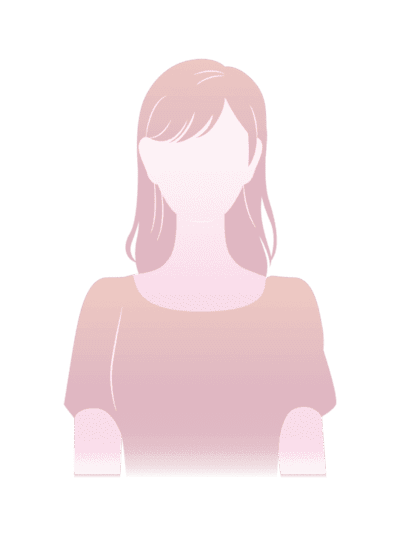
【依頼】夫の不貞行為の相手方に慰謝料を請求したい
【結果】状況を綿密にヒアリングし、内容証明で不貞行為の損害賠償請求。内容証明を無視された場合の対応も含めてご説明していたが無事に支払われた

【依頼】友人にお金を貸していたが返してもらえない
【結果】内容証明で返済を請求。返してもらえない場合は少額訴訟をするとのことだったが、翌週に一括して返済してもらえた
プライバシー配慮のため部分一致で記述しています
内容証明は、用紙に書いて郵便局へ持参して発送する方法と、WORDで作成してネットで発送するE内容証明(電子内容証明)の方法があります。
用紙に書くのは、文字数などの制限があるので、E内容証明の方が作成しやすいと思われます。
しかし、書き方よりももっと重要なのは、その内容です。特に他人に対して何かを請求する内容である場合については特に注意が必要です。請求する権利が何もないのに請求すると、反撃される可能性があります。
内容証明は証拠能力が高いため、自分で発送した内容証明によって自分の首を絞めることにもなりかねません。
内容証明の作成と発送は、行政書士、弁護士、司法書士などが業務として取り扱っています。どこへ頼むかは、内容証明に記載する内容によって異なります。
内容証明には請求する根拠となる法令を記載することが一般的で、その根拠となる法律の知識が豊富な士業を選ぶべきです。
報酬額は弁護士が最も高いですが、内容証明を送った後ですぐに裁判を提起するつもりであれば、内容証明の段階で弁護士に依頼しておくことも考えられます。
当事務所は内容証明のご相談も初回無料相談ですので、ご利用いただければ、最良のアドバイスができると思います。
不貞行為が発覚した場合、それにより離婚をするのか否かにより対応を作成書類が異なります。不貞行為の相手方に慰謝料を請求することは可能ですが、慰謝料請求だけでは足りないケースもあります。
内容証明には何か資料等を同封することはできないので、慰謝料請求をするだけの場合に使用します。例えば、不貞行為が原因で離婚が成立した後で、相手方に対して慰謝料請求をするケースなら内容証明で請求します。
相手方が請求を無視した場合は訴訟になることも考慮した上で文面を作成しなければなりません。専門家へ相談せずに突っ走ると、相手方が専門家に相談していた場合はブーメランを喰らうことにもなりかねません。
長い間、別居をしていて連絡も取っていない場合、郵便では読んでもらえない可能性が高いと考えられます。このようなケースで確実に離婚協議の申し入れをしたい、また、申し入れをした証拠を残したい場合は内容証明が役立ちます。
内容証明は知らない、見ていないと言わせないもので、法定効果も高いため「意思を伝えて何かを要求する」場合には最適だといえます。
書面による購入申込日から8日以内にキャンセルの意思表示をしなければなりません。キャンセルは、書面で意思表示をしてクーリングオフが適用されますが、証拠能力が高い内容証明でします。
期限まで時間がないことがほとんどなので、電子内容証明が最適です。電子内容証明なら文字制限も大幅に緩和されており、文章が長くなりがちなクーリングオフにも向いています。
内容証明の基礎知識
ここからは内容証明に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも内容証明に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
内容証明とは
内容証明とは、内容証明郵便という「手紙の1種」です。通常の手紙では宛先に届いたのかどうかわかりません。書留にすると届いたかどうかはわかりますが、送った手紙の内容は証明できません。
内容証明は配達記録を付けて送付し、届いたことと、内容の証明を日本郵便がしてくれるものです。「届いてない、知らない、見ていない」は通用しなくなり、非常に証拠能力が高いものです。
内容証明は一度出してしまうと撤回できません。よって、言葉の度が過ぎると、反対に相手方から脅迫や恐喝で訴えられる危険性もあります。そうなると相手方に有利な証拠をわざわざ与えてしまうことになってしまいます。今後もお付き合いしていく相手に対して内容証明を利用する場合は、厳しい文言は使用せずに粛々と記載をする方がよいでしょう。
電子内容証明とは
電子内容証明とは、e内容証明の名称で利用できます。ネット上でWORD文書をアップロードして内容証明を送付するものです。インターネット環境があれば自宅からでも事務所からでも24時間送付できます。
また、文字制限も大幅に緩和されています。ご依頼の内容によっては非常に有効になります。相手方に心理的な圧迫を与えるような事案ではない場合に有効です。自宅や職場からでも送付手続きができるのは大きなメリットです。
電子内容証明のデメリットは、心理的圧迫が少ないことです。当事務所ではヒアリングの上、どちらがよいか決定しますが、原則、電子内容証明を使用します。
電子内容証明の作成規定
| 文書作成ソフト | Microsoft Word 2013、2016、2019 |
|---|---|
| 文書枚数 | 最大5枚 |
| 文字ポイント | 10.5以上145ポイント以下 |
| 用紙レイアウトA4縦置き・横書き | 用紙の余白上左右の余白が1.5cm以上、下の余白が7cm以上 |
| 文字の種類 | JIS第1・第2水準範囲の文字で外字や図表は使用できません |
| 文字装飾 | 太字、斜体のみ可 |
受取人の方で「配達証明」を有りにします。受取人へは正本が送付され、配達証明は正本のみに附帯できます。一方、謄本は差出人へ簡易書留で送付され、配達済通知ハガキも差出人へ届きます。
郵便法
第四十七条(配達証明)配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。
第四十八条(内容証明)内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
②前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。引用元: e-Gov 法令検索
内容証明の書き方
内容証明は、どんな用紙でもよいとされていますが、最低でも謄本の保存期間である5年間の耐久性は必要です。縦書きでも横書きでも構いません。
赤色の枠の原稿用紙のような、内容証明専用用紙は縦書きです。当事務所で内容証明を作成する場合はこの様式を使用します。間接的に圧迫できるといえます。
内容証明の書式には定めがあります。用紙1枚あたり26行、1行あたり20文字以内と定められています。( )や「 」など括弧や句読点も1文字に数えます。複数ページになる場合は契印が必要です。
内容証明を発送する際の必要部数は、相手方送付用、自分の控え用、日本郵便保管用の合計3通必要です。送付用以外はコピーでもよいとされていますが、押印をする場合は、3通ともに押印が必要です。
なお、内容証明の差出人や宛名に関する留意点は以下のとおりです。
| 内容証明の宛名 | 法人や団体に送付するときの宛名は代表者宛にします。商業登記簿で確認すると間違いがありません |
|---|---|
| 内容証明の差出人 | 法人や団体が送付するときの差出人は代表者等の権限のある者の名前で出します。内容証明を発送するのは差出人以外の人でも構いません |
| 内容証明の表記を統一する | 本文の住所・氏名の表記と封筒の表記は一言一句同じである必要があります |
クーリングオフとは
本来、有効に成立した契約は一方の一方的な都合で解除することはできません。ただし、訪問販売や電話勧誘による販売については、セールスマンによるセールストークによって勢いで契約してしまったり、断ったが帰ろうとしないために渋々契約してしまうこともあります。
不要な契約であることは明確なのに、その場の状況によって契約してしまって後悔することがあります。このような消費者を保護するために特定商取引法では、契約後の一定期間内であれば無条件で契約を解除することができると定められており、これがクーリングオフです。
クーリングオフの解除可能期間は、契約書類を受領した日から起算されますので、受け取った日も1日でカウントします。クーリングオフの意思表示は、消印が解除可能期間内なら、相手方に届くのが期間経過後でもかまいません。
民法では相手方に意思表示が到達したときに効力が発生する「到達主義」を定めていますが、クーリングオフでは例外として、意思表示を発信したときに効力が発生する「発信主義」が採用されています。
解除期間が8日間の取引例
| 訪問販売 | 印鑑や健康商品を訪問販売する形態。アポセールスやキャッチセールスも含む |
|---|---|
| 電話勧誘販売 | 電話で契約を勧誘する形態 |
| 特定継続的役務提供 | 学習塾や家庭教師、エステなど継続したサービスを販売する形態 |
| 訪問購入 | 訪問して消費者から品物を買い取る形態 |
解除期間が20日間の取引例
| 連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法 |
|---|---|
| 業務提供誘引販売取引 | いわゆるモニター商法、内職 |
クーリングオフ対象外の例
- 訪問販売ではなく、消費者自身が店舗へ出向いて契約した場合
- 通信販売、ネット販売で購入した場合
- 現金で3,000円未満の場合
- 食品や化粧品など、使用・消耗した部分
- 路上での勧誘がきっかけで飲食店など
- 自動車、自動車のリースなど
クーリングオフをする場合、契約書や約款など購入したときの書類を確認しましょう。キャンセル、契約解除についての記載があると思います。そして、契約先の代表者へクーリングオフしたい旨の通知を書面で送付します。
クーリングオフは必ず書面で通知しなければなりません。書面なので封筒に入れて送付することも可能ですが、相手方(販売者)が「知らない、見てない、届いてない」と言われると証明できないので泣き寝入りになってしまいそうです。
内容証明なら、送付した書類の内容と、お届け日の証明も可能なので、ハガキや手紙に比べてはるかに証拠能力が高いのでおすすめです
内容証明の出し方
内容証明の発送は郵便局で行いますが、内容証明郵便を取り扱っている局へ行きましょう。お住まいの地域の本局クラスの郵便局になると思われます。
内容証明書3通と、内容証明書に記載したとおりに宛名と送付先を記入した封筒1通を窓口で出します。窓口では、配達証明付き内容証明郵便とお願いしましょう。
局員さんがチェックして、問題が無ければ認証印を押して、封筒と内容証明書の送付用1通を渡されます。封をしてもう一度、窓口に出します。料金を支払って、自分の控え用内容証明を受け取って終了です。
相手方に届けられるのは配達記録で届けられます。相手方が受領した場合、ハガキのような郵便物配達証明書が届きますので内容証明の控えと一緒に保管しておきましょう。