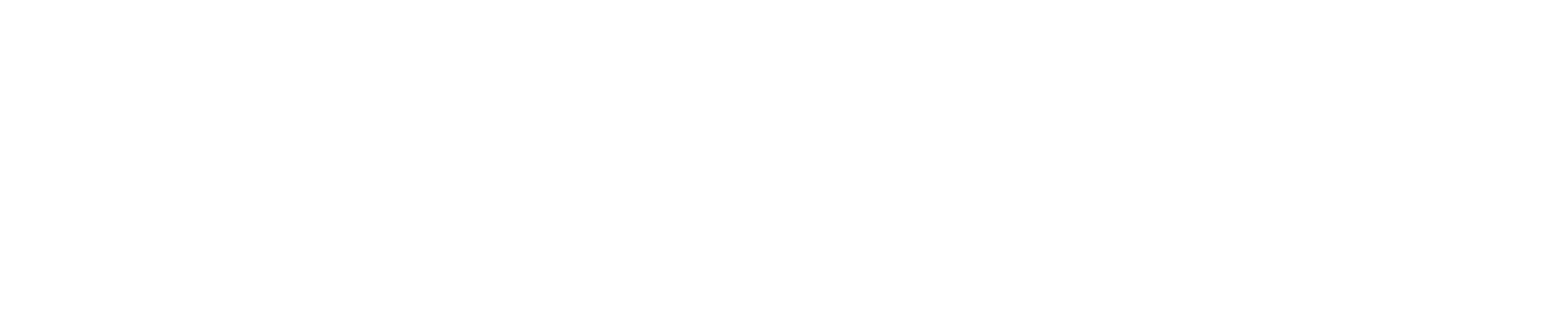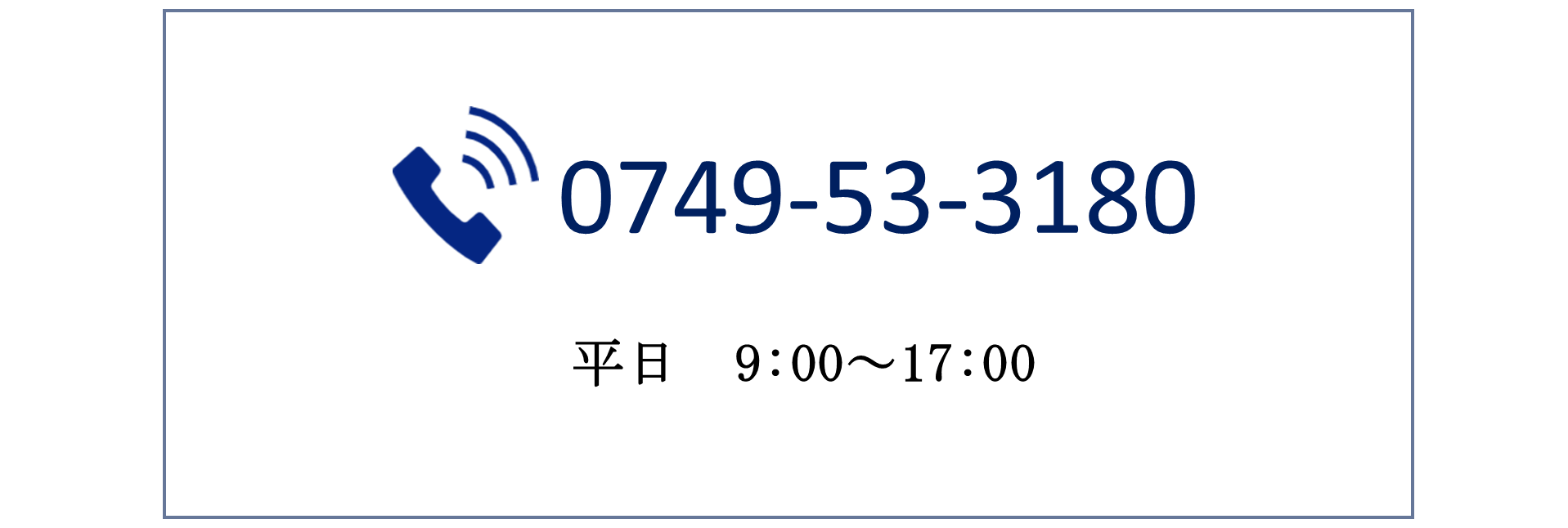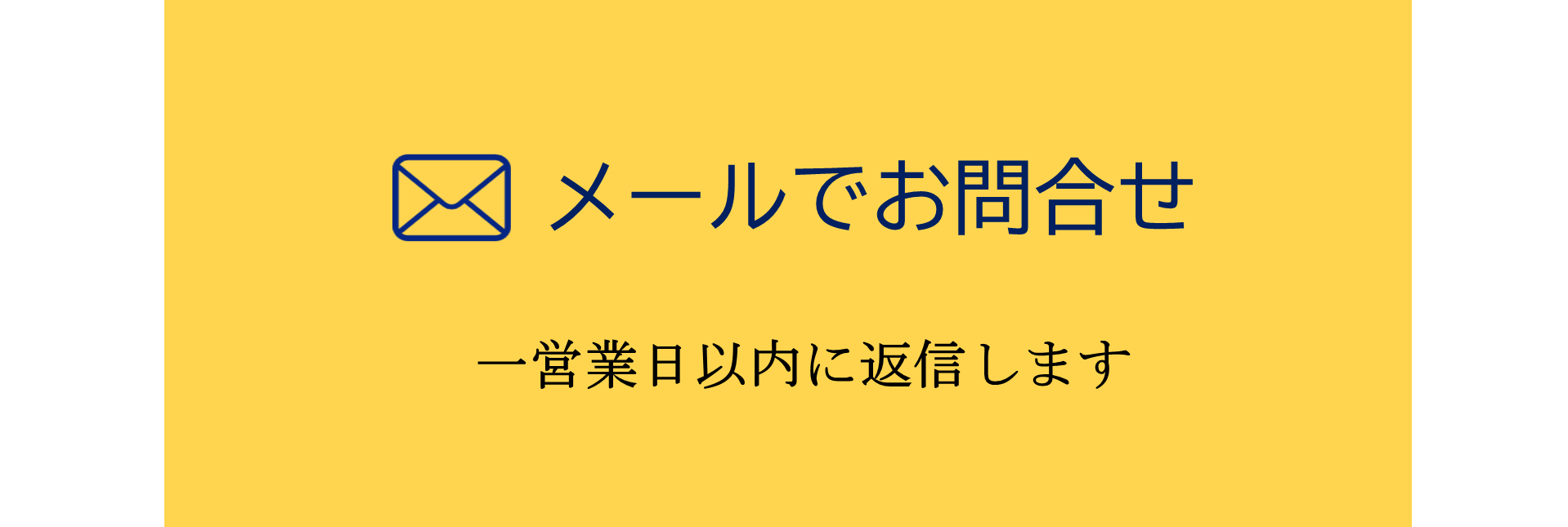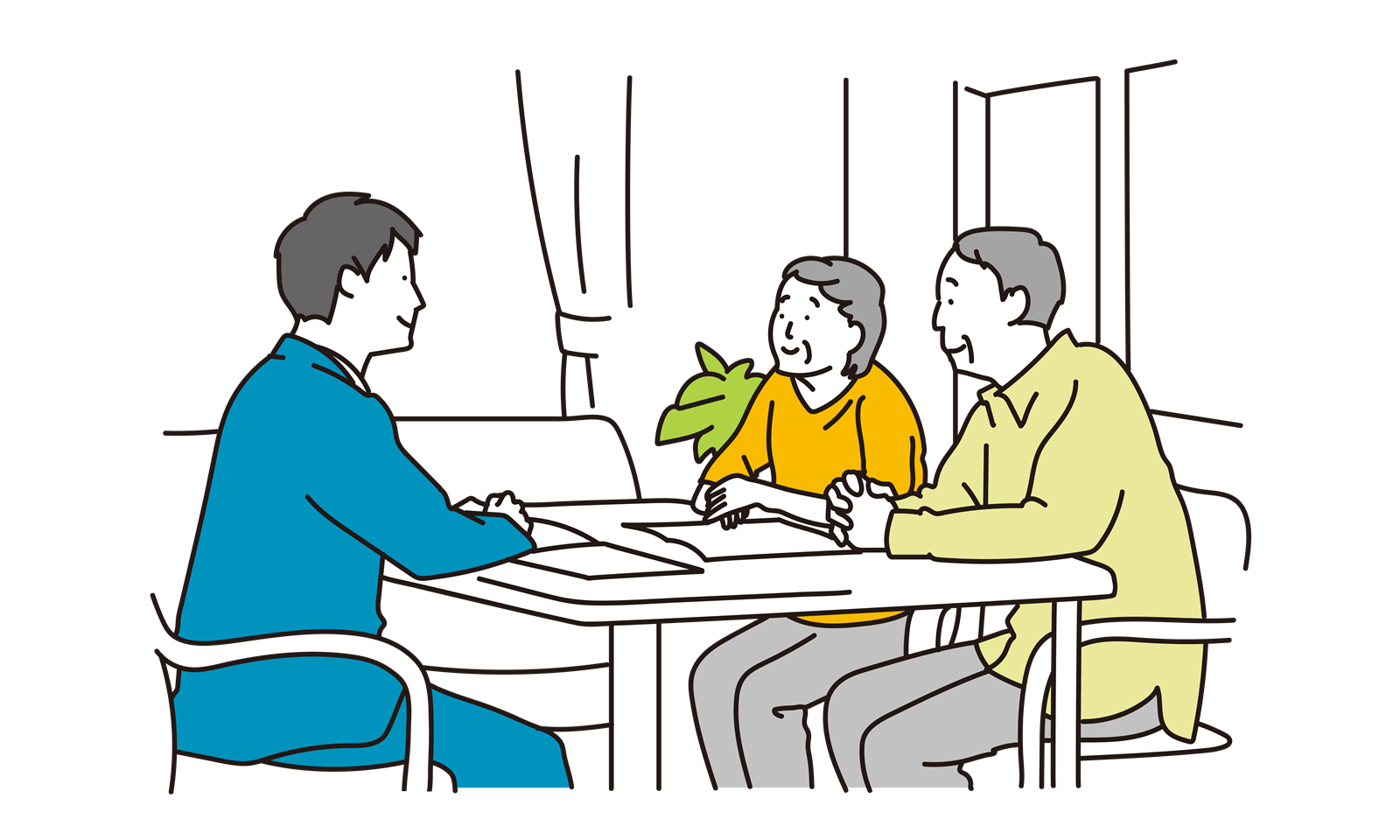セミナー講師について
遺言書の書き方教室や相続についてのセミナー講師を承ります。公民館や葬祭ホールのイベントにぴったりの内容で、堅苦しくないわかりやすいセミナーです。
よくご年配の方は「うちは遺言なんか必要ない」とおっしゃいますが、遺言書が必要かどうかはその人が決めるのではなく、相続人が決めるべきものです。遺言書は自分の死後、遺された相続人がする相続手続きを円滑かつ揉めないようにするためのものです。
エンディングノートと遺言書は全く異なるものです。遺言書は法的効力がある書面です。遺言書がある場合と無い場合とでは相続手続きの方法自体が変わるのです。
行政書士かわせ事務所のご案内

当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
| 事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 特定行政書士 川瀬規央 |
| 所在地 |
〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318-15 |
| TEL | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 |
カレンダー通り(役所と同じ) 12/29~1/3は休業 |
| 所属 |
登録番号:第16251964号 |
|
会員番号:第1292号 |
|
|
行政書士 付随資格 |
特定行政書士(不服申立て代理) |
| 入管申請取次行政書士(ビザ申請) | |
| CCUS登録行政書士(建設業許可) | |
| 著作権相談員 |
セミナー講師のお問合せ
行政書士のよくある質問
行政書士の業務内容は、司法機関を除く官公署などの行政機関に対してする申請や届出の代理と書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。
そもそも、他人からの依頼を受け報酬を得て、業として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)
例えば、自動車販売店が車庫証明の申請を「車庫証明の費用は無料です」と言って行うと、行政書士法違反です。
車庫証明自体のの報酬は得ていなくても車両代や諸費用を得ているからです。
行政書士法違反は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。
行政書士法
(業務)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
行政書士法
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。引用元: e-Gov 法令検索
特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。
特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。
特定行政書士のみがすることができる業務は、不服申立ての代理です。許認可で不許可処分になった場合の審査請求が代表的な例です。
行政書士法
第一条の四 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。引用元: e-Gov 法令検索
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任により知り得た秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。
行政書士法
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。引用元: e-Gov 法令検索
日本には士業は8種類あり、行政書士はそのうちのひとつです。士業は法律により取り扱うことができる業務が区別されており、いわばナワバリのようなものです。
司法書士は法務局などの司法機関に提出する書類作成が取扱業務ですが、不動産登記、商業登記がメインです。
弁護士は士業の最高峰として何でも取り扱うことができますが、裁判所手続きである調停や訴訟の代理人がメインです。紛争状態にあるケースの相手方との交渉は弁護士にしか認められていません。
当事務所の相談料は1時間迄5,500円(税込)ですが、初回相談は無料で、しかも時間制限はありません。特に離婚のご相談になると2時間超になることがほとんどです。
相談したからといって必ず依頼をしなければならないわけではありませんので、ご相談だけのご利用も大歓迎です。
また、相談の結果、司法書士や弁護士など他士業の業務管轄であった場合でも相談料はいただきませんので、どこへ相談すればよいかわからない場合もご相談ください。行政書士は「街の法律家」と言われています。
なお、2回目の相談後14日以内に正式に業務委任の場合は、頂戴した相談料を受任業務の報酬に充当します。
当事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約をお願いします。土日祝や17時以降も柔軟に対応いたします。
WEBからのお問合せの場合、初回相談のご希望日時を第1~第3希望まで入力していただけます。こちらからのメール返信において、日時をご連絡します。
また、相談内容を具体的に入力いただければ、この時点で司法書士や弁護士など他士業の業務管轄を判断できる場合はその旨をご連絡いたしますので無駄足になりません。
セミナー講師 実施事例
彦根市の河瀬地区公民館様

彦根市の河瀬地区公民館様で約20名のご参加でした。「福寿大学」の一環として、今回も好評の「遺言書の書き方教室」をテーマに講演をいたしました。
準備した資料に沿って、また、当職の実務上の経験などを織り交ぜてお話いたしました。講演後は、「わかりやすかった」との感想を頂戴いたしました。ありがとうございました。
彦根市の西地区公民館様

彦根市の西地区公民館様で約60名のご参加でした。今回は「遺言書の書き方教室」の内容を一新し、実際に遺言書を作成する場合の手順に沿ってお話しました。
とても熱心な方が多く、終了後もたくさんのご質問をいただきました。堅い話ですが、時折笑い声も起こる楽しい講演となりました。ありがとうございました。
長浜市のロータリークラブ様

長浜ロータリークラブ様の卓話で、「早めに知っておきたい民法改正」セミナーを実施いたしました。2020年に120年ぶりの民法大改正がございます。お仕事や暮らしに影響があると思われるテーマに絞ってお話いいたしました。
彦根市の高宮地域文化センター様
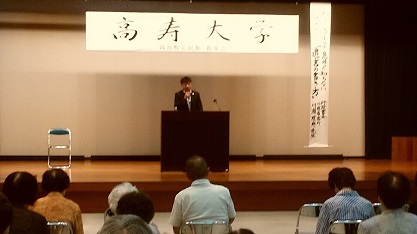
彦根市高宮の高宮地域文化センター様で約70名のご参加で「高寿大学」という催しでした。お題目は遺言の書き方教室で、民法で定められた遺言書の決まりごとをお話しました。
遺言書とエンディングノートとの違いについても解説いたしました。
彦根市の南地区公民館様

猛暑の中、約50名のご参加で遺言の書き方教室を実施いたしました。皆様熱心に聞き入っていただき、遺言とはこういうものなんだということをご理解いただけたことと思います。
南地区公民館様の「シニアカレッジ」の催しです。すごく精力的な活動をされています。
遺言書の書き方教室
遺言書という言葉は皆様ご存知ですが、遺言書の内容や決まりごと、遺言書作成の前に知っておくべき事柄に関しては知らない方が圧倒的多数です。
遺言書とエンディングノートを同じような物とお考えの方にいち早く考えを改めていただける内容です。遺言書は「法律」に沿って作成しなければならないものだからです。
遺言書の書き方教室では、まず遺言書というものを知っていただくためのセミナーで、公民館・自治会館、葬祭ホールの催しに最適なテーマです。
遺言セミナーの実施概要
- お時間:1時間~1時間半
- 使用するレジメ:当職作成の資料を使用します。参加人数分の印刷をお願いします
- 実施方式:レジメを配布。ホワイトボードがあれば使用します
- 対象会場:公民館、自治会館、葬祭ホールなどご指定の会場で実施いたします
- 報酬:公民館など規定がある場合には、柔軟に対応しておりますのでご安心下さい