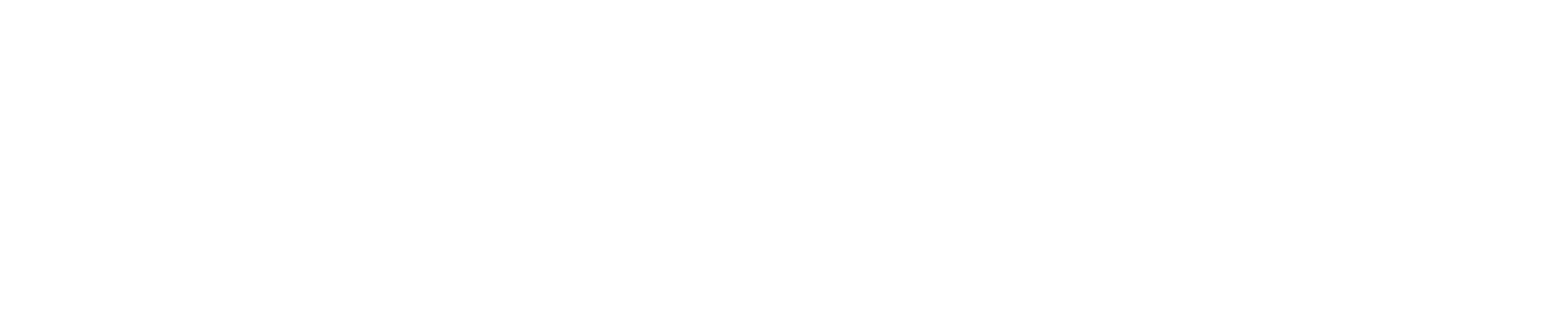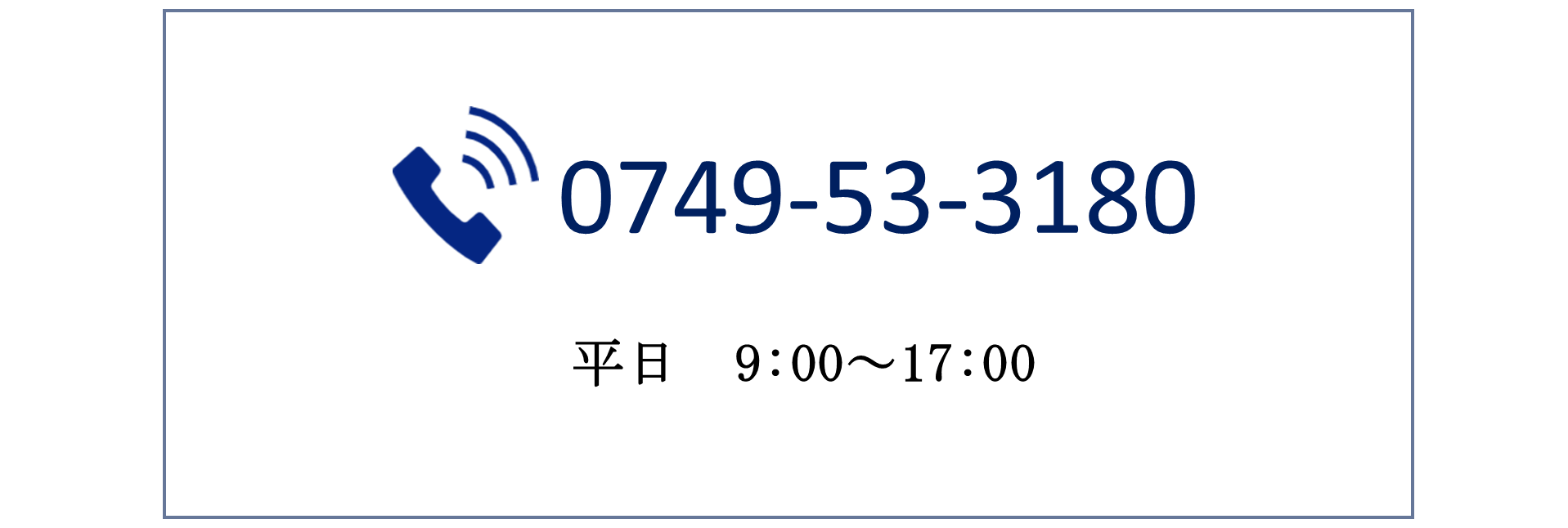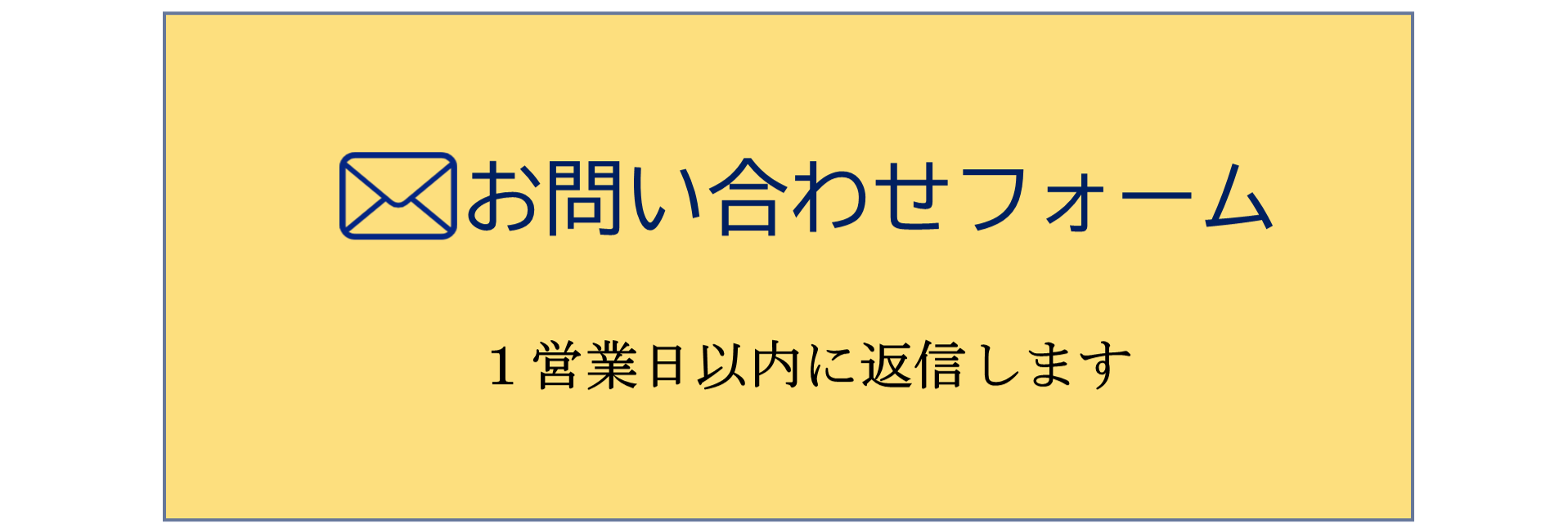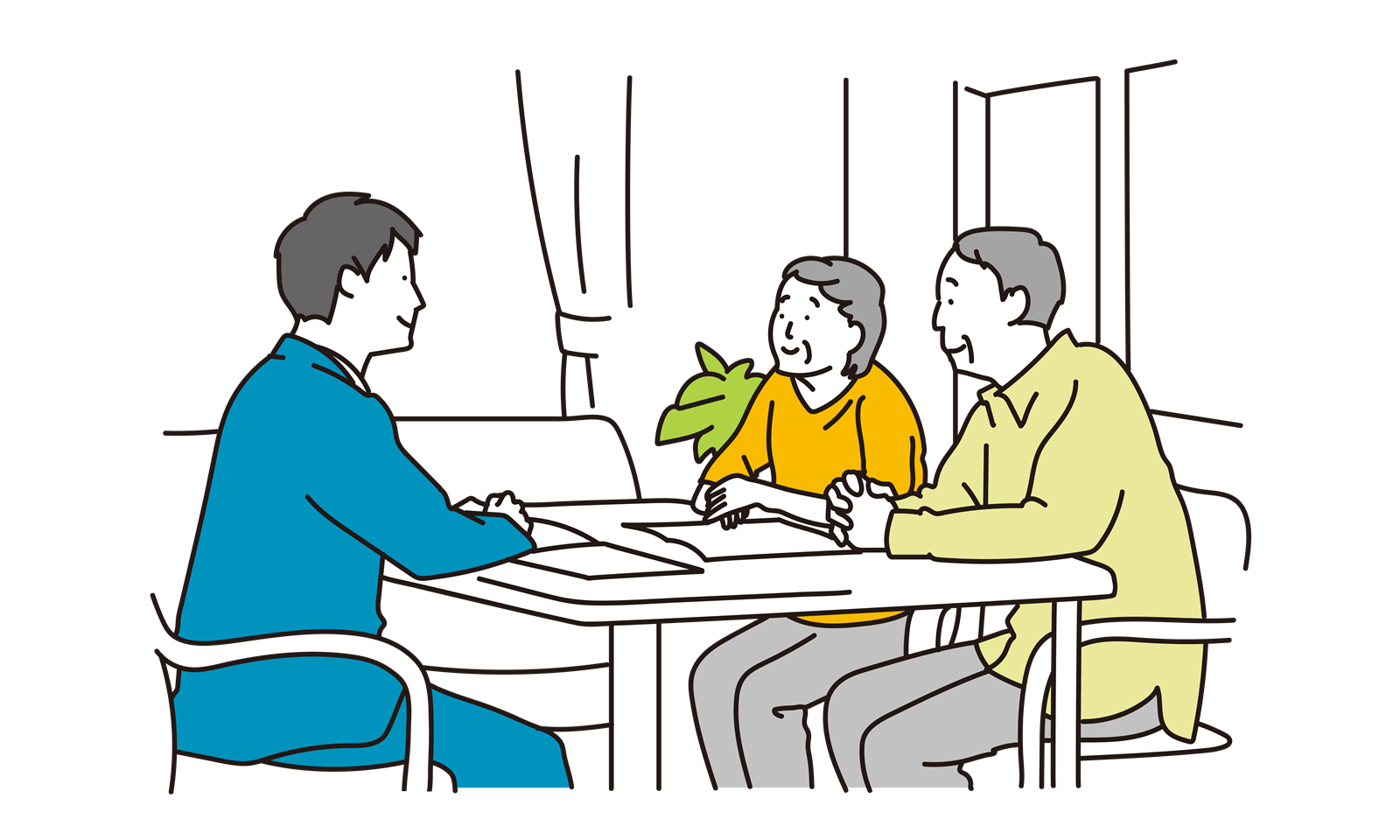HACCP導入について
- HACCPの完全義務化
HACCPは2020年6月1日から完全義務化されました。ほぼすべての食品関連事業所が対象となっています - HACCPには2種類ある
「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に区分されています。一般的な飲食店は後者に該当します
HACCP導入に関する
無料相談は時間無制限
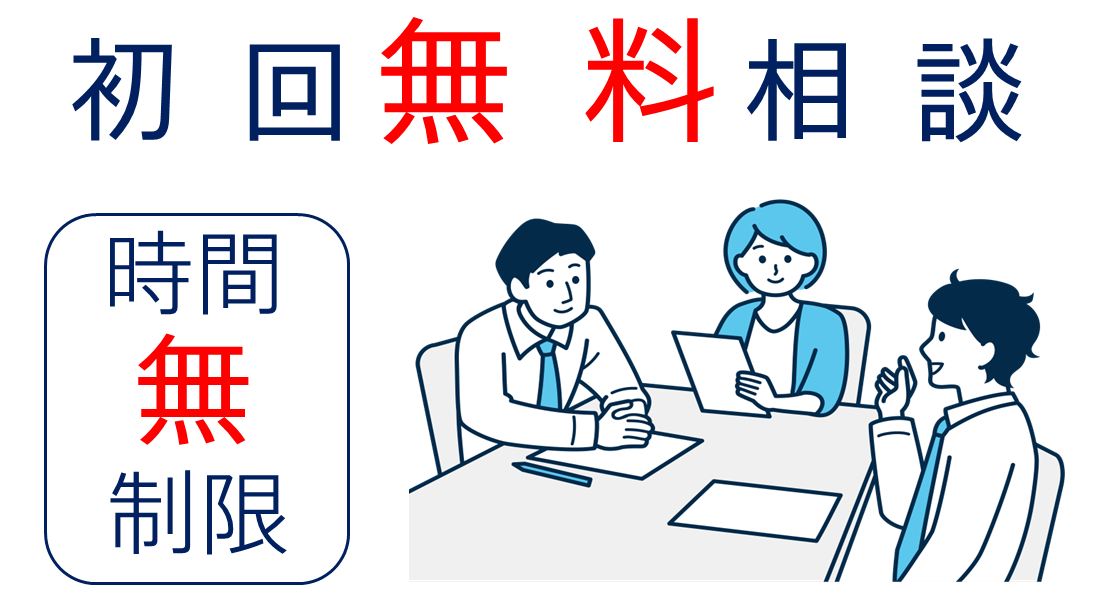
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
もちろん、他の事務所の無料相談を利用した上で比較検討していただいても一向に構いません。無料相談を利用したからといって必ず業務を委任しなければならないわけではありませんのでお気軽にお申し込みください。
HACCP導入の専門家
当事務所の経営理念は『最高のサービスをいつも通りに』です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人様やご相談者様に対して、常に公平かつ全力で提供するので、「いつも通りに」なのです。
また、専門家として心がけていることは、徹底的に準備をすることです。この準備によって圧倒的なスピード対応を可能にし、単に業務をこなすだけではない「違い」を生み出しています。「準備を失敗すること = 失敗するための準備をしたこと」、これが当職の最強の法則です。

はじめまして、特定行政書士の川瀬規央です。当職は営業出身ならではのコミュニケーション力と難しいことをわかりやすくお伝えできる話術が大きな武器です。
士業にありがちな堅苦しい対応とは違い、士業らしからぬ明るさと気さくな対応で好評いただいています。
| 代表 | 特定行政書士 川瀬規央 |
|---|---|
| 出身 | 滋賀県彦根市生まれの長浜市育ち |
| 最終学歴 | 神戸学院大学経済学部卒 |
| 登録番号 | 第16251964号 |
| 所属 | 滋賀県行政書士会 |
| 所在地 | 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
| 電話番号 | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
|---|---|
| 定休日 | 土日祝(お役所と同じ) |
| 受任エリア | 長浜市と彦根市を中心に滋賀県内 |
| 付随資格1 | 特定行政書士(不服申立て代理) |
| 付随資格2 | 申請取次行政書士(ビザ申請) |
| 付随資格3 | CCUS登録行政書士(建設業許可) |
| 付随資格4 | 著作権相談員(著作権登録) |
HACCP導入の
ご相談・お問い合わせ
HACCP導入の基礎知識
ここからはHACCPに関する基礎知識をご紹介しています。
HACCPの完全義務化
HACCP義務化は令和3年6月1日に完全施行されています。ほぼ全ての食品に関わる業種が対象となることから、1年間の猶予期間が設けられていましたが、完全義務化となりました。
当事務所では、一般飲食店のHACCP導入サポートを承ります。一般飲食店でHACCPを導入する際に、新たに設備を増やしたりする必要はありません。一番重要なことは、HACCPは「何をすればいいか」ということです。
HACCP導入の流れ
当事務所のHACCP導入サポートは以下のような流れです。ご依頼人がすべきことは管理項目について決めていただくことと、導入後の日々の管理です。
HACCP導入には書類作成も必要です。行政書士は書類作成のスペシャリストであることから、HACCP導入を依頼する士業としては行政書士が適任だとされています。
- HACCPについてヒアリングいたします
- 業種・業態を確認し、HACCPの対象であることを確認します
- HACCPでやることを解説します
- 管理項目についていくつか店舗で決めていただきます
- HACCPに必要な書類を作成します
- 作成した書類に沿って日々の運用をして下さい
- 見直しが必要であれば作成し直します(料金別途)
HACCPの概要
HACCPは「ハサップ」と読み、HazardAnalysisCriticalControlPointの頭文字をとった略称です。従来の衛生管理の手法は、最終製品の抜き取り検査をすることが主流です。
HACCPとは衛生管理の手法です。HACCPでは、原料→入荷→保管→加熱→冷却→包装→出荷といった工程ごとに、微生物や細菌による汚染、異物混入などの危害を予測した上で、防止につながる特に重要な工程を継続して監視・記録することで製品の安全性を確保する衛生管理の手法となっています。
HACCPの制度化は衛生管理の手法、つまりソフトに関するものですので、施設や設備といったハードに新設や変更は必要ありません。現状の環境で導入できます。
HACCPに資格は必要か
現状ではHACCPに国家資格はございません。民間資格でHACCPコンサルタントといったようなものはありますが、一般飲食店がHACCPを導入するにあたって有資格者は必須とはされておりません。
また、HACCPは許可を取ったり認可を得るような許認可が必要なものではありません。食品を取り扱う事業者として、いわば統一化された衛生管理をすればいいのです。
HACCPの対象業種
HACCP対象業種の代表的な例を挙げておきます。食品製造業だけの話だと思われている方も多いですが、飲食店や小売業のように食品を提供する業種も当然に対象業種です。
- 一般飲食店…ファミレス、居酒屋、中華料理店、ラーメン店など飲食店全般
- 食品製造/加工業…ケーキ製造、清涼飲料水メーカー、精肉店など
- 配食産業…病院・介護施設・学校等への給食センター、宅配ピザ店など
- 運送業…冷凍車、冷蔵車
- 倉庫業…冷蔵庫、冷凍庫
- 小売業…コンビニエンスストア、スーパーマーケット、道の駅など
- 風俗営業…バー、スナック、クラブなど
- 旅館業…旅館、ホテル、民宿など
- 重要食堂…介護事業所内食、病院内食堂、保育園内食堂など
公衆衛生に与える影響が少ない営業
以下のような公衆衛生に与える影響が少ない営業については、食品等事業者として一般的な衛生管理を実施しなければならないのは間違いありませんが、衛生管理計画の作成や実施状況の記録、保存を行う必要はありません。また、営業の届出も不要です。なお、農業及び水産業における食品の採取業はHACCPに沿った衛生管理の制度化の対象外です。
- 食品または添加物の輸入業
- 食品または添加物の貯蔵または運搬のみの営業(冷凍・冷蔵倉庫業は除く)
- 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
- 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
- 器具容器包装の輸入または販売業
- ①~③及び⑤の営業者は、法第50条の2第2項に基づく衛生管理計画及び手順書の作成も不要です
- 学校や病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁家が行う採取の一部とみなせる行為についても、営業届出及び衛生管理計画・手順書の作成は不要です
HACCPの2つの基準
HACCPは全ての食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理計画を作成して運用しなければなりませんが、事業規模等により以下の2つの基準に区別されています。
HACCPに沿った衛生管理の区分
- HACCPに基づく衛生管理
食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取り組みです。コーデックスのHACCP7原則に基づき、食品等事業者が、使用する原材料や製造方法等に応じて計画を作成し、管理します。対象事業者は大規模事業者、と畜場(と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者)、食鳥処理場(食鳥処理業者だが認定小規模食鳥処理事業者を除く) - HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
取り扱う食品の特性等に応じた取り組みです。各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行います。対象事業者は小規模な営業者等です。
HACCPの小規模な営業者等
- 食品を製造・加工する営業者であって、食品を製造・加工する施設に併設(隣接)した店舗においてその施設で製造・加工した食品の全部または大部分を小売販売するもの。代表例は菓子の製造販売、豆腐の製造販売、魚介類の販売など。
- 飲食店営業または喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者。代表例はそうざい製造業、パン製造業、学校・病院等の営業以外の集団給食施設、調理機能を有する自動販売機など。
- 容器包装に入れられ、または容器包装で包まれた食品のみを貯蔵・運搬または販売する営業者
- 食品を分割して容器包装に入れ、または容器包装で包み小売販売する営業者。代表例は八百屋、米屋など。
- 食品を製造・加工・貯蔵・販売し、または処理する営業を行う者のうち、食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満である事業場。
HACCPの7原則12手順
手順1~手順5は危害要因の分析を適切に実施するための準備段階です。
- 手順1
製品の全ての情報が集まるように各部門の担当者が集まってHACCPチームを結成する - 手順2
自社製造商品を書き出す。名称や種類、原材料や添加物、製品特性、包装形態・単位・量、容器包装の材質、消費期限、保存方法などを詳細にまとめる - 手順3
商品が誰にどのように食されるか書き出す。非加熱か加熱か、高齢者や幼児も食するかなど - 手順4
商品の製造方法を書き出す。原材料の受入から保管、製造、加工、包装、出荷までの一連の流れを把握する。温度や時間も含めて製造の工程図を作ってみる - 手順5
手順4で作成した製造工程図を現場で確認し、必要であれば修正していく
コーデックスのHACCP7原則
以下は手順6~手順12に該当します。
- 危害要因の分析
食品または添加物の製造、加工、調理、運搬、貯蔵または販売の工程ごとに、食品衛生上の危害を発生させ得る要因(危害要因)の一覧表を作成し、これらの危害要因を管理するための措置(管理措置)を定めること - 重要管理点の決定
1.で特定された危害要因の発生の防止、排除または許容できる水準にまで低減するために管理措置を講ずることが不可欠な工程を重要管理点として特定すること - 管理基準の設定
個々の重要管理点において、危害要因の発生の防止、排除または許容できる水準にまで低減するための基準(管理基準)を設定すること - モニタリング方法の設定
重要管理点の管理の実施状況について、連続的または相当な頻度の確認(モニタリング)をするための方法を設定すること - 改善措置の設定
個々の重要管理点において、モニタリングの結果、管理基準を逸脱したことが判明した場合の改善措置を設定すること - 検証方法の設定
1.~5.に規定する措置の内容の効果を、定期的に検証するための手順を定めること - 記録の作成
営業規模や業態に応じて、1.~5.に規定する措置の内容に関する書面をその実施の記録を作成すること - 小規模営業者等への弾力的運用
小規模な営業者等は、業界団体が作成し、厚生労働省で確認した手引書に基づいて対応することが可能
HACCPに関する罰則
HACCPが完全義務化されましたが、不備があったり導入していないと判断された場合は罰則等があるのでしょうか?現在のところ、衛生管理の実施状況は営業許可の更新時や保健所の定期的立入りの機会に食品衛生管理員が確認・チェックすることが考えられます。
飲食店の営業許可には有効期限があり、期限前に更新の手続きをしなければなりません。この更新手続きの際にHACCPの各書面を確認される見込みです。
当面の間、支援や助言が中心となりますが、改善の指導が入り、改善が図られない場合は営業停止処分や営業禁止処分といった重い行政処分が下されるおそれがあります。
また、行政処分に従わずに営業を継続すると、拘禁刑または罰金に処される可能性まであります。完全義務化とはこのようなリスクも同時に発生することになるのです。
HACCPを導入するということは、書類を作成して、計画のとおりに実施し、記録し、保管(1年間)する義務を負うということですが、有事の際には自らを助ける証明にもなり得ます
HACCPで実施すること
HACCPを導入するにあたり、実際に事業者や従業員はどのようなことを実施していくのでしょうか。完全施行までの営業者が実施することは以下のとおりです。
- 一般的な衛生管理及びHACCP衛生管理計画を作成して、従業員に周知徹底する
- 必要に応じて清掃・洗浄・消毒や食賃の取扱い方法等について具体的な方法を定めた手順書を作成する
- 衛生管理の実施状況を記録し、保存する
- 衛生管理計画及び手順書の効果を定期的及び工程に変更が生じた際などに検証し、必要に応じて内容を見直す
小規模営業者等については、業界団体が作成して厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして実施すれば法第50条の2第2項の規定に基づき、「営業者は厚生労働省令に定められた一般的衛生管理基準とHACCP衛生管理基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守している」とみなされます。
その上で実施すべき内容は以下のとおりです
- 手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害要因となるか理解する
- 手引書に従い、衛生管理計画を作成する。必要に応じて手順書も作成する
- 内容を従業員に周知する
- 手引書に従い、衛生管理の実施状況を記録する
- 手引書で推奨された期間、記録を保存する
- 記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直す
一般的衛生管理基準
- 食品衛生責任者等の選任
食品衛生責任者の指定や食品衛生責任者の責務に関すること - 施設の衛生管理
施設の清掃、消毒、清潔保持などに関すること - 設備等の衛生管理
機械器具の洗浄、消毒、整備、清潔保持などに関すること - 使用水等の管理
水道水または飲用に適する水の使用、飲用に適する水を使用する場合の年1回以上の水質検査、貯水槽の清掃、殺菌装置・浄水装置の整備などに関すること - ねずみおよび昆虫対策
年2回以上のねずみ(そ族)、昆虫の駆除作業、または定期的な生息調査等に基づく防除装置に関すること - 廃棄物および排水の取扱い
廃棄物の保管・廃棄、廃棄物・排水の処理などに関すること - 食品または添加物を取り扱う者の衛生管理
従事者の健康状態の把握、従事者が下痢・腹痛等の症状を示した場合の判断、作業着や手洗いに関すること - 検食の実施
弁当、仕出し屋等の大量調理施設における検食の実施に関すること - 情報の提供
製品に関する消費者への情報提供、健康被害または健康被害につながるおそれがあるといった情報の保健所への情報提供や報告・連絡に関すること - 回収・破棄
製品回収の必要が生じたときの責任体制、消費者への注意喚起、回収方法、保健所等への連絡、回収製品の取扱いなどに関すること - 運搬
車両・コンテナ等の清掃、消毒や、温度・湿度・時間の管理などに関すること - 販売
適切な仕入れ量、販売中の製品の温度管理に関すること - 教育訓練
従事者の教育訓練、教育訓練の効果検証等に関すること - その他
仕入元・販売先等の記録の作成・保存、製品の自主検査の記録・保存に関すること
HACCPの手引書
小規模営業者等の場合に使用する厚生労働省が確認した手引書。これらはHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書です。手引書は、対象食品、食品群の詳細説明・工程が記載されています。また、団体がまとめた危害要因分析の内容も記載されています。
実際に使用する際には以下の構成に沿って実施します。
- 衛生管理計画の様式と記載例
- 記録の様式と記載例
- 一般衛生管理の項目と重点的に管理する項目
- 振り返り
- 記録の保存期間
食品衛生法
第五十条 厚生労働大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において有毒な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な基準を定めることができる。
② 営業者(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。)は、前項の規定により基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。引用元: e-Gov 法令検索