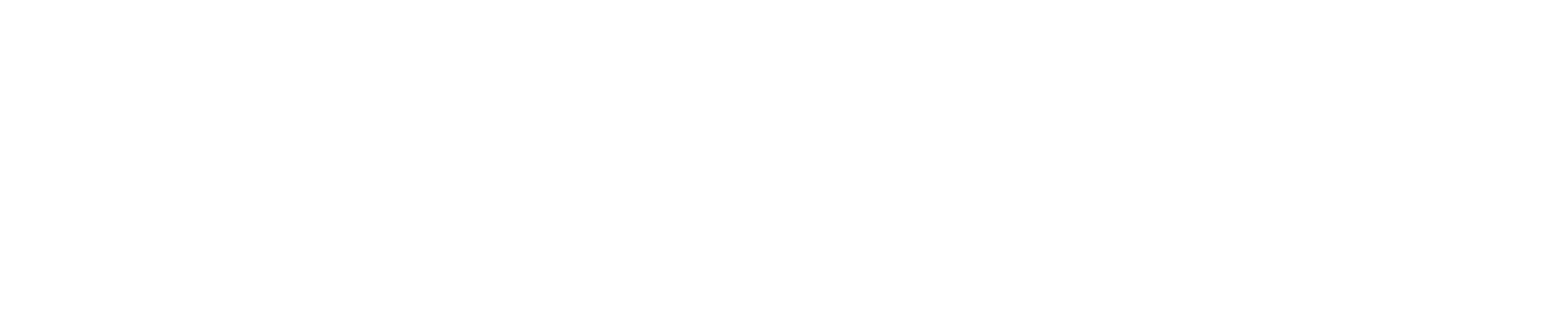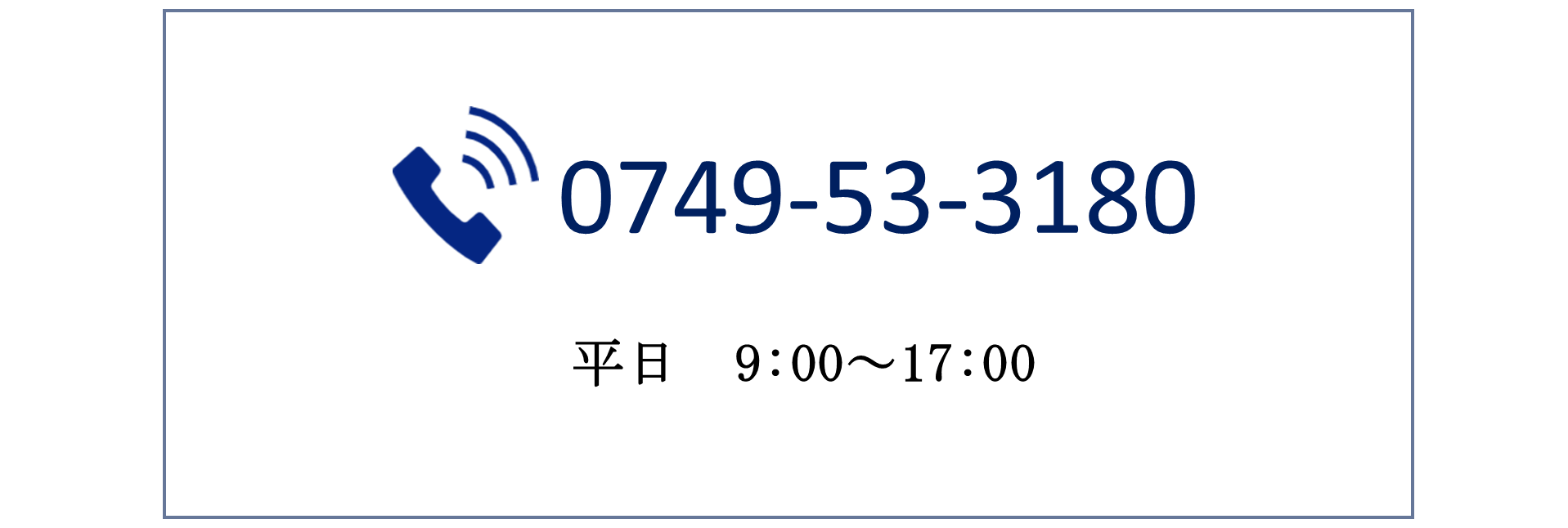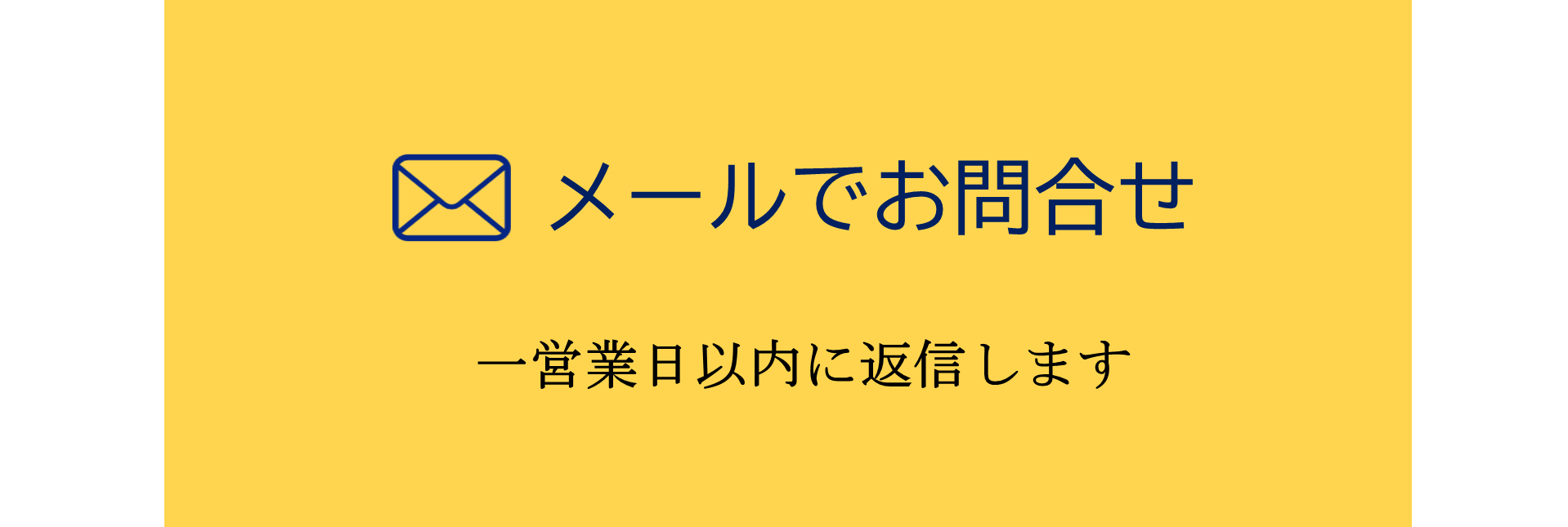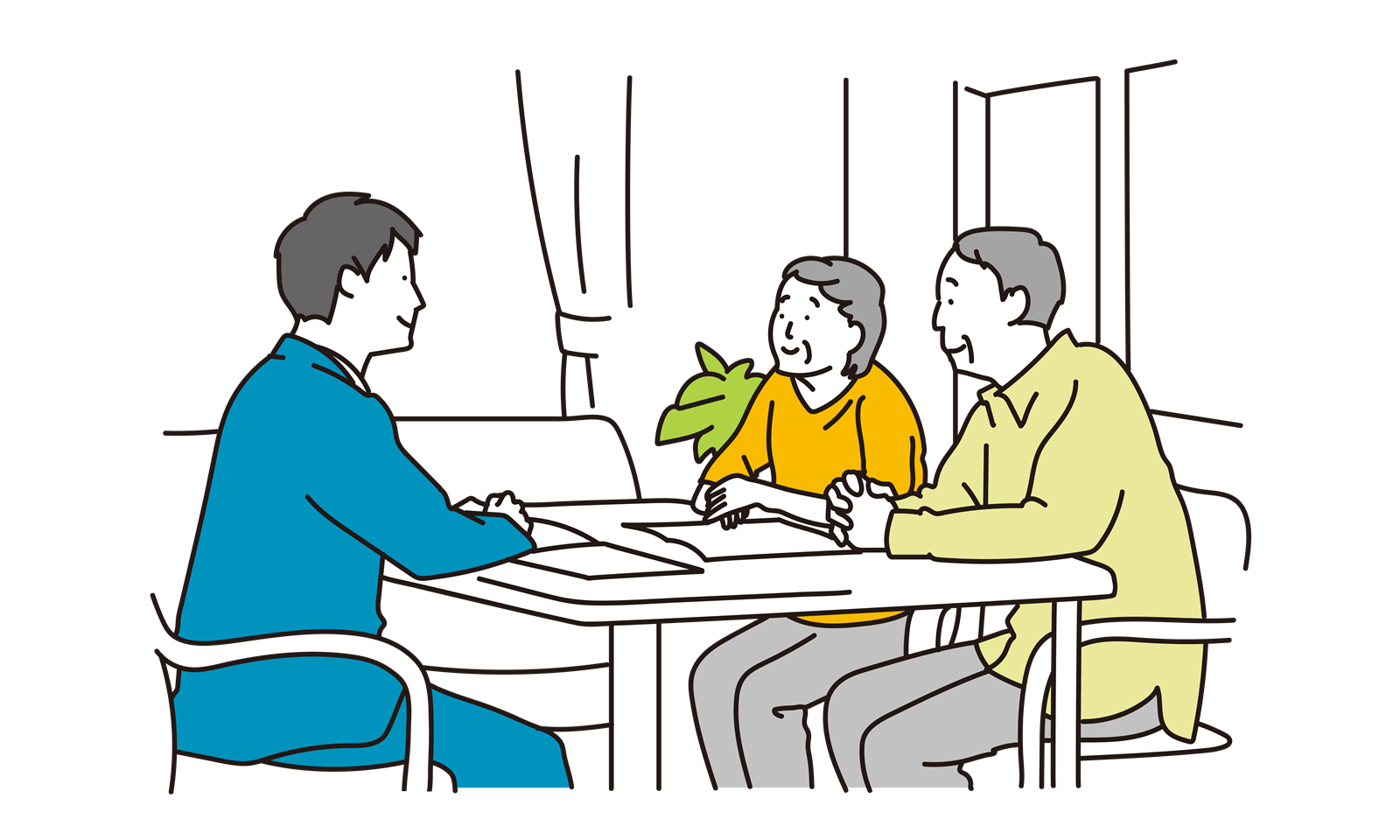建設業許可に関する業務
- 建設業許可申請(新規)
必要な6つの要件を満たしているか確認して新規許可申請をします。申請は迅速な電子申請(JCIP)で行います。電子申請の場合、事前にGビズIDプライムを取得願います。 - 建設業許可申請(更新)
許可の有効期間は5年です。有効期間の30日前までに申請をしなければ許可は失効します。届出義務がある変更が発生している場合は変更届をしておかないと更新できません。 - 決算変更届
毎年決算後4か月以内にしなければならない届出です。届出モレが一度でもあると、許可更新できず失効します。工事を請け負った際に届出に必要な内容を記録しておくことが重要です。 - 各種変更届
役員変更や経管変更など一定の変更が発生すると、届出をする義務があります。2週間以内にする事項もあり、時間がありません。怠ると許可失効の場合もあります。 - 建設キャリアアップシステムの登録
建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者と技能者の登録を代行申請します。当事務所は事業者IDを取得しているCCUS登録行政書士です。
建設業許可に関する業務は、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください。
建設業許可の専門家

当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
| 事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 特定行政書士 川瀬規央 |
| 所在地 |
〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318-15 |
| TEL | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 |
カレンダー通り(役所と同じ) 12/29~1/3は休業 |
| 所属 |
登録番号:第16251964号 |
|
会員番号:第1292号 |
|
|
行政書士 付随資格 |
特定行政書士(不服申立て代理) |
| 入管申請取次行政書士(ビザ申請) | |
| CCUS登録行政書士(建設業許可) | |
| 著作権相談員 |
長浜市・彦根市を中心に滋賀県が受任エリアです
建設業許可のお問合せ
建設業許可のよくある質問
法人ではない個人事業でも要件を満たせば建設業許可を取得できます。下請けで入る場合でも建設業許可業者になっていれば有利なので販路拡大・利益増大に繋がります。
代表取締役の経営業務の管理経験が5年に達していない場合、ご本人が経管(常勤役員等)になることができません。現状で経管の要件を満たせる人がいない場合、建設業許可は取得できません。経管は必須です。
このような場合、経管の要件を満たせる人を取締役として迎え入れて、その人を経管にすれば建設業許可を取得することができます。しかし、その人がもし退職等でいなくなった場合は2週間以内に他の経管に変更する届出をしなければ建設業許可は失効してしまいます。手続きを怠ると、その後5年間は許可が取れなくなることも有り得ます。
経管になる人は取締役でもあるので、何か問題を起こされた場合は法人にも影響が波及する恐れがあるので慎重に決めなければなりません。
すでに建設業許可を持っている場合に他の業種についても許可を取ることはできます。手続きとしては「業種追加」です。こういったケースでは、営業所技術者等(専任技術者)の要件を満たせるかどうかがポイントです。
追加したい業種の営業所技術者等の必要資格を所持している人がいれば円滑に申請をすることができます。また、実務経験10年でいけるだろうと考えている方がおられますが、一業種で10年必要なので、二業種だと20年必要となり相当厳しくなります。
決算変更届は毎年必須の届出です。名称に「変更」と付きますし、確かに変更届というものはたくさんあります。決算変更届は別名「事業年度終了届」といいます。
よって、変更事項の有無に関わらず決算日から4か月以内に届け出る必要があります。これを1度でも怠ると許可更新ができなくなり建設業許可は失効してしまいます。
建設業許可業者の義務として各種変更届があります。変更届の対象事由に役員の変更が該当しますので変更届が必要です。変更届を失念する方は少なくありません。
「そんなの知らなかった」と口をそろえておっしゃられますが、新規許可を取ったときに建設業許可通知書と一緒に資料を受け取っておられます。仮に県庁から案内がなかったとしても無条件で義務を負っているので、ご自身の事業のために自己管理と建設業法のご理解に努めていただきたいと思います。
建設業許可の基礎知識
ここからは建設業許可に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも建設業許可に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
500万円以上は許可が必要
建設業許可とは、建設業を営む際に一定金額以上の請負金額になるときに必要な許認可です。次の軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、建設業許可が不要とされています。
- 1件あたりの請負金額が500万円未満
- 建築一式は、1,500万円未満、又は延べ面積150㎡未満の木造住宅の場合
50㎡未満の木造住宅でも1/2以上を店舗等に使用する場合は建設業許可が必要。木造住宅とは主要構造部が木造で1/2以上を居住に供するものをいいます。
500万円未満でも登録が必要な業種
また、500万円未満の軽微な工事であっても登録や届出をしなければならない業種は以下のとおりです。
- 電気工事業
登録電気工事業者登録が必要。建設業許可があればみなし登録届出が必要 - 解体工事業
解体工事業登録が必要。建設業許可の土木一式、建築一式、解体工事を受けていれば不要
これらは請負金額が500万円未満であっても、滋賀県に登録しなければ工事をすることができませんので注意しなければなりません
建設工事に該当しないもの
以下のものは建設工事には該当しないため、工事経歴書や直前3年工事金額の様式にも記載は不要です。
- 除草、伐採、除雪、測量、採石
- 機械器具修理、造園管理、建売住宅の販売
- 浄化槽の清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃
- 資材の運搬、社屋の工事、人工出し(常用工事)、解体時の金属売却など
建設業法
(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。引用元: e-Gov 法令検索
建設業許可の種類とは
建設業許可の種類とは、2つの項目について区別されており、営業所の所在地に関する区別と請負金額に関する区別です。
建設業の営業所に関する区別
- 県知事許可
建設業の営業所が1つだけの場合や、2つ以上あるが全て同じ都道府県内にある場合の許可 - 大臣許可
建設業の営業所を2つ以上もち、それが2つ以上の都道府県にあるケースの許可
建設工事の請負金額に関する区別
- 特定建設業許可
自社で直接に受注し(元請け)、かつ、1件あたり5,000万円以上の下請けを出す場合は特定建設業許可になります。建築一式は8,000万円以上です - 一般建設業許可
特定建設業許可以外は一般建設業許可です
建設業許可の業種とは
建設業許可の業種とは、建設業法で指定されており、それぞれ自身が請け負う建設業の工事に必要な許可を取得します。建設業許可の業種は以下のとおりです。
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・レンガ工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
建設業許可の申請区分とは
建設業許可の申請区分とは、建設業を営む際に発生する状況を類型化した申請区分です。それぞれの申請区分の中から該当する手続を選択して申請します。
- 建設業許可の新規許可
建設業許可を受けていない業者が新たに取得したり、法人成りするケース - 建設業許可の業種追加
一般でAの建設業許可を受けており、さらに一般でBの建設業許可を追加して取るケース - 建設業許可の許可換え新規
現在、建設業許可を受けている者が、他の行政庁から新たに建設業許可を受けるケース - 建設業許可の般・特新規
異なる業種で特定建設業許可と一般建設業許可を取るなら般・特新規許可に該当。特定許可と一般許可は、同業種で重ねて取れません - 建設業許可の更新
建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新をしなければなりません
建設業許可の要件とは
建設業許可の要件とは、満たさなければ建設業許可の新規許可がおりない条件です。大きくは下記のとおり6つの要件があります。
- 経営業務管理の要件
- 適切な社会保険への加入の要件
- 営業所技術者等(専任技術者)の要件
- 誠実性の要件
- 財産的基礎の要件
- 欠格要件等
経営業務管理の要件
常勤役員等(経営業務の管理責任者)は、経営面での要件を満たす人で、以下のような経験を持った人の常勤が求められます。
- 個人事業は事業主又は支配人
- 法人は常勤の役員のうちの1人
必要な経験の例は以下のとおりです。
- 建設業に関し5年以上の経管としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上の経管に準ずる地位にある者として経営を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上の経管に準ずる地位にある者として経管を補佐した経験
建設業においての役員は、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者です。「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長等は役員には含まれません。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)の確認資料で代表的なものは以下のとおりです。これらに加えて常勤であることの確認資料も必要です。
- 個人事業主としての経験
確定申告書等を5年分+工事請負契約書(発注者からの注文書)を年1件5年分 - 法人の役員としての経験
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)で5年以上の期間が記載+工事請負契約書(発注者からの注文書)を年1件5年分
営業所技術者等(専任技術者)の要件
営業所技術者等(専任技術者)は、技術面での要件を満たす人で、以下のような経験を持った人の常勤が求められます。
- 申請する建設業について定められた資格を持っている
- 申請する建設業について指定された学科を卒業し、かつ、実務経験がある
- 申請する建設業について10年以上の実務経験がある
他には「2年以上の指導監督的実務経験を有する者」も認められます。営業所技術者等(専任技術者)は、当該営業所の常勤でなければなりませんので、他の会社で営業所技術者等(専任技術者)として登録されている人は認められません。
資格・免許がなく指定学科卒業でもない方は、1業種につき10年以上の実務経験を証明して満たさなければなりません。実務経験証明書を作成して証明資料として3年分(滋賀県の場合)の請負契約書等を添付します。資格+実務経験のパターンでは、資格を取得した後の実務経験でなければなりません。
営業所技術者等(専任技術者)の確認資料は以下のとおりです。これらに加えて常勤であることの確認資料も必要です。
- 資格免許を有する者の場合
合格証明書や免許証の写し。実務経験を併せて必要とする資格免許は実務経験証明書+契約書等も必要 - 所定学科卒業者等の場合
卒業証明書等の写しと実務経験証明書+契約書等 - 10年以上の実務経験を有する者の場合
実務経験証明書+契約書等
適切な社会保険への加入要件
令和2年10月1日の建設業法改正により、社会保険の適用事業所に関し、届出をしていることが要件となりました。健康保険、厚生年金保険、雇用保険のいずれかに未加入があると許可は取れません。
- 社会保険(健康保険、厚生年金保険)
法人はすべての事業所、個人事業は常時従業員を5名以上雇用している事業者 - 雇用保険
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません。ただし、法人の役員、個人事業主と同居家族等は除きます。原則としてパート・バイトを含めて労働者を1人でも雇用すれば適用事業所となります
財産的基礎の要件
施主を保護するためにも一定の財産的能力を問われます。必要とされる財産は、一般建設業許可での財産要件はは以下のとおりです。
- 500万円以上の自己資本がある
貸借対照表の純資産合計が500万円以上なら可 - 500万円以上の資金調達力がある
金融機関の残高証明書で証明できます - 過去5年間継続して建設業許可業者である
業種追加や更新の場合です
建設業許可の欠格要件
人的な欠格要件です。以下のいずれにも該当しないことです。(簡略に記載しています)
- 申請書に虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正に許可を受けたこと、営業停止処分等により許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出をし、その日から5年を経過しない者
- 適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき
- 請負契約に関し不適切な行為をしたことにより営業停止を命じられ、停止期間が経過しない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
なお、暴力団排除条例に基づき、暴力団関係者や反社会的勢力に属する方のご依頼は受任できません。
建設業法
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の八第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。引用元: e-Gov 法令検索
建設業許可の申請先等
新規許可申請、業種追加、般特新規申請は予約制となっており、受付日は月・水・金曜日(休日・閉庁日等は除く)の午前9時から12時 午後1時から4時となっております。申請先は次のとおりです。
- 滋賀県大津市京町四丁目1番1号(滋賀県庁新館5階)
- 土木交通部監理課建設業係
- 直通電話077-528-4114
建設業許可の日数ですが、申請時に提出書類をチェックされ、不備が無ければ受理されて審査に入ります。申請後おおむね30日で許可となります(標準処理期間)
電子申請(JCIP)にも対応可能
電子申請(JCIP)は、申請先の窓口(滋賀県庁)へ行かなくても電子申請で手続きができるシステムです。当事務所では電子申請にも対応しており、新規許可申請は原則としてJCIPにて申請いたします。
建設業許可の電子申請は、「GビズIDプライム」が必須ですので事前に取得しておいてください。電子上で委任状の取り交しを必要があるからです。当事務所に建設業許可の申請をご依頼の場合、必要書類等をご持参いただければ当事務所でGビズIDプライムを取得します。
建設業許可の手数料
建設業許可の申請のときに納める申請手数料です。
滋賀県知事許可の手数料
- 新規(許可換え新規、般特新規含む)
申請手数料は90,000円 - 業種追加、更新
申請手数料は50,000円
国土交通大臣許可の手数料
- 新規(許可換え新規、般特新規含む)
登録免許税は150,000円(納付書) - 業種追加、更新
申請手数料は50,000円(収入印紙)
建設業許可の更新とは
建設業許可の更新とは、建設業許可の有効期間である5年を経過する前にする許可更新の申請です。建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了します。
引き続いて建設業を営もうとする方は、有効期間が満了する30日前までに更新の手続きをしなければなりません。期間満了日までに更新の手続きをすればいいわけではありません。
建設業許可の更新は、滋賀県知事許可は有効期間満了の日の3か月前から、国土交通大臣許可は6か月前から手続きができます。更新時には、全ての年度分の決算変更届を提出していなければ更新できません
建設業許可取得後の届出
建設業許可を取得した後で、一定の状況が発生した場合には届出をしなければなりません。義務とされる届出は以下のとおりです。
決算変更届
決算変更届とは、事業年度終了届ともいわれている届出で、決算終了後4か月以内にすべての建設業許可業者が届出しなければなりません。
決算変更届を1年でも怠っている場合、建設業許可の更新ができなくなるので、注意が必要です。また、各種変更届の提出を怠ると、建設業法違反となり、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます。
決算変更届の必要書類
- 決算変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の工事履歴
- 財務諸表(確定申告書や決算書ではなく建設業法に沿ったもの)
- 納税証明書(個人事業税または法人事業税の税目)
- 事業報告書(株式会社のみ)
事業年度内に以下の変更があった場合
- 使用人数に変更があった場合
- 営業所長の異動があった場合
- 定款の変更があった場合
- 健康保険等加入状況に変更があった場合
これらに該当する場合は、追加して必要な届出の様式を提出します。
各種変更届とは
変更届は、決算変更届とは若干異なり、毎年定期で届出をするものではありません。下記の変更が生じた場合、変更届をする義務があります。
事実発生から2週間以内に届出
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の氏名変更
- 営業所技術者等(専任技術者)の変更
- 営業所技術者等(専任技術者)の氏名変更
- 許可要件を欠く廃業届
事実発生から30日以内に届出
- 商号または名称の変更
- 営業所の名称・所在地の変更
- 営業所の新設
- 営業所の業種変更
- 営業所の廃止
- 資本金額の変更
- 役員の変更
- 事業主の氏名変更
- 支配人の氏名変更
- 営業所長の変更
他には、「廃業届・全部廃業と一部廃業は廃業日より30日以内」、「国家資格者・監理技術者の変更は決算終了後4か月以内、出来る限り変更があった時点」です。
建設業法
(変更等の届出)
第十一条 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4 許可に係る建設業者は、営業所に置く営業所技術者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は第七条第二号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。引用元: e-Gov 法令検索
建設キャリアアップシステムとは
建設キャリアアップシステム(CCUS)の概要
建設キャリアアップシステムとは、建設業を営む事業所と、そこに従事する技能者がシステムに登録して「見える化」を実現するものです。技能者にはIDカードを発行し、元請と下請の間も工事情報等を登録します。
工事現場では工事情報等を登録し、設置したカードリーダーで技能者のIDカードを読み込みます。建設キャリアアップシステムは、技能者個人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげます。
建設業界は人材不足が著しく、高年齢化も年々進行しています。若い方でこれから建設業に従事しようと考え、従業先を選定する場合には、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録している事業者を優先することが考えられます。
また、外国人(特定技能等、一定の在留資格を所持する外国人)を雇用する場合は建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が義務化されています。さらに近い将来にはすべての建設業許可業者に対して義務化される可能性もあります。
代行申請はCCUS登録行政書士の当事務所へ
CCUS登録行政書士とは、CCUSが実施する「CCUS実務講習」を受講し、CCUSのホームページにおいて連絡先を公表する行政書士の呼称です。CCUS登録行政書士は、自ら事業者IDを取得しているので、建設キャリアアップシステムの事業者登録と技能者登録の代行申請が可能です。
代行申請とは、自らの事業者IDとメールアドレスによって建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録をすることです。システムへの登録作業はCCUS登録行政書士が単独で行うことができます。
一方、代理申請とは、申請人本人のメールアドレスを使用して、申請人本人に代わって登録申請をすることです。代行申請と比べると複雑な手順となり、申請人本人のシステム操作も必要です。
CCUS登録申請の方法
建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録申請方法は、インターネット申請と窓口申請の2通りあります。CCUS登録行政書士に依頼できるのはインターネット申請のみです。
窓口申請は、認定登録機関で申請する方法ですが、予約制で遠方まで赴かなければならず負担が大きく手間がかかります。なお、技能者登録の場合、写真付き本人確認書類をお持ちでない方は認定登録機関でのみ申請可能です。
登録するのは事業者登録と技能者登録の2つですが、まず事業者登録をして事業者IDが発行されてから、技能者の登録をしていきます。
建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録
事業者登録は個人事業主、法人のいずれも可能です。登録する項目は以下のとおりですが、システムに入力するだけではなく、入力した内容を証明するための様々な書類を電子上で添付する必要があります。添付書類は指定された書類の中からマッチするものを選択し、必要箇所をマスキングしてJPEGにしなければなりません。
事業者登録の項目
- 建設業許可の有無
- 資本金情報
- 完成工事高情報
- 登録責任者
- 建設業許可情報
- 健康保険
- 年金保険
- 雇用保険
- 建設業退職金共済制度
- 中小企業退職金共済制度
- 労災保険特別加入
- CI-NET、電子証明書、主要取引先、表彰履歴、所属団体(これらは任意)
事業者登録料
事業者登録には、事業者がCCUSを利用する際に必要な登録料の支払いが必要です。登録の有効期限は5年間ですので更新も必要です。法人の場合の登録料は事業者の資本金額をもとに決まります。なお、CCUS登録行政書士に依頼する場合は行政書士への報酬等の支払いも必要です。
| 資本金 | 新規・更新 | |||||||||||||||||||||||
| 500万円未満 | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 1億円以上3億円未満 | 120,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 3億円以上10億円未満 | 240,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 10億円以上50億円未満 | 480,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 50億円以上100億円未満 | 600,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 100億円以上500億円未満 | 1,200,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 500億円以上 | 2,400,000円 | |||||||||||||||||||||||
個人事業主は一律6,000円、一人親方は無料です。
管理者ID利用料
事業者がCCUSにおいて事業者情報(現場情報を含む)を管理するために必要となる管理者IDに対する利用料金です。利用可能期間は取得・更新日から1年後の取得日の属する月末までなので、毎年支払う必要があります。
| ID数 | 利用料 | |||||||||||||||||||||||
| 一人親方 | 2,400円 | |||||||||||||||||||||||
| ID数ひとつあたり | 11,400円 | |||||||||||||||||||||||
現場利用料
CCUSのシステムにおいて現場・契約情報を登録した元請事業者に対し、当該現場における技能者就業履歴情報の登録回数(現場に入場する技能者の人日単位)に対する利用料金であり、一定期間ごとの事後精算で支払います。
| 就業履歴回数 | 利用料 | |||||||||||||||||||||||
| 1回 | 10円 | |||||||||||||||||||||||
建設キャリアアップシステム(CCUS)の技能者登録
事業所登録が完了して事業所IDが発行されたら、技能者ひとりひとりについて技能者登録をします。登録完了の後に発行されるIDカードを現場に設置してあるカードリーダーで読み取ります。
技能者の能力評価の対象として、経験(就業日数)、知識・技能(保有資格)、マネジメント能力(登録基幹技能者・職長経験)をCCUSにより客観的に把握し、レベル判定によりスキルアップも見える化できます。
技能者登録の項目 ※詳細型の場合
- 本人情報(氏名や住所など)
- 登録する型(簡略型または詳細型を選択)
- 主たる所属事業者
- 複数の事業者に雇用されている場合は、他の所属事業者
- 職種
- 入力した職種についての経験等
- 健康保険
- 年金保険
- 雇用保険
- 建設業退職金共済制度
- 中小企業退職金共済制度
- 労災保険特別加入
- 健康診断
- 学歴
- 保有する登録基幹技能者
- 保有資格
- 研修等の受講履歴
- 表彰
技能者の登録料
技能者がCCUSを利用する際に必要な登録料です。カード有効期間は10年間(申請時60歳以上の方の有効期間は15年間)です。本人確認書類未提出者は同2年目の誕生日までが有効期限です。
| 簡略型 登録料 | 2,500円 | ネット申請のみ。本人情報、所属事業者情報、社会保険情報 | ||||||||||||||||||||||
| 詳細型 登録料 | 4,900円 | ネット申請と認定登録機関。簡略型+保有資格情報等 | ||||||||||||||||||||||
レベル判定をするためには、詳細型での技能者登録が必須となっています。技能者個人のスキルを見える化するためにも、詳細型を選択して保有資格情報を登録することをおすすめします。