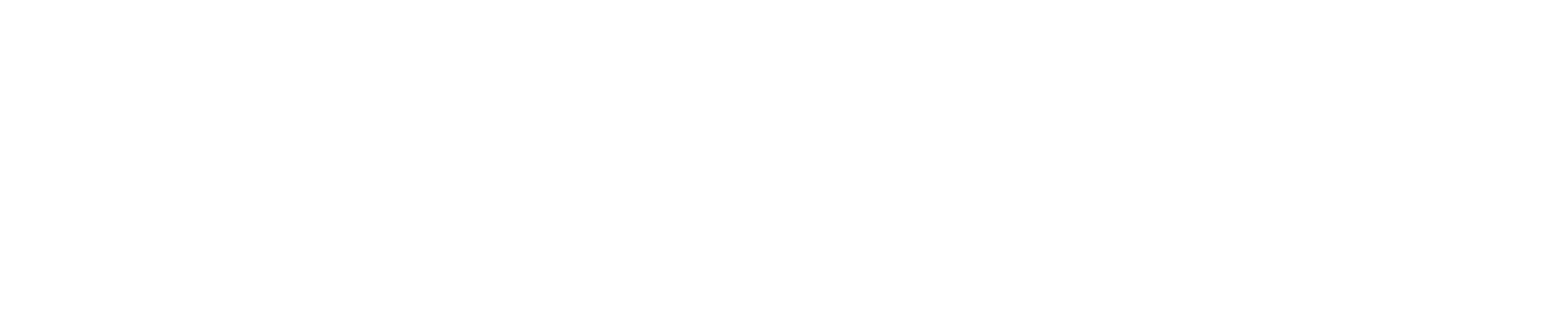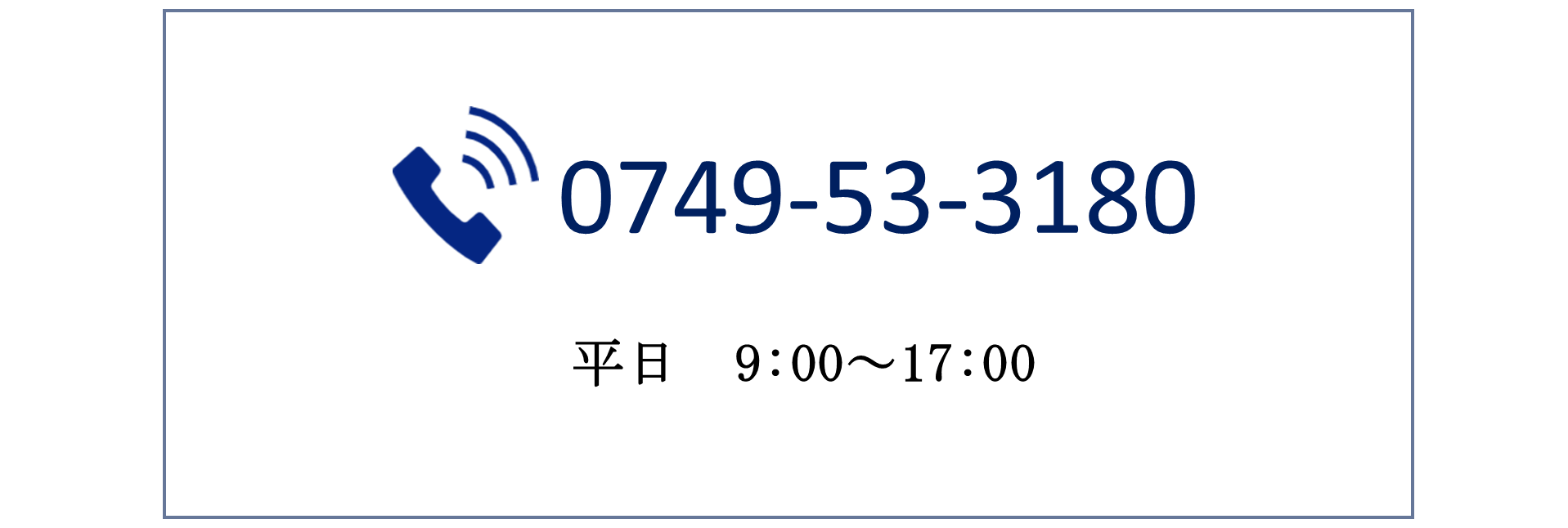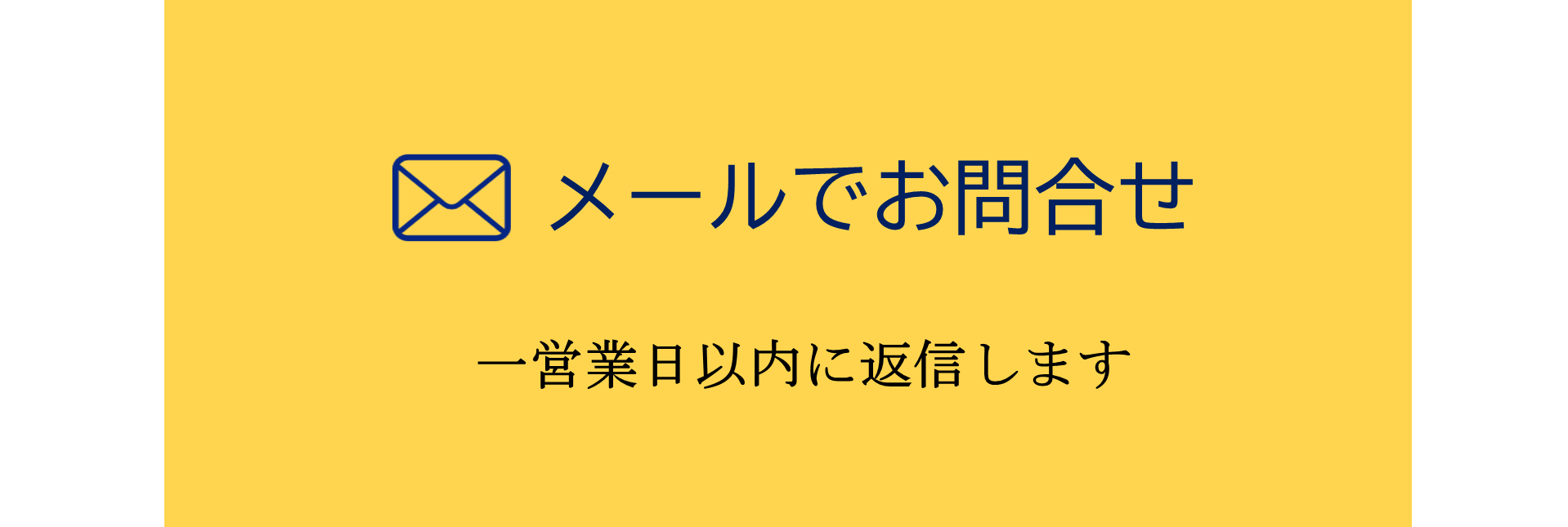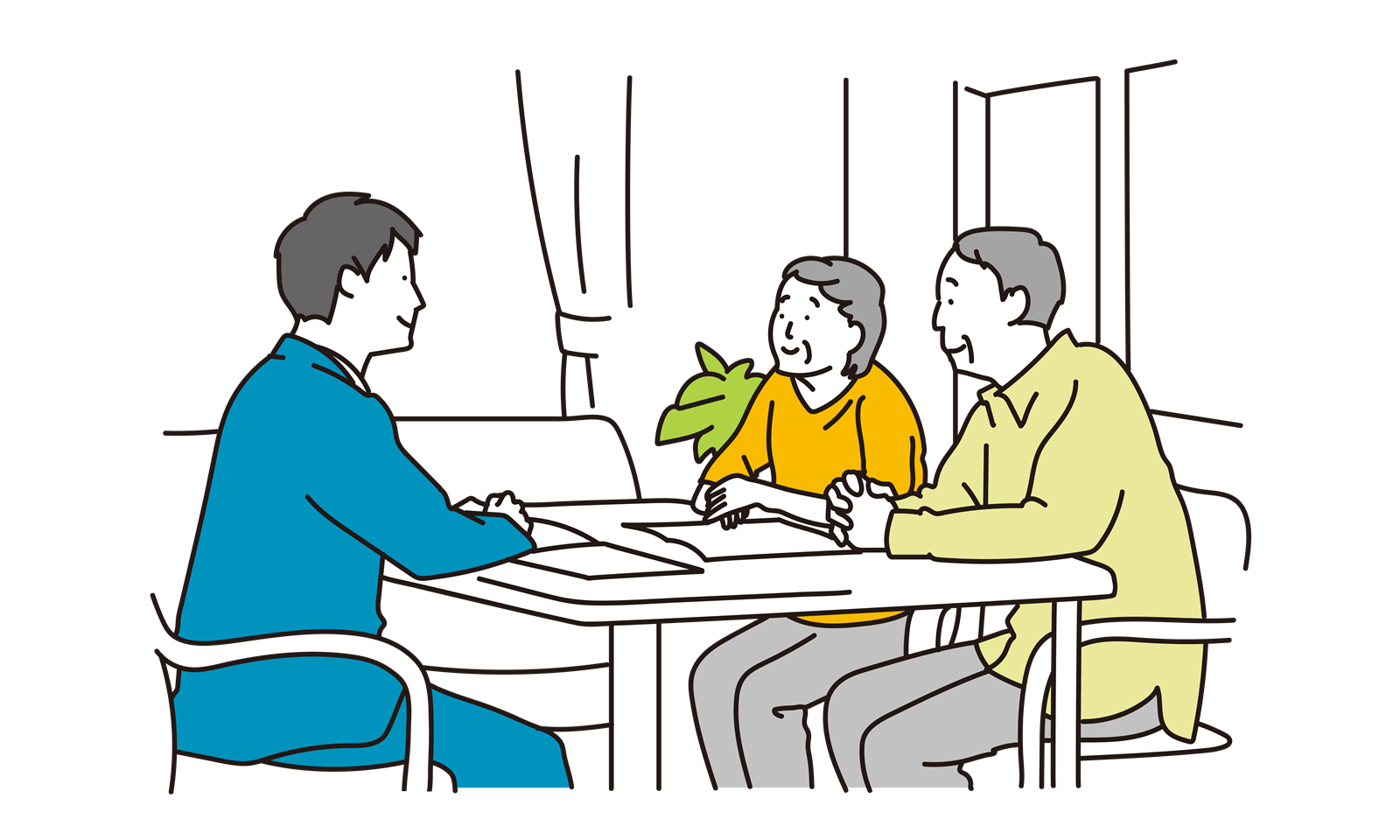ビザ申請に関する業務
- 在留資格認定証明書交付申請
外国から外国人を日本へ呼び寄せるビザ申請です。オンライン申請なら在留資格認定証明書はメール発行ですので迅速です。在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。 - 在留資格変更許可申請
現在所持している在留資格から、別の在留資格へ変更するビザ申請です。大学生の新卒を雇用する場合はこちらのビザ申請になります。 - 在留期間更新許可申請
現在所持している在留資格の有効期間を更新するためのビザ申請です。有効期間の3か月前から手続き可能です。 - 永住許可申請
永住要件をすべて満たす場合に申請する永住権のビザ申請です。永住許可を取得すると、在留期間更新が不要になります。
これらの他にもビザ申請の業務があります。ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください。
ビザ申請の専門家

当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
| 事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 特定行政書士 川瀬規央 |
| 所在地 |
〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318-15 |
| TEL | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 |
カレンダー通り(役所と同じ) 12/29~1/3は休業 |
| 所属 |
登録番号:第16251964号 |
|
会員番号:第1292号 |
|
|
行政書士 付随資格 |
特定行政書士(不服申立て代理) |
| 入管申請取次行政書士(ビザ申請) | |
| CCUS登録行政書士(建設業許可) | |
| 著作権相談員 |
長浜市・彦根市を中心に滋賀県が受任エリアです
ビザ申請のお問合せ
ビザ申請のよくある質問
留学ビザから就労ビザへの在留資格変更許可申請が必要です。就労ビザの代表的なものは「技術・人文知識・国際業務(技人国)」という在留資格です。
履修科目と就職後の従事業務のマッチングを確認して要件を満たせるかを確認して申請となります。ご本人はもちろん、雇用主である会社側に対する審査をされます。実務としてはカテゴリー1~4のいずれかに該当するので、そのカテゴリーに該当する必要書類を揃えます。
在留期間更新許可申請が必要です。夫:日本人、妻:外国人なので、このケースでは「日本人の配偶者等」という在留資格が圧倒的多数です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労ビザ、で母国から呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請が必要です。
オンライン申請なら迅速なだけでなく、在留資格認定証明書をメール交付にし、ご本人様にメール転送で納品することができるので。簡単・円滑に日本に来ることができます。
日本在留している方が所持している在留資格の種別により家族を呼び寄せできるかどうかが決まります。可能な在留資格(技人国ビザ等)なら、在留資格「家族滞在」で在留資格認定証明書交付申請をします。
家族滞在は就労資格ではないので、働くことはできませんが、資格外活動許可を取得すればアルバイトをすることができます。ただし、週28時間以内などの制限があり、これに違反すると不法就労で罰せられます。なお、雇用した側も不法就労助長罪となり、大変厳しい処分になってしまいますので要注意です。
ビザ申請の基礎知識
ここからはビザ申請に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでもビザ申請に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
ビザ申請とは
ビザ申請とは、在留資格に係る申請のことをいいます。外国の方が日本に在留するためには、在留資格を得なければなりません。ビザ申請は出入国在留管理局が窓口となります。
当事務所が業務で行う「ビザ申請」は、日本人が外国へ渡航する際のビザ取得のことではなく、外国人が日本に在留するための「在留手続き」です。
ビザ申請の流れ
- ビザの種類を検討
大きく区別すると就労資格(就労ビザ)、非就労資格、居住資格、特定活動の4種類です - ビザ申請の種類を確定
在留資格認定、変更、更新、永住などです - ビザ申請の許可要件を検討
申請人の要件を検討します。ヒアリングさせていただきますが、外国人の方は通訳の方も加わっていただきます - 申請書作成と資料準備
必要書類も揃えなければなりませんが、証明写真のように申請人からいただくものもあります。揃ったら申請書を作成します - 入管へビザ申請
申請書等が出来上がったら入管へビザ申請します。当事務所は申請取次行政書士なので、本人の入管への出頭は免除されます - 在留カード等の交付
許可の場合、在留カードや認定証明書が交付され、納品をもって委任業務は完了です
当事務所では不正な申請は一切いたしません。申請人(もしくは雇用主)と必ず面談し、本人確認をいたします。ブローカー・人身あっせん業者からの依頼はお断りします
在留資格の種類とは
在留資格の種類とは、外国人が日本に在留するために、その目的とマッチした種類の在留資格を所持しなければならず、在留目的によって定められているものです。
ビザは大きく分けて「活動資格」と「居住資格」の2パターンです。活動資格は、『本邦でする仕事によって』発給されるビザである「就労資格」が主になっています。
就労資格
- 外交
外国政府の大使、公使など - 公用
外国政府の大使館、領事館の職員など - 教授
大学教授など - 芸術
作曲家、画家、著述家など - 宗教
外国の宗教団体から派遣される宣教師等 - 報道
外国の報道機関の記者、カメラマンなど - 高度専門職
ポイント制による高度人材 - 経営・管理
企業等の経営者、管理者など - 法律・会計業務
弁護士、公認会計士など - 医療
医師、歯科医師、看護師など - 研究
政府関係機関や私企業等の研究者など - 教育
中学校、高等学校の語学教師など - 技術・人文知識・国際業務
エンジニア、通訳、デザイナーなど - 企業内転勤
外国の事業所からの転勤者など - 興行
俳優、歌手、プロスポーツ選手など - 技能
外国料理の調理師、パイロットなど - 技能実習
技能実習制度の技能実習生 - 特定技能
単純労働も可能なビザ
非就労資格
- 文化活動
日本文化の研究者など - 短期滞在
観光客など - 留学
大学、短大、高等専門学校等の学生 - 研修
研修生 - 家族滞在
在留外国人が扶養する配偶者、子など
居住資格(身分資格)※就労制限なし
- 永住者
永住許可を受けた人 - 日本人の配偶者等
日本人の配偶者、子 - 永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者、子 - 定住者
日系3世、中国残留邦人など
個々に与えられる特定の資格
- 特定活動
外交官家の事使用人、ワーキングホリデーなど
就労ビザとは
就労ビザとは、活動資格の在留資格のなかで就労が認められているビザです。就労ビザはそれぞれ日本での仕事内容に合致したビザを取得します。
就労ビザの在留資格認定証明書交付申請
就労ビザで日本に在留する外国人を母国から呼び寄せる場合の在留手続きは、在留資格認定証明書交付申請です。この申請によって、在留資格認定証明書を取得します。
交付された在留資格認定証明書を本国にいる本人に郵送します。受け取った本人が、外国にある日本大使館や領事館でこの証明書を提示して査証(ビザ)の発給を申請すれば、査証の発給は迅速に行われます。
当事務所は電子申請に対応しており、電子申請なら在留資格認定証明書をメール送信してもらえるので、申請人へメール転送すれば母国での手続きが速く簡潔にできます。
在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。処分(許可または不許可)までの標準処理期間は1~3か月ですので、有効期間を考慮して申請する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請については、「短期滞在ビザ」は対象外です
出入国管理及び難民認定法
(在留資格認定証明書)
第七条の二 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
3 特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。
5 前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。引用元: e-Gov 法令検索
就労ビザの在留資格変更許可申請
在留資格変更とは、現在所持している在留資格から他の在留資格へ変更するときの許可申請です。
例としては、「留学」のビザで大学生として在留していたが、卒業・就職に伴い「技術・人文知識・国際業務」のビザへ変更するようなケースです。なお、短期滞在ビザからの変更は特別な事情がなければ許可されません。
出入国管理及び難民認定法
(在留資格の変更)
第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
二 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載
三 第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載
5 第三項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。引用元: e-Gov 法令検索
就労ビザの在留期間更新許可申請
在留期間更新とは、日本に在留している外国人が、現在与えられているビザと同じ活動を行うために、在留期間を超えて、日本に在留する場合に必要な手続です。
在留資格には「永住者」を除いて、すべてに在留期間が設けられており、これらのビザを更新して引き続き日本で在留するのであれば、在留期限が切れる前に在留期間更新許可申請のビザ申請をしなければなりません。
在留期間が過ぎてしまうと不法残留として退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の拘禁刑もしくは拘禁刑または300万円以下の罰金」が課せられることもあります。
出入国管理及び難民認定法
(在留期間の更新)
第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。引用元: e-Gov 法令検索
結婚ビザ(配偶者ビザ)とは
結婚ビザ(配偶者ビザ)とは、日本人の配偶者・子として日本に在留する場合の、日本人の配偶者等という在留資格です。
結婚ビザの在留資格認定証明書交付申請
日本人と結婚して配偶者として日本に在留する外国人を、母国から呼び寄せる場合の在留手続きは、在留資格認定証明書交付申請です。この申請によって、在留資格認定証明書を取得します。
交付された在留資格認定証明書を本国にいる本人に郵送します。受け取った本人が、外国にある日本大使館や領事館でこの証明書を提示して査証(ビザ)の発給を申請すれば、査証の発給は迅速に行われます。電子申請なら在留資格認定証明書をメール送信してもらえるので、申請人へメール転送すればOKです。
在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。処分(許可または不許可)までの標準処理期間は1~3か月ですので、有効期間を考慮して申請する必要があります。
結婚ビザの在留資格変更許可申請
在留資格変更とは、現在所持している在留資格から他の在留資格へ変更するときの許可申請です。
例としては、就労資格で日本に在留している外国人が日本人と結婚して配偶者となったとき、従前に受けていた在留資格から、日本人の配偶者等の在留資格へ変更するようなケースです。
結婚ビザの在留期間更新許可申請
在留期間更新とは、日本に在留している外国人が、現在与えられているビザと同じ活動を行うために、在留期間を超えて、日本に在留する場合に必要な手続です。
在留資格には「永住者」を除いて、すべてに在留期間が設けられており、これらのビザを更新して引き続き日本で在留するのであれば、在留期限が切れる前に在留期間更新許可申請のビザ申請をしなければなりません。
在留期間が過ぎてしまうと不法残留として退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の拘禁刑もしくは拘禁刑または300万円以下の罰金」が課せられることもあります。
家族滞在ビザとは
家族滞在ビザとは、高度専門職、経営・管理、医療、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、特定技能2号などの在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子が家族として日本に在留するための在留資格です。
家族滞在ビザの対象は配偶者と子であり、親は含まれません
家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付申請
日本に在留している一定の外国人に扶養される配偶者・子を日本に呼び寄せる場合の在留手続きは、在留資格認定証明書交付申請です。この申請によって、在留資格認定証明書を取得します。
交付された在留資格認定証明書を本国にいる本人に郵送します。受け取った本人が、外国にある日本大使館や領事館でこの証明書を提示して査証(ビザ)の発給を申請すれば、査証の発給は迅速に行われます。電子申請なら在留資格認定証明書をメール送信してもらえます。
在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。処分(許可または不許可)までの標準処理期間は1~3か月ですので、有効期間を考慮して申請する必要があります。
家族滞在ビザの在留期間更新許可申請
在留期間更新とは、日本に在留している外国人が、現在与えられているビザと同じ活動を行うために、在留期間を超えて、日本に在留する場合に必要な手続です。
在留資格には「永住者」を除いて、すべてに在留期間が設けられており、これらのビザを更新して引き続き日本で在留するのであれば、在留期限が切れる前に在留期間更新許可申請のビザ申請をしなければなりません。
在留期間が過ぎてしまうと不法残留として退去強制の対象になるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の拘禁刑もしくは拘禁刑または300万円以下の罰金」が課せられることもあります。
永住ビザとは
永住ビザとは、法務大臣が永住を認めることをいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごすためのビザです。永住ビザは永住許可を受けなければなりません。
永住者のメリットは、在留活動や在留期間に制限がないことです。自由に活動することができて、ビザ更新をすることもないという大きなメリットです。
日本に入国の際に「永住者」の在留資格で上陸を許可されることはありません。永住者以外のビザで在留している外国人が一定の条件を満たすものについて、永住許可のビザ申請をし、認められれば永住ビザが発給されます。
出入国管理及び難民認定法
(永住許可)
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。引用元: e-Gov 法令検索
特定技能ビザとは
特定技能ビザとは、平成30年12月に出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部が改正され、「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、出入国在留管理庁の設置等が盛り込まれました。
特定技能ビザは、今まで禁止されていた外国人の単純労働を認めるビザですが、その運用は他のビザとは比較になりません。単に外国人を雇用するのではなく雇用側(企業側)に様々な義務が課せられ、雇用する外国人の生活支援も必要だからです。
申請書類も他のビザ申請よりもはるかに多いです。特定技能ビザには特定技能1号と特定技能2号があります。特定技能1号から特定技能2号への移行が認められているのは限られた業種です。
特定技能1号
- 在留期間
3年を超えない範囲(上限5年) - 技能と日本語の水準
試験等で確認されます - 家族の滞在
不可です - 支援対象
受入機関又は登録支援機関です
なお、技能実習2号を良好に修了した者は技能試験と日本語試験が免除になります。
特定技能2号
- 在留期間
3年・2年・1年・6月 - 技能水準
試験等で確認されます - 日本語水準
確認不要とされます - 家族の滞在
配偶者と子は可です - 支援対象
対象外です
その他の在留手続き
在留手続きには「在留資格(ビザ)を取得する手続」の他にも在留資格(ビザ)を補助する役目である手続きがあります。代表的なものは以下のとおりです。
資格外活動許可とは
資格外活動許可とは、所持している在留資格の活動を行いながら、その在留資格で認められている活動以外の収入を伴う活動(アルバイト)を行う場合に必要な許可です。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者については居住資格ですので、就労に制限がないため資格外活動許可は不要です。(入管法別表第一に記載の在留資格が対象)
資格外活動許可を必要とする代表的なケースは「留学」のビザをもって留学している学生、「家族滞在」のビザをもって在留する方です。資格外活動許可は無制限に就労してもよいものではありません。
留学生の場合は1週28時間、夏季休暇等は1日8時間、家族滞在の場合は1週28時間です。この1週28時間というのは、何曜日からカウントしても28時間以内という意味です。
また、資格外活動許可は所持しているビザ(在留資格)に付帯して有効な許可ですので、ビザが切れると資格外活動許可も切れるということです。
留学の場合、学校を卒業すると、留学ビザの期限が残っていたとしてもアルバイトをすることはできません。家族滞在ビザの場合は、更新する際に資格外活動許可も取得し直す必要があります。
なお、風俗営業については禁止されています。風俗営業許可が必要な業種・業態での営業所でするアルバイト等が禁止されるということです。代表的な例はスナック、パチンコ店、麻雀店ですが、営業終了後にする清掃活動も禁止です。
就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、申請する者が収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことができることを法務大臣が証明する文書です。
就労資格証明書は、転職しようとする外国人がこの証明書を提出することによって適法で就労可能なビザ(在留資格)を所持していることを証明するものです。
在留期間更新許可申請(ビザ更新)の際に就職先が変わっている場合は更新できない恐れがありますので事前に就労資格証明書を取得しておけば円滑に更新申請ができます。
出入国管理及び難民認定法
(就労資格証明書)
第十九条の二 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。引用元: e-Gov 法令検索
申請取次行政書士とは
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に届出済の行政書士です。通常の行政書士がビザ申請する場合は申請人本人と一緒に入管へ行くことになります。
申請取次行政書士なら、原則として申請人本人の入管への出頭は免除になります。なお、令和4年春から拡大された在留申請オンライン申請制度に当職は登録されており、より迅速に対応することが可能です。