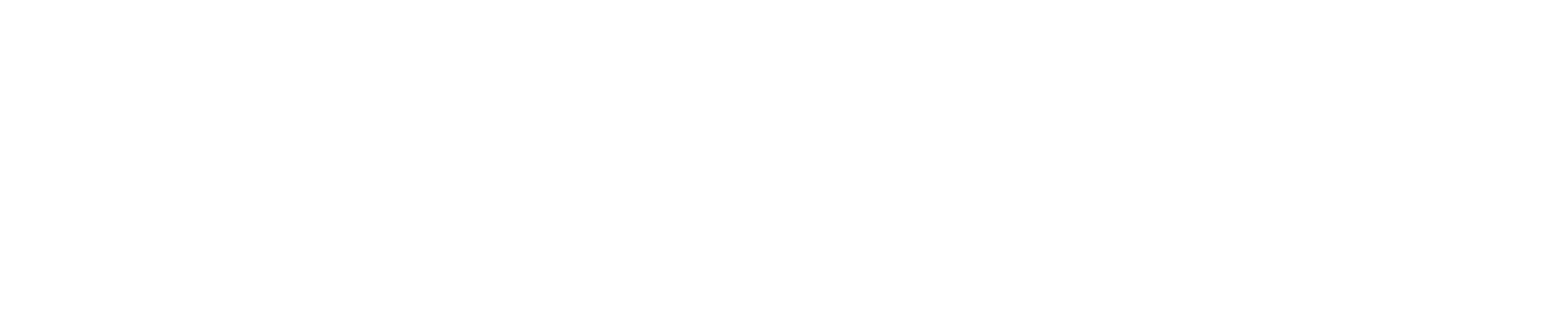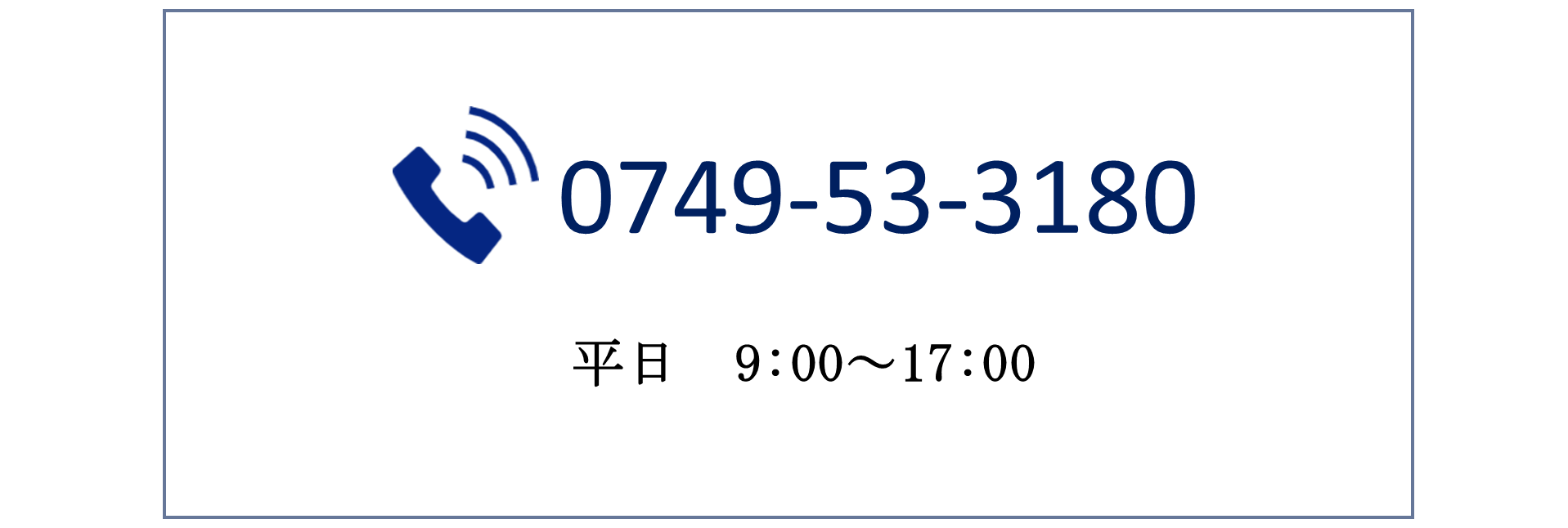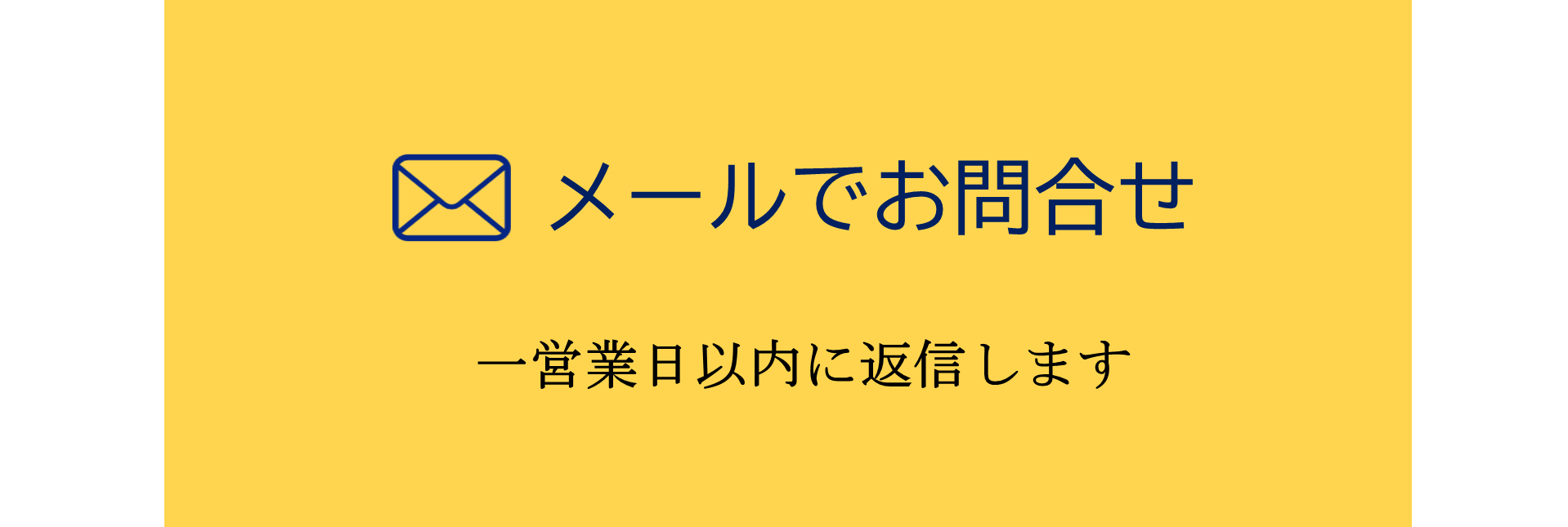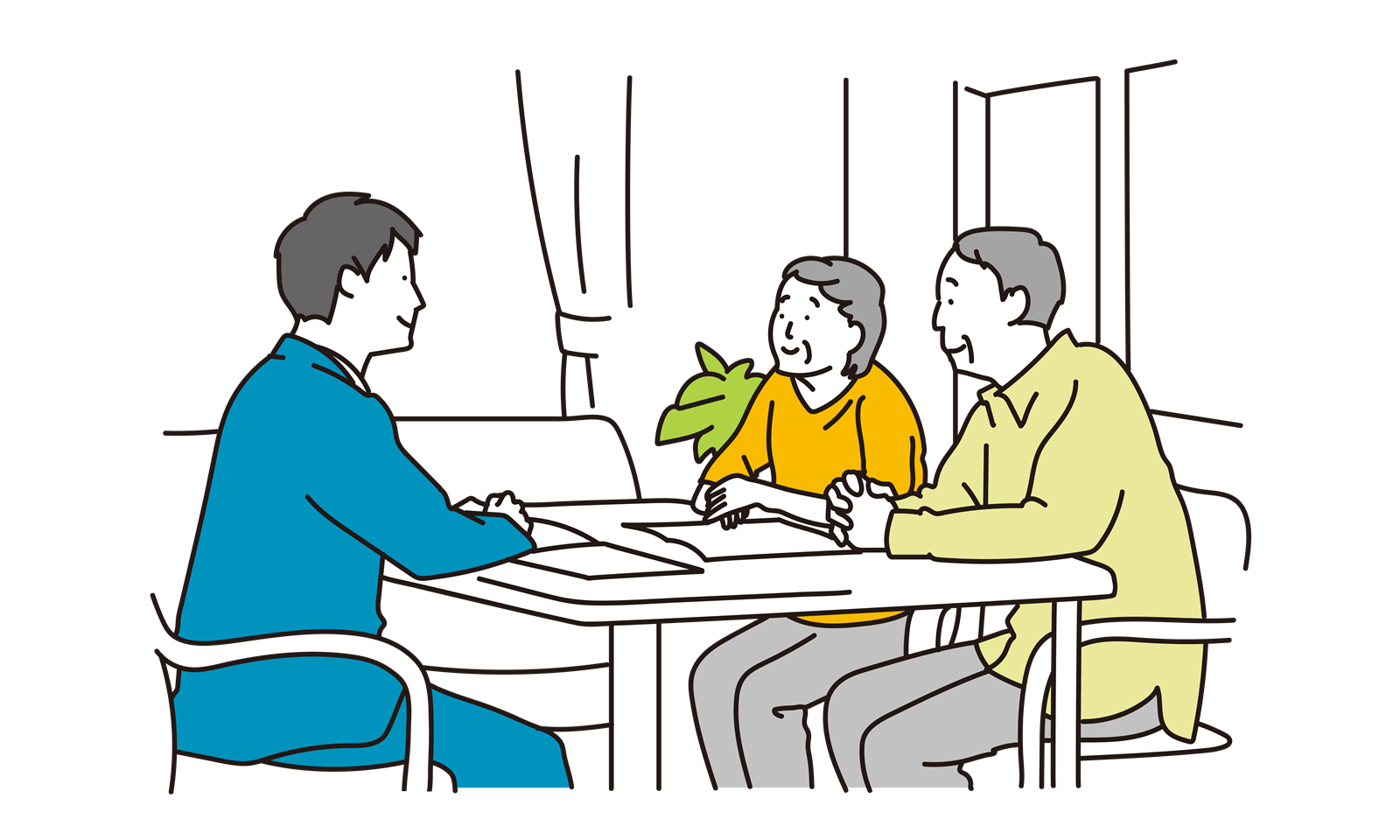告訴状作成に関する業務
- 暴行罪
- 傷害罪、過失傷害罪
- 脅迫罪、強要罪
- 恐喝罪
- 窃盗罪
- 名誉毀損罪、侮辱罪
- 住居侵入罪、不退去罪
- 器物損壊罪、業務妨害罪
- 私文書偽造等罪、公文書偽造等罪
これらの他にも作成できる告訴状があります。ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください。
告訴状作成の専門家

当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
| 事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 特定行政書士 川瀬規央 |
| 所在地 |
〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
| TEL | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 |
カレンダー通り(役所と同じ) 12/29~1/3は休業 |
| 学歴 | 神戸学院大学経済学部卒 |
| 所属 |
登録番号:第16251964号 |
|
会員番号:第1292号 |
|
|
行政書士 付随資格 |
特定行政書士(不服申立て代理) |
| 申請取次行政書士(ビザ申請) | |
| CCUS登録行政書士(建設業許可) |
告訴状作成の相談・お問合せ
告訴状作成のよくある質問
告訴をして逮捕、起訴されて有罪が確定したとしても盗まれたお金は帰ってきません。罰金刑が確定しても被害者へ排してもらえるわけではなく国庫に収まります。
告訴はあくまでも加害者を処罰して欲しいという目的です。お金の返還を望むのであれば、民事上で請求(訴訟)して勝訴判決を得る必要があります。
被害者が生存している場合については、被害者本人、被害者の法定代理人(親権者、未成年後見人など)が告訴できます。
被害者が死亡している場合については、配偶者、直系親族、兄弟姉妹が告訴できます。
被害者の法定代理人、配偶者などが被疑者の場合については、被害者の親族が告訴できます。
当職が言うのもなんですが、弁護士だと言えます。弁護士は警察署への告訴状提出や交渉もお任せすることができ、何度か交渉の上で告訴状受理までいけることも考えられます。また、刑事上だけではなく民事上の裁判で被害を賠償してもらう場合、弁護士なら訴訟代理人になれます。よって、弁護士はなんでもできるというのが理由です。
しかし、弁護士に依頼するとかなりの高額報酬となります。被害額よりも弁護士への報酬額が上回ることも少なくありません。行政書士は告訴状作成のみをお任せいただけますが、その分、報酬額は弁護士と比較すると圧倒的に安価です。
加害者への処罰意思の強さ、民事上での請求の有無、法的手段への覚悟などをもって弁護士に委任するか行政書士に委任するかをご判断いただければと思います。
告訴状作成の基礎知識
ここからは告訴状作成に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも告訴状に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
被害届・告訴・告発の違いとは
- 被害届とは
被害届は、捜査をするかどうかは警察署の判断に委ねられています。被害届はあくまでも犯罪があったことを報告することです - 告訴とは
告訴は、犯罪の被害者等である告訴権者が刑事訴訟法230条に基づいて行うものです。警察署へ犯罪があったことを申告し、犯人に対して処罰を求める意思表示です - 告発とは
告発は、当事者(被害者および遺族など)以外の第三者が犯罪の事実を知った場合に、犯人の処罰を求める意思表示です。
告訴の方法とは
- 資料・証拠・記録等を準備する
刑事告訴の目的は犯罪の捜査と犯人の逮捕・処罰です。告訴状が受理されやすくなるように予め準備をすることはとても重要です。少なくとも、①被告訴人の情報②告訴の趣旨③事件詳細④証拠品は必須で、それぞれ可能な限りを揃えます。 - 告訴状の作成
刑事告訴は、口頭でも可能ですが、警察署で断られることも少なくありませんし、犯罪の事実などをしっかり伝えることはかなり困難です。通常は告訴状を作成し、これを提出して告訴することになります。告訴状は独特の書式と文章で作成しますので一般の方では困難だと思われます。 - 告訴状の提出
告訴状を作成したら警察署へ提出します。提出先は①犯罪が発生した場所②告訴人の居住地③被告訴人の居住地を優先に管轄の警察署です。
警察署での告訴に関する事前相談や交渉、加害者(犯人)との示談交渉については弁護士にのみ認められています。民事で損害賠償をすることもありますが、この代理も弁護士に認められています。
行政書士は警察署に対する告訴状・告発状の作成、司法書士は検察庁に対する告訴状・告発状の作成が業務です。弁護士はすべて可能ですが、報酬は非常にお高いのでよくご検討ください。
告訴状の受理とは
警察署では、告訴状を受理した場合は必ず捜査をしなければなりません。刑事訴訟法では、告訴人に対しては事件処理の通知を行わなければならず、告訴人からの請求があれば不起訴理由についても告知しなければならないと規定されています。
ところが、「告訴状を提出しても受理してもらえない」ということがあります。この状態は正式に受理していないが告訴状は預かるという、いわゆる「預かり」です。預かっているだけなのでこの時点では捜査は始まりませんし、被害届と何ら変わりがないことになってしまいます。
弁護士や行政書士が作成した告訴状なら受理の可能性を高めることができます。弁護士や行政書士が作成した告訴状でも受理されないことはありますし、受理してもらえたとしても不起訴処分で決着することもあります。この点は十分にご理解の上、ご依頼願います。
刑事訴訟法
第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
② 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。引用元: e-Gov 法令検索
告訴の取消し
告訴は、捜査機関(警察署)に犯罪事実を申告し、犯人に対し刑事処罰を求めるものですので、告訴状が受理されたら捜査が始まり、起訴・不起訴の処分が決定します。
この一連の流れの中で、加害者側から示談を働きかけてくる場合があります。示談は、被害者がいる犯罪に対して可能です。起訴されてしまい前科が付くと許認可が関係する業種の場合に許可取り消しになることが多く、示談金を支払ってでも不起訴にしてほしいと考える者もいます。
告訴は、検察官が裁判所に起訴状を提出し、刑事訴訟を提起するまでなら取り消すことができます。しかし、非親告罪は告訴が捜査の端緒(きっかけ)にすぎず、公訴提起後でも散り消すことができます。
一方、親告罪の場合は、そもそも告訴がなければ起訴できないので、起訴後は取り消せないというわけです。告発の取消しについては、刑事訴訟法には明確な規定がありませんが、告発も取消しができるとされています。
刑事訴訟法
第二百三十七条 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
② 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
③ 前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。引用元: e-Gov 法令検索
刑罰の種類
前科とは、有罪判決を受けた経歴をいいます。拘禁刑、罰金刑で前科が付き、実刑か執行猶予付き判決かにかかわらず前科が付きます。
前科と似たようなものに前歴というものがあります。前歴は、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ、捜査対象となった経歴のことをいいます。不起訴の場合は、前歴は残りますが前科は付かないことになります。
親告罪とは
親告罪とは、捜査を行うためには必ず被害者からの告訴が必要とされている罪のため、通常は告訴状を作成して告訴します。親告罪は、『親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときには、これをすることができない』と定められているため、6か月を過ぎると告訴期間が徒過し、告訴できなくなります。
刑法上の親告罪は以下のとおりです。
- 刑法135条による親告罪
信書開封罪(刑133)、秘密漏示罪(刑134) - 刑法209条2項による親告罪
過失傷害罪(刑209①) - 刑法229条による親告罪
未成年者略取・誘拐罪(刑224)、拐取幇助目的被拐取者収受罪(刑227①)、これらの未遂罪(刑228) - 刑法232条による親告罪
名誉毀損罪(刑230)、侮辱罪(刑231) - 刑法244条2項による親告罪
親族(配偶者、直系血族または同居の親族以外の親族)間の窃盗罪(刑235)、不動産侵奪罪(刑235の2)、これらの未遂罪(刑243) - 刑法251条による親告罪
上記親族間の詐欺罪(刑246)、電子計算機使用詐欺罪(刑246の2)、背任罪(刑247)、準詐欺罪(刑248)、恐喝罪(刑249)、これらの未遂罪(刑250) - 刑法255条による親告罪
上記親族間の横領罪(刑252)、業務上横領罪(刑253)、遺失物等横領罪(刑254) - 刑法264条による親告罪
私用文書等毀棄罪(刑259)、器物損壊・動物傷害罪(刑261)、信書隠匿罪(刑263)
刑法
(親告罪)
第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。引用元: e-Gov 法令検索
告訴状作成が可能な罪名
当事務所で告訴状作成が可能な罪名一覧です。刑法の認知件数が多い順に対応しておりますので、ほとんどはカバーできると思います。また、これら以外にも記載の罪名に類似しているものは対応できることもありますので、ご相談下さい。
なお、ここに列挙した罪名なら無条件で作成を承るということではなく、告訴状を作成できるだけの申述かどうか、委任業務の内容にご了承いただける場合にのみ承ります。
生命・身体に対する罪
- 傷害罪(刑204)
- 過失傷害罪(刑209)【親告罪】
- 重過失傷害罪(刑211)
- 暴行罪(刑208)
自由に対する罪
- 脅迫罪(刑222)
- 住居侵入罪(刑130)
- 建造物等侵入罪(刑130)
- 不退去罪(刑130)
秘密・名誉・信用・業務に対する罪
- 侮辱罪(刑231)【親告罪】
- 信書開封罪(刑133)【親告罪】
- 信用毀損罪(刑233)
- 業務妨害罪(刑233)
- 威力業務妨害罪(刑234)
- 名誉毀損罪(刑230)【親告罪】
財産に関する罪
- 窃盗罪(刑235)【相対的親告罪】
- 強盗罪(刑236)【相対的親告罪】
- 強盗利得罪(刑236②)
- 事後強盗罪(刑238)【相対的親告罪】
- 昏睡強盗罪(刑239)【相対的親告罪】
- 詐欺罪(刑246)【相対的親告罪】
- 恐喝罪(刑249)【相対的親告罪】
- 横領罪(刑252)【相対的親告罪】
- 業務上横領罪(刑253)【相対的親告罪】
- 遺失物横領罪(刑254)【相対的親告罪】
- 背任罪(刑247)【相対的親告罪】
- 盗品等無償譲受け罪(刑256①)
- 盗品等保管罪(刑256②)
- 盗品等有償譲受け罪(刑256②)
- 公用文書毀損罪(刑258)
- 私用文書毀損罪(刑259)【親告罪】
- 建造物等損壊罪(刑260)
- 器物損壊罪(刑261)【親告罪】
- 信書隠匿罪(刑263)【親告罪】
取引の安全に対する罪
- 公文書偽造・変造罪(刑155)
- 私文書偽造・変造罪(刑159)
当事務所では、受理の可能性を上げるべく、警察署へ提出する告訴状作成を承ります。なお、本業務は弁護士法に関連して一定の制限がありますので受任前に確認いたします。
虚偽の申述は虚偽告訴罪(刑法172)となり3月以上10年以下の拘禁刑に処せられ恐れがあります。