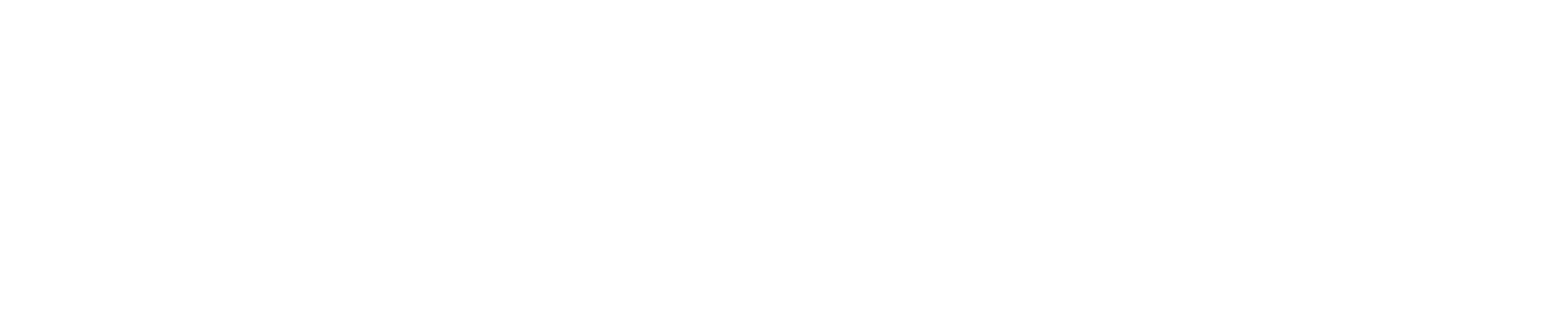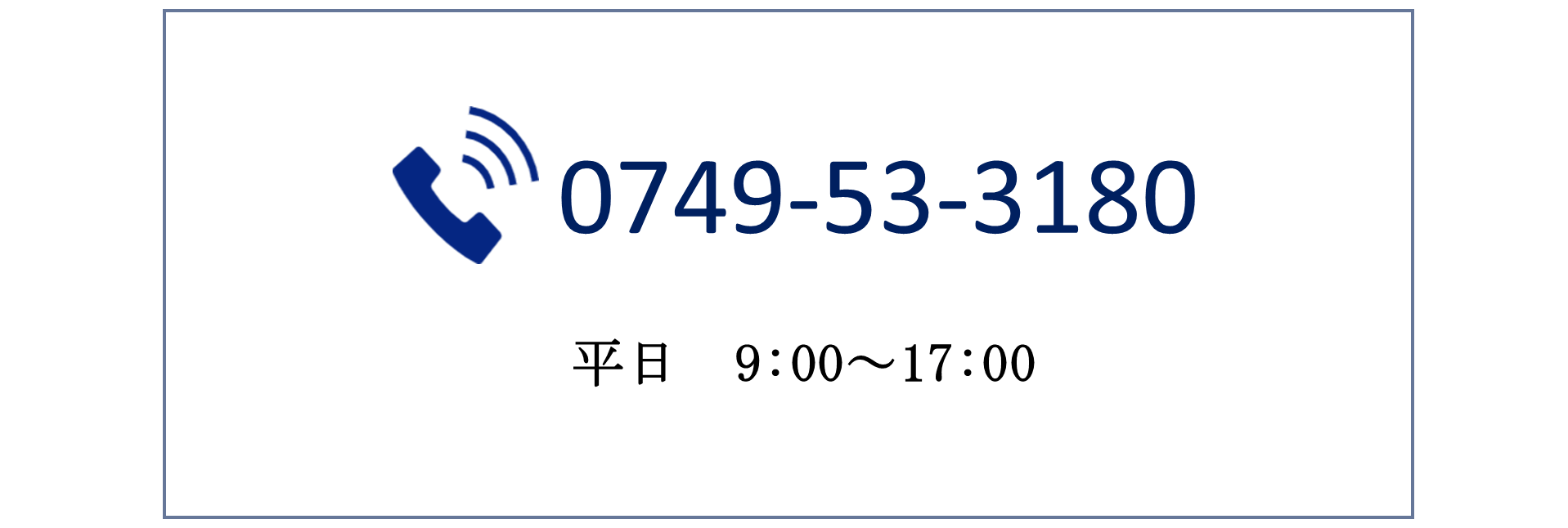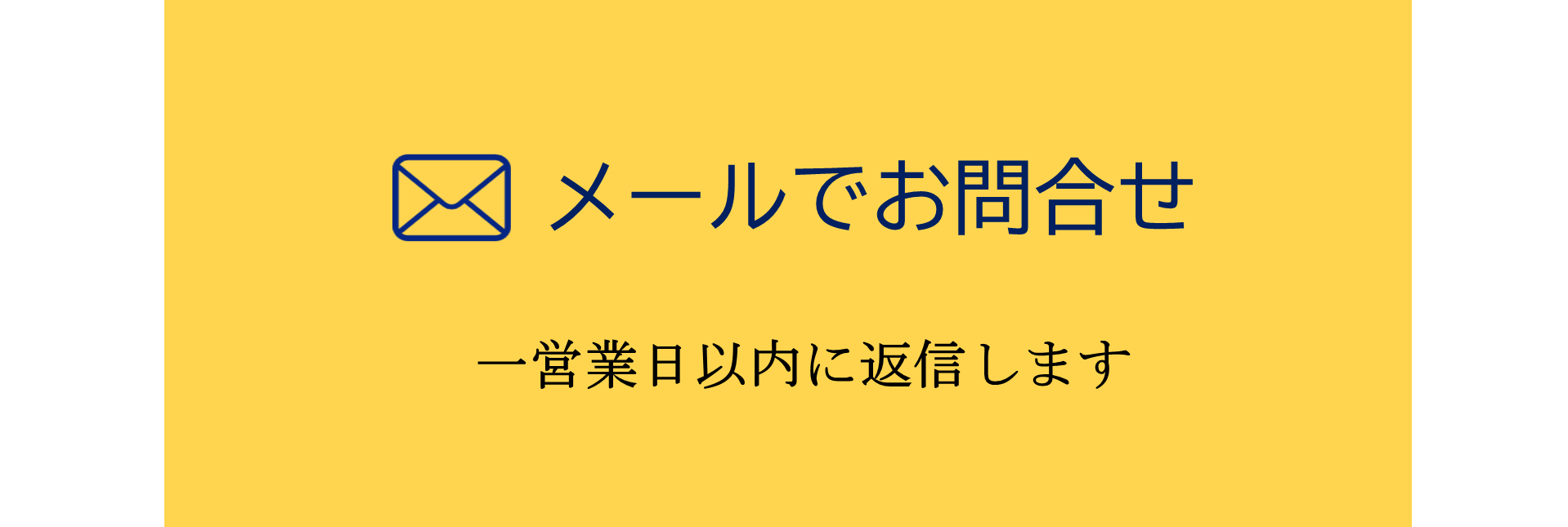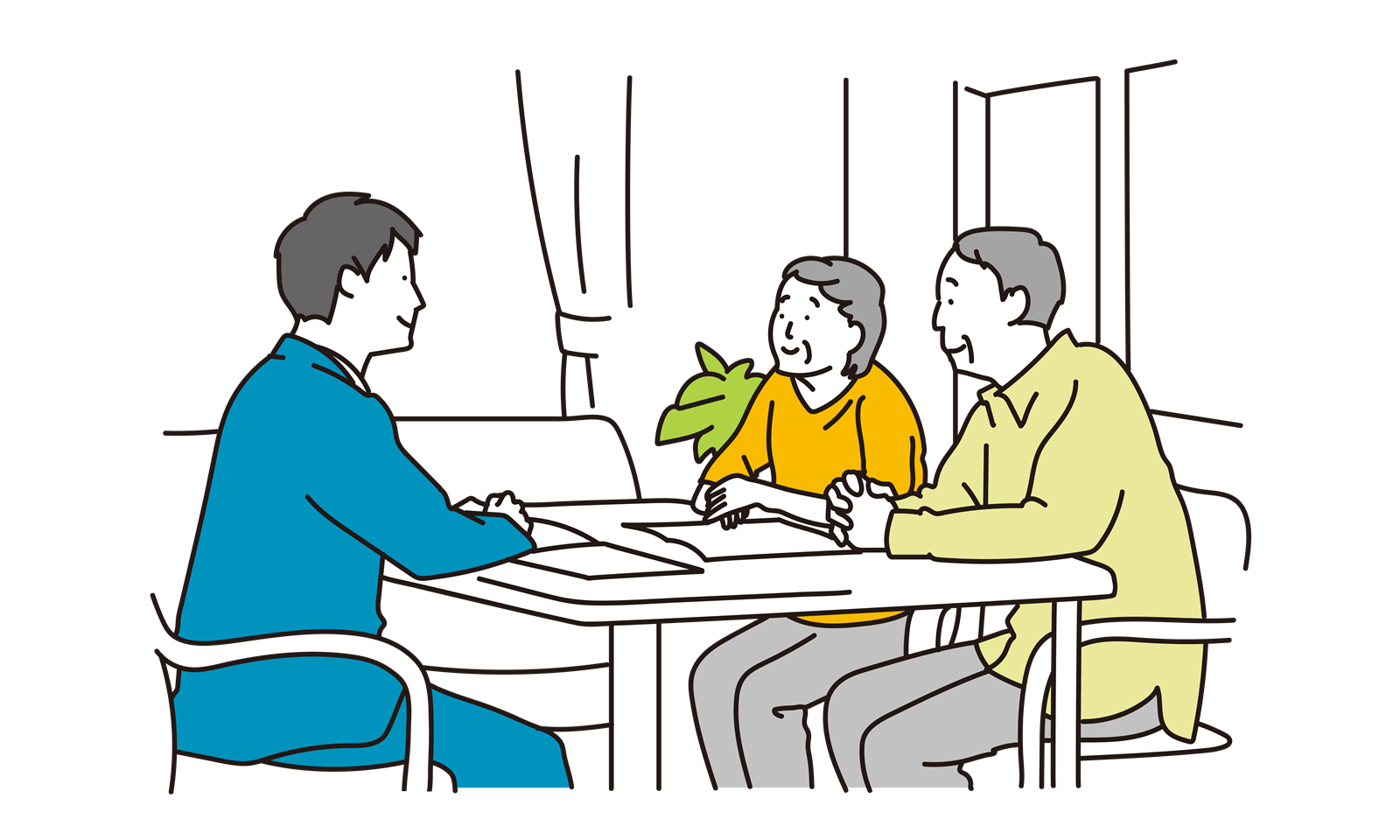協議離婚の業務
夫婦の合意があれば離婚できる協議離婚とはいえ、離婚に伴う様々な取り決めをしようとしても法律・判例・実務・学説の知識がなければ難航します。まずは協議離婚専門の当事務所で時間無制限の初回無料相談をご利用ください
離婚の約9割は裁判所が関与しない協議離婚です。協議離婚は離婚届を出す前に離婚協議書を作成しておきます。当事務所独自の「かわせ式」なら、離婚相談から始めて円滑に離婚協議書を作成することができます
-
STEP
- 初回無料相談
無料相談は時間無制限です
-
STEP
- ご依頼(委任)
行政書士業務委任契約の締結、ヒアリングを行います。「かわせ式」は円滑な離婚協議が可能です
-
STEP
- 業務着手
夫婦間で合意した内容で離婚協議書を作成、1日いただきます
-
STEP
- 委任業務完了
作成した離婚協議書を納品して完了です。確認後に双方が署名押印をして1部ずつ所持します
協議離婚については、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください
無料相談は時間無制限
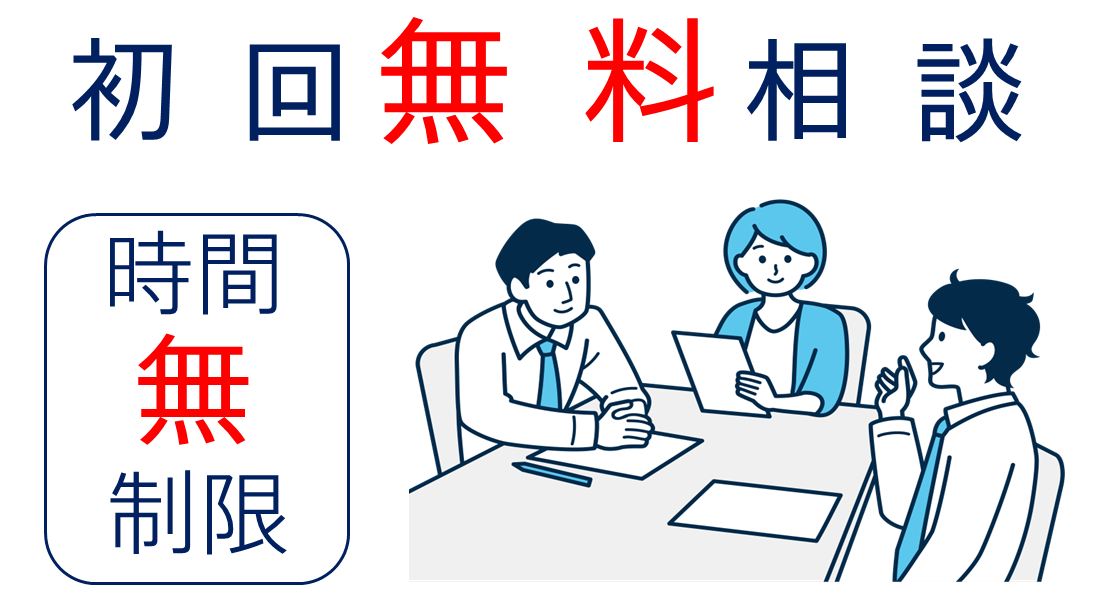
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、行政書士かわせ事務所では「この行政書士は話を聞いてくれて、専門知識が豊富で信頼できる人物なのか」を十分な相談時間で見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
もちろん、他の事務所の無料相談を利用した上で比較検討していただいても一向に構いません。無料相談を利用したからといって必ず業務を委任しなければならないわけではありませんのでお気軽にお申し込みください。
協議離婚・離婚協議書の
専門家

最高のサービスをいつも通りに、これは当事務所の経営理念です。
特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人様やご相談者様に対して常に公平かつ全力で提供するので、「いつも通りに」なのです。
明るく気さくな対応でご好評いただいております。
| 代表 | 特定行政書士 川瀬規央 |
|---|---|
| 出身 | 滋賀県彦根市生まれの長浜市育ち |
| 最終学歴 | 神戸学院大学経済学部卒 |
| 登録番号 | 第16251964号 |
| 所属 | 滋賀県行政書士会 |
| 所在地 | 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
| 電話番号 | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
|---|---|
| 定休日 | 土日祝(お役所と同じ) |
| 受任エリア | 長浜市と彦根市を中心に滋賀県内 |
| 付随資格1 | 特定行政書士(不服申立て代理) |
| 付随資格2 | 申請取次行政書士(ビザ申請) |
| 付随資格3 | CCUS登録行政書士(建設業許可) |
| 付随資格4 | 著作権相談員(著作権登録) |
①相手方との交渉②調停・訴訟中や弁護士介入の案件③裁判所手続の代理と書類作成④法的紛争事件の相談・受任は法律により承ることができません
協議離婚・離婚協議書の
ご相談・お問合せ
協議離婚の
業務事例・よくある質問
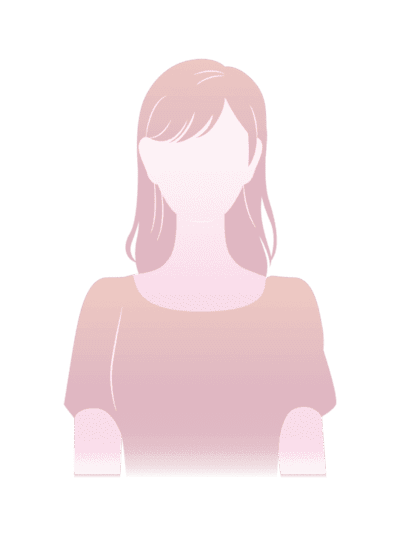
【依頼】夫の浮気が原因で離婚するので、法的にきちんとした書類を作りたい。財産分与と慰謝料も欲しいし、不貞行為の相手にも慰謝料を払ってほしい
【結果】ご主人が不貞行為を認め離婚にも合意しており、「かわせ式」により、また、相手方への慰謝料請求も考慮した内容で離婚協議書を作成した
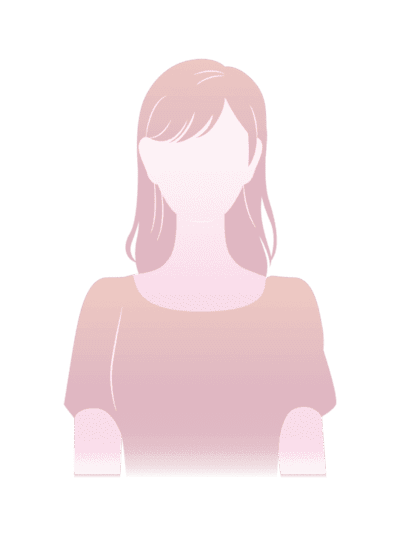
【依頼】子が2人いるので養育費もしっかり離婚協議書に書いてほしい。養育費の知識がないので説明してもらって詳細を決めたい
【結果】「かわせ式」により夫婦間の離婚協議が円滑に整った。ご主人の給与体系が特殊なためボーナス加算ありで養育費の条項を記述して離婚協議書を作成した

【依頼】住宅ローン中の自宅の財産分与で引っ掛かり離婚が進まない。弁護士に相談したが離婚裁判をすすめられた。裁判は嫌なので協議離婚にしたい
【結果】オーバーローン住宅の財産分与は難解だが、法律や判例に加えて実務的なアイデアにより夫婦双方が納得できる条項を組んで離婚協議書を作成した
プライバシー配慮のため部分一致で記述しています
離婚の方法によって、最適な相談先が異なります。
離婚の方法が協議離婚なら(離婚の約90%は協議離婚)、離婚協議書を作成することが業務なので行政書士です。しかし、法律・判例などの知識が十分な行政書士は本当に少ないです。サイトで極端に安価な報酬額を記載している事務所や、「修正・訂正は何度でも無料」の事務所、調停や裁判のことはわからない事務所は期待に応えられない可能性が高いと思われます。
協議離婚以外(調停離婚や裁判離婚)の方法なら弁護士一択です。法の定めにより、これらの代理人になれるのは弁護士だけだからです。また、法的に紛争状態にある案件は弁護士しか受任できないので、相手方が弁護士を立てている場合も弁護士に相談することになります。
弁護士に相談に行ったあとで当事務所の離婚相談をご利用いただき、相談内容や対応の違いにご納得されて離婚協議書の作成をご依頼いただくことも少なくありません。
まずは、当事務所の離婚相談(初回無料・時間無制限)をご利用いただき、離婚調停をご希望の場合など、弁護士が最適だと判断した場合でも当事務所の相談料は不要です。
時間無制限で初回無料の離婚相談をご利用いただければ、取り決め事項の選択肢とそれぞれの内容をご説明いたします。
どんな事をどんなふうに取り決めればいいかが明確になると思います。この先どうなるのか不安でいっぱいだった状態から、不安が軽減され離婚へ大きな一歩を踏み出せます。
なお、離婚協議書の作成をご依頼いただいた場合、当事務所独自の「かわせ式離婚協議」の方法で離婚協議書の作成をします。法的知識が無い方でも(全員無くて当たり前)、円滑に離婚協議をすることが可能となる画期的な方法だと自負しています。
公正証書がベストを記載しているサイトがほとんどですが、当事務所では令和8年の法改正も考慮し、必ずしも公正証書がベストだとは考えていません。公正証書にするメリットとデメリットをご説明し、通常の離婚協議書か公正証書かのいずれかを選択していただけます。
公正証書で作成する場合でもいきなり公証役場へ行っては作成してもらえません。公証役場は解説や指導をするところではないからです。まずは離婚協議書を作成しておくことが重要です。なお、彦根市には公証役場はありませんので、彦根市にお住まいの方は長浜公証役場が便利です。
離婚に関する法律は「民法」が関係しますが、六法全書にすべて記載されているわけではなく、ケースバイケースとなります。当事務所ではヒアリングを丁寧に行い、ネット上のひな形では作成不可能な離婚協議書を作成することができます。
何をどのように取り決めするのか、法的知識がない方同士が協議するのは困難です。将来の紛争リスクを考慮して、先回りしておくことがキモなので、法的知識がない方同士では自分の希望がぶつかり、離婚協議が円滑に進みません。
当事務所の離婚相談は初回無料で時間無制限です。離婚相談をご利用いただくだけでも不安が軽減され、この先どうなるのか、どうすればいいのかが明確になります。
また、離婚協議書の作成をご依頼いただいた場合、当事務所独自の「かわせ式」の離婚協議により円滑に離婚協議書を作成することができます。
養育費に相場というものはありませんので、一人3万円も全く根拠がないです。養育費を裁判所手続きで決定する場合、義務者(支払う人)と権利者(支払ってもらう人)の収入、子の年齢と人数によって算定されます。
養育費の金額は、離婚届を提出する前に作成する離婚協議書に記載します。もちろん、金額だけではなく支払期間やや支払方法なども詳細に記載しなければなりません。つまり、離婚する前の段階で養育費の金額については夫婦で合意できていることが原則的です。
養育費を取り決めずに離婚をしてしまった場合、令和8年4月1日施行改正民法によって導入の「法定養育費」を請求できます。法定養育費は一人あたり2万円です。法定養育費は離婚の日から請求できるもので、支払わなければ強制執行(差押え)されます。
養育費の申立てもしておくと、調停や審判で決まった養育費の金額を受け取ることになり、法定養育費は正式に決定するまでの「つなぎ」の役割ということがいえます。
協議離婚の基礎知識
ここからは協議離婚に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも離婚に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
協議離婚の手順
協議離婚は、4種類ある離婚の方法のうち唯一、裁判所が関与しない方法です。夫婦間での合意があれば、離婚届を提出すると正式に離婚が成立します。ここでは、協議離婚の手順についてご紹介しておきます。
| (1) 夫婦で離婚協議 | 離婚に伴う様々な取り決め事項について協議をして定めます。現実としては、何をどのように定めるのかがわからないため、専門家に相談をしておきましょう |
|---|---|
| (2) 離婚協議書を作成 | 離婚後に金銭トラブルなどの紛争を未然に防ぐためにも離婚協議書を作成することが重要です。離婚協議書には、財産分与や親権、養育費などを記載します |
| (3) 離婚届を提出する | 離婚届を提出して受理されたら離婚が成立します |
協議離婚の離婚届の出し方は以下のとおりです。
| 離婚届の提出先 | 夫婦の本籍地または住所地の役所 |
|---|---|
| 離婚届を提出する人 | 夫婦が離婚に合意して離婚届に署名すれば夫か妻の一方でもよい |
| 離婚届の証人 | 18歳以上の証人2名が必要 |
協議離婚の無料相談の内容
当事務所の離婚相談は、以下のような内容です。ご利用しやすい環境を整えておりますので、まずはお問合せください。
| ご質問・疑問に対する回答 | 離婚のお悩み事の質問・疑問にお答えします |
|---|---|
| 離婚の種類・方法について | 協議離婚、調停離婚、裁判離婚をフロー形式でご説明 |
| 離婚協議書の種類について | 離婚協議書と離婚公正証書についての違いをご説明 |
| 取り決め事項について | 離婚協議書に記載する取り決め事項のご説明 |
当事務所の離婚相談では「協議離婚に関する法律的なことがわからない、この先どうなるのか不安だ…」といったストレスを軽減することができます。不安により正しい判断ができなくなる恐れもあります。離婚問題から逃れたい気持ちが働き、必要不可欠な取り決めをせずに、正当な権利を行使せず離婚に至ることも考えられます。
当事務所は協議離婚専門です。専門家の離婚相談なのに「無料とは思えないクオリティ」をお約束します。専門家への離婚相談は離婚問題の早期解決を実現する第一歩です。
離婚相談から
離婚協議書の作成へ
当事務所なら、法的知識がない場合でも離婚相談から始めて離婚協議書を作成することができます。特に、当事務所独自の「かわせ式」による離婚協議書の作成は画期的といえます。具体的なスキームは離婚相談でご説明いたします。
なお、離婚協議書の作成を取扱業務としてHPに記載している行政書士でも「あとは書類作成だけ」の状態しか受任しない場合もありますのでご注意ください。
離婚協議書を自分で作成する場合、「間違った内容に効力が発生してしまう」恐れがあります。少しの語句の違いで法的に異なる結果になるからです。特に危険なのは、ネット上のひな形をダウンロードして使うこと、周りの方(特に離婚経験者)の意見を鵜呑みにしてしまうことです。専門家への離婚相談で正しい知識を得ることが必須です。
「離婚協議書は公正証書がおすすめ」と記載しているサイトが多いですが、デメリットもありますのでご説明いたします。公正証書は公証役場で作成します。彦根市に公証役場がありませんので、彦根市にお住まいの方は長浜市にある公証役場が便利です
離婚協議書の条項
当事務所では、15条項以上の中から必要な条項を選択して記載していきます。下記はその代表的な条項です。詳しくは離婚相談の際に説明いたします。
| 離婚合意の条項 | 夫婦が離婚に合意して協議離婚で離婚することを記載します |
|---|---|
| 親権者の条項 | 未成年の子がいる場合は親権者を定めます |
| 財産分与の条項 | 財産分与の方法を具体的に記載します |
| 養育費の条項 | 未成熟子がいる場合、養育費の取り決めを記載します |
| 親子交流(面会交流)の条項 | 非親権親が離婚後に子と面会する旨を記載します |
| 慰謝料の条項 | 慰謝料が発生する場合のみ記載します |
| 年金分割の条項 | 合意できた合意分割の按分割合を記載します |
| 通知義務の条項 | 通知義務の取り決めを記載します |
| 裁判所管轄の条項 | 2パターンのいずれかで裁判所管轄の記載をします |
| 清算条項 | 離婚後の紛争を未然に防ぐ重要な条項です |
財産分与 | 協議離婚
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を原則2分の1ずつ分け合うことです。財産分与は特有財産を含めず共有財産のみが財産分与の対象財産となります。協議離婚なら、調停離婚や裁判離婚よりも柔軟に取り決めすることができるメリットがあります。
| 財産分与の対象外財産 | 趣味・ギャンブルによる債務、他人への貸金、オーバーローン住宅のみが財産、オーバーローン住宅の売却益(例外あり) など |
|---|---|
| 特有財産 | 婚姻前からの所有財産、親族からの相続分・贈与分、子が貯めた預金、交通事故等の損害賠償金、法人財産、個人が使用する日用品 など |
| 共有財産 | 交通事故等の休業補償金、児童手当、学資保険の解約返戻金、子名義の名義預金、貯蓄性がある保険、個人年金・確定拠出年金、退職金、自動車(初年度登録から10年以内が目安)、所有者の区別が困難な物 など |
財産分与に自宅不動産が含まれる場合についてはローンの有無や、オーバーローン(売却してもローンが残る)かどうかにより分与方法が異なります。離婚協議書の作成において最も困難な条項は、オーバーローン住宅を含む財産分与です。
財産分与について、令和6年5月の法改正(令和8年4月1日施行)により財産分与の請求期限変更(5年になる)などが定められました。しかし、期限が延びたとはいえ、離婚の際に取り決めをしておくことが重要であることに変わりはありません。
民法 ※令和8年4月1日施行
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。引用元: e-Gov 法令検索
慰謝料 | 協議離婚
離婚の慰謝料とは、不法行為に基づく損害賠償であり、離婚原因をつくった方(有責配偶者)が支払うものです。よって、離婚原因によって慰謝料が発生するか否かが決まります。
慰謝料に相場というものはありません。判例では300万円以下が多いですが、協議離婚なら合意した金額でOKです。裁判所では認められない金額の慰謝料でも、協議離婚なら取り決めすることができる場合があります。
不貞行為は、共同不法行為になりますが、民法上の連帯債務にはならず、不真正連帯債務という関係になります。不貞行為の慰謝料請求は専門家への相談が必須だと言えます。
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は消滅時効にかかる前にしなければなりません。消滅時効は、「不貞行為があったことおよびその相手方を知ったときから3年」もしくは「不貞行為があったときから20年」の短い方です
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。引用元: e-Gov 法令検索
養育費 | 協議離婚
養育費とは、非親権者が親権者に対して、子を教育・監護するための費用を支払うことです。子がいるケースでは必ず離婚協議書に記載します。養育費は未成年が対象ではなく、未成熟子が対象です。
未成熟とは、社会的・経済的に自立していない子です。実際に養育費の条項を離婚協議書に記載する際は、以下のような項目を取り決めて記載することになります。
- 支払始期と支払終期
- 支払方法、振込先口座
- 支払期日
- 養育費の月額、オプション
- 物価変動等への対応
よく養育費の相場は3万円だと言う人がいますが、相場はありません。養育費は、ご夫婦の収入と子の年齢・人数によって算定するものです。養育費の算定を簡易的にできるのが養育費算定表であり、最も公平な決め方だと言えます。裁判所サイトの「統計・資料」から「公表資料」へ移ると算定表をダウンロードすることができます。
協議離婚の場合、夫婦双方で合意できた養育費の金額を離婚協議書に記載します。調停離婚や裁判離婚のように裁判所が関与する離婚の場合より協議離婚の方が柔軟に取り決めできる可能性があります。
養育費については、令和6年5月の法改正(令和8年4月1日施行)により法定養育費や先取特権などが定められました。これにより債務名義がなくても養育費未払いに対する差押えが可能になり、未払養育費の回収がしやすくなります。
民法 ※令和8年4月1日施行
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。引用元: e-Gov 法令検索
親権者 | 協議離婚
親権者とは、未成年者の子を監護・養育し、財産を管理し、代理人として法律行為をする権利や義務を行使できる者です。子が複数名の場合、それぞれに対して親権者を定めます。協議離婚の場合は裁判所は関与しないので夫婦双方で合意できた方を親権者として離婚協議書に記載します。
また、親権者の決定要因に離婚原因は無関係です。例えば、不貞行為をした側が親権者になる場合でも、不法行為の事実は考慮されません。裁判所手続きで子の意見を参考にするのは10歳ぐらいからで、15歳以上の子には陳述を聴取します。
令和6年5月の法改正(令和8年4月1日施行)により共同親権について定められました。これにより単独親権しか認められなかった親権について、共同親権とすることも認められます。
民法 ※令和8年4月1日施行
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。7 裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
8 第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。引用元: e-Gov 法令検索
親子交流 | 協議離婚
親子交流(面会交流)とは、非親権者が、子と一緒に過ごすことです。親子交流(面会交流)について離婚協議書に記載する際は、具体的ではない記載を推奨しています。詳しくは離婚相談でご説明いたします。
目安として親子交流(面会交流)の頻度を離婚協議書に記載する場合、「月に1回程度」、1回当たりの時間は、「子が4歳ぐらいまでは2~3時間、子が5歳以上であれば5~7時間ぐらい」が一般的とされています。
親子交流(面会交流)について、令和6年5月の法改正(令和8年4月1日施行)により祖父母等との親子交流や親子交流の試行的実施などが定められました。
「面会交流」は「親子交流」に名称変更されています
民法 ※令和8年4月1日施行
(親子の交流等)
第八百十七条の十三 第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。
4 前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
5 前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。引用元: e-Gov 法令検索
年金分割 | 協議離婚
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類あります。離婚協議書には、合意分割の按分割合や年金基礎番号を記載することが多いです。事前に年金事務所で相談することを推奨します。
|
合意分割 |
3号分割 |
|
|---|---|---|
| 対象の年金 | 厚生年金 | 厚生年金 |
| 対象者 |
第1号改定者(分割する側)と第2号改定者(受ける側)が対象者 |
特定被保険者(厚生年金保険の被保険者)、被扶養配偶者(特定被保険者の配偶者で第3号被保険者)のみが対象 |
| 対象期間 | 婚姻していた期間 | 2008年4月1日以降の婚姻期間で、第3号被保険者であった期間 |
| 按分割合 | 上限は0.5、下限は0.4。按分割合は夫婦で決める | 自動的に0.5、相手方の合意は不要 |
3号分割は相手方の承諾なしで単独で請求できますが、離婚成立日の翌日から2年を経過すると請求できなくなります。また、相手方が死亡した場合は死亡日から1か月で請求できなくなります。
協議離婚以外の離婚の方法
夫婦での離婚協議で合意できない場合や、協議すらできない状況の場合は、家庭裁判所での離婚調停や離婚訴訟で離婚をする流れになります。離婚調停とは、管轄の家庭裁判所で行います。協議離婚が不可能なときは、家庭裁判所に申し立てをします。訴訟(裁判)ではありませんので費用も非常に安価です。ただし、弁護士を代理人にする場合は高額な費用を要します。
離婚調停で離婚自体や取り決め事項に合意できた場合、調停離婚として離婚が成立します。反対に、離婚調停が成立しない場合は不調となり離婚調停は終了します。
離婚調停終了後、もう一度離婚に向けた行動を取る場合、下記の選択肢が考えられます。離婚調停では合意できなかったものの、調停で離婚に関する法的な見解が明確になり、離婚訴訟は避けたいケースなどでは協議離婚の方法に戻ることもあります。
- 協議離婚で離婚をする
- 再度離婚調停を申し立てる
- 離婚訴訟を提起する
離婚調停が不調で終了した後、夫婦いずれかの提起によって離婚訴訟(離婚裁判)で決することになります。離婚訴訟は、調停前置主義により、いきなり離婚裁判の提起はできないため、まずは離婚調停から始めることになるのです。
離婚訴訟は認容、和解、判決のいずれかにより決します。離婚訴訟は弁護士に委任することになりますが、弁護士費用は高額で、長い期間を要します。