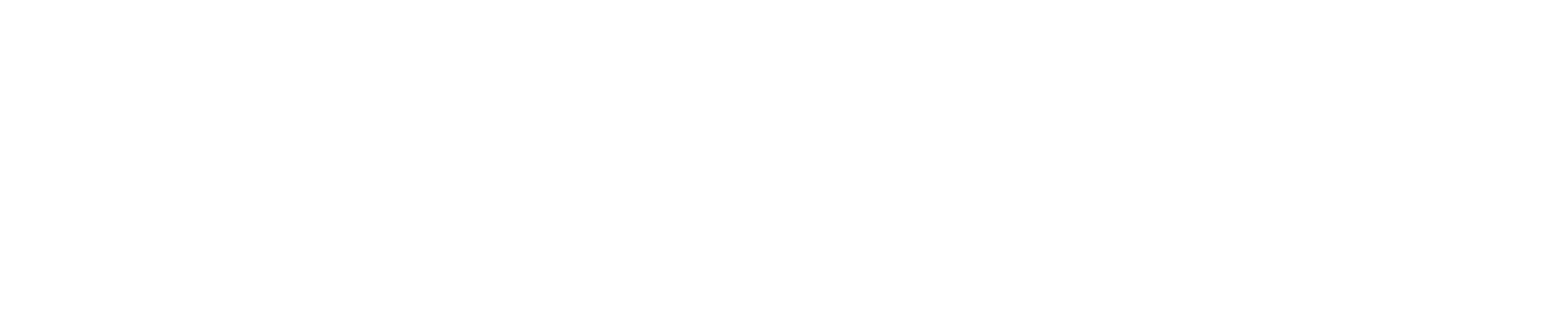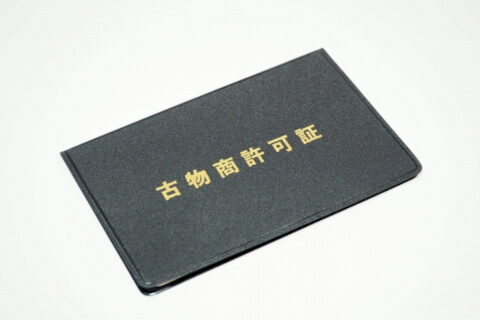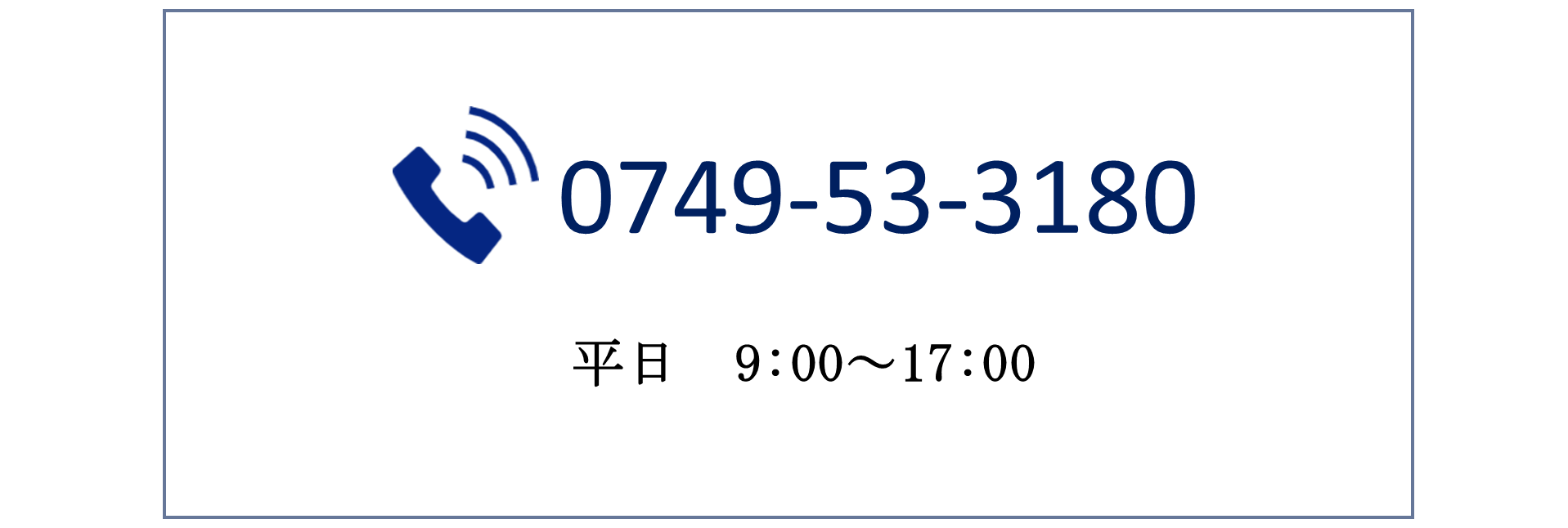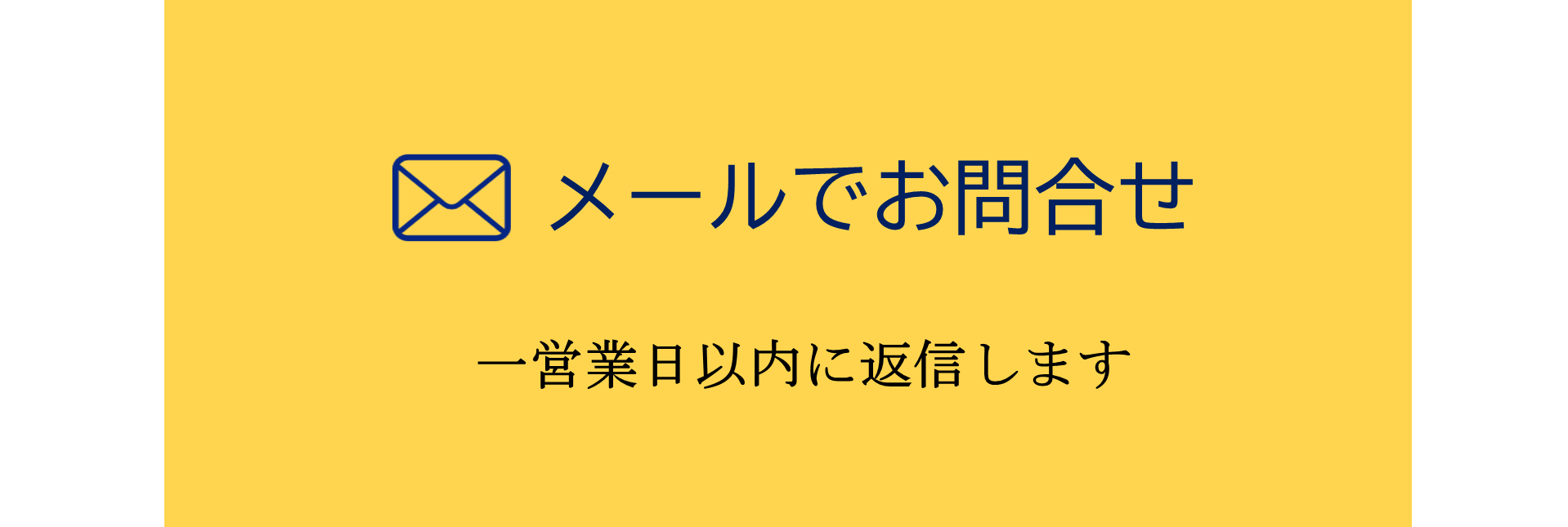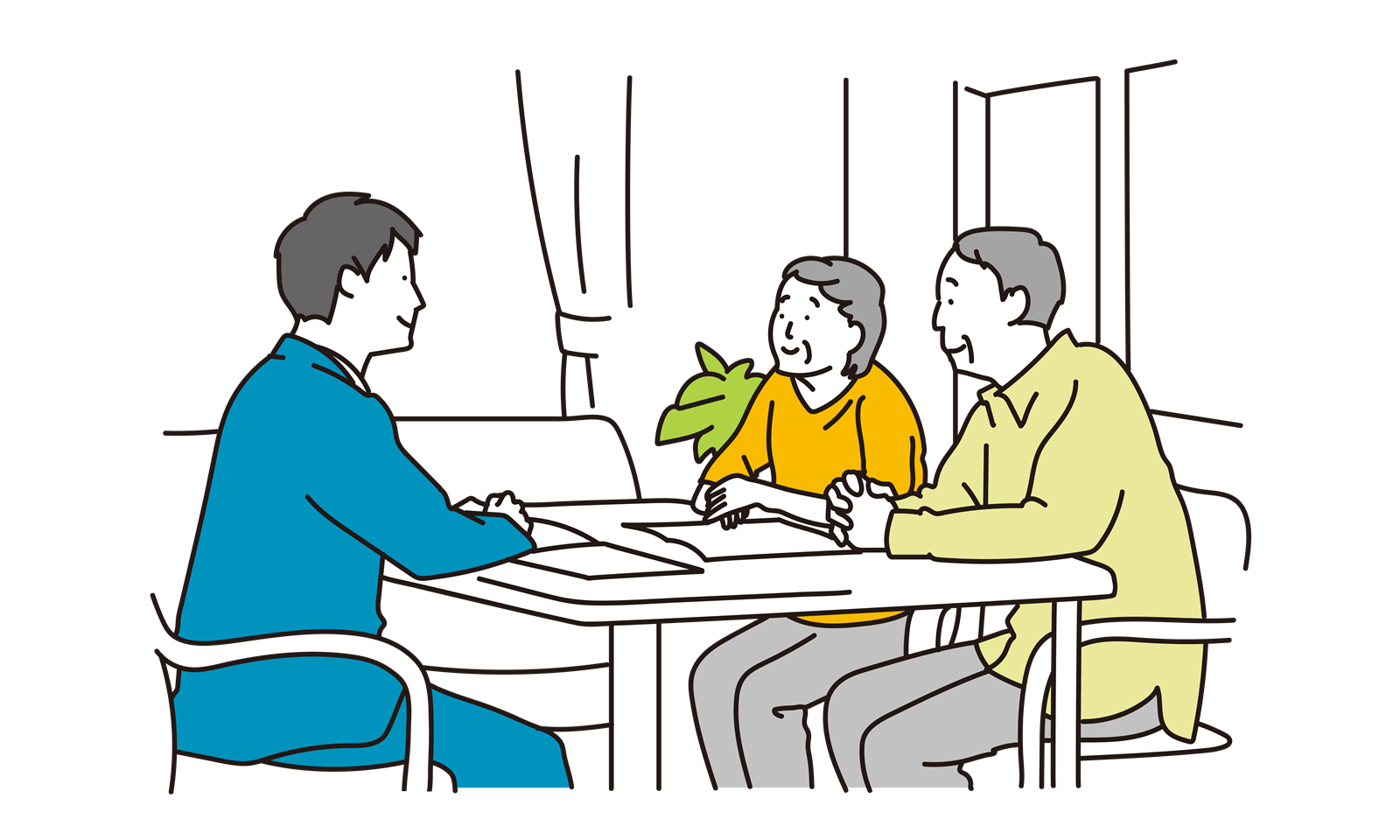営業許可の業務
営業許可に関する業務は、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください。
なお、法定手数料については最新の情報を記載するよう心がけておりますが、いつの間にか変更されていることもありますのでご容赦くださいませ。
行政書士かわせ事務所のご案内

当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
| 事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 特定行政書士 川瀬規央 |
| 所在地 |
〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318-15 |
| TEL | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 |
カレンダー通り(役所と同じ) 12/29~1/3は休業 |
| 所属 |
登録番号:第16251964号 |
|
会員番号:第1292号 |
|
|
行政書士 付随資格 |
特定行政書士(不服申立ての代理) |
| 入管申請取次行政書士(ビザ申請) | |
| CCUS登録行政書士(建設業許可) | |
| 著作権相談員(著作権登録) |
営業許可のお問合せ
行政書士のよくある質問
行政書士の業務内容は、司法機関を除く官公署などの行政機関に対してする申請や届出の代理、その書類作成、また、権利と義務の書類作成などです。そもそも、他人の依頼を受け報酬を得て行として官公署に提出する書類作成をすることが認められているのは行政書士のみです。(別の法律で定めがあるもの除く)
例えば、自動車を購入する方が登録費用等や車両代として代金を支払い、自動車販売店が車庫証明の申請を「無料ですので大丈夫」と言ってすると行政書士法違反であり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。知らず知らずのうちに法令違反に関わることがないよう注意が必要です。
行政書士法 ※令和8年1月1日施行
(業務)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
行政書士法 ※令和8年1月1日施行
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。引用元: e-Gov 法令検索
特定行政書士は行政書士のうち日本行政書士会連合会の研修課程を修了し、考査試験にパスした者がなれます。訴訟の要件事実を理解し、最新の行政法の知識が必要なため、たとえベテラン行政書士でも合格することは簡単ではありません。
特定行政書士には行政書士の資格を得てからしかなれませんので、行政書士の上位資格ともいえます。
特定行政書士は、不服申立ての代理をすることができます。許認可で不許可処分になった場合の審査請求が代表的な例です。
行政書士法 ※令和8年1月1日施行
第一条の四 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。引用元: e-Gov 法令検索
行政書士は国家資格者として守秘義務を遵守いたします。ご相談や業務受任により知り得た秘密事項を第三者に漏らすようなことはいたしませんのでご安心ください。
行政書士法
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。引用元: e-Gov 法令検索
日本には士業は8種類あり、行政書士はそのうちのひとつです。士業は法律により取り扱うことができる業務が区別されており、いわばナワバリのようなものです。
司法書士は法務局などの司法機関に提出する書類作成が取扱業務ですが、不動産登記、商業登記がメインです。
弁護士は士業の最高峰として何でも取り扱うことができますが、裁判所手続きである調停や訴訟の代理人、紛争状態にあるケースの相手方との交渉がメインです。
当事務所の相談料は1時間迄5,500円(税込)ですが、初回相談は無料で、しかも時間制限はありません。特に離婚のご相談は2時間超になることがほとんどです。
相談したからといって必ず依頼をしなければならないわけではありませんので、ご相談だけのご利用も大歓迎です。
また、相談の結果、司法書士や弁護士など他の士業の取扱業務であった場合でも相談料はいただきませんので、どこへ相談すればよいかわからない場合もご相談ください。行政書士は「街の法律家」と言われています。
なお、相談後14日以内に正式に業務委任の場合は頂戴した相談料を受任業務の報酬に充当します。
当事務所は完全予約制ですので、まずはお電話かWEBからご予約をお願いします。土日祝や17時以降も柔軟に対応いたします。
営業許可の基礎知識
ここからは営業許可に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも営業許可に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
飲食店営業許可とは
飲食店営業許可とは、食品に関する営業を行う場合に必要な営業許可で、営業予定地域所管の保健所へ申請(業種によっては届出)しなければなりません。飲食店営業許可は、厚生労働省の食品衛生申請等システムよりオンライン申請も可能です。従来通りに窓口での紙申請もできます。
新たな営業許可・届出制度
令和3年6月1日から、新たな営業許可・届出制度が始まっています。新制度は、許可業種・届出業種・許可届出不要業種の区別と施設基準の改正です。
許可業種と届出業種はHACCPに沿った衛生管理が必要です。ただし、合成樹脂製の器具・容器包装の製造事業者はGMP製造管理の制度化によりHACCPに沿った衛生管理の対象外です。
許可業種
- 飲食店営業(旧喫茶店営業を統合)
- 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
- 食肉販売業※包装品は除く、食肉処理業、食肉製品製造業
- 魚介類販売業※包装品は除く、魚介類競り売り営業
- 集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業
- 食品の放射線照射業
- 菓子製造業(旧あん類製造業を統合)
- アイスクリーム類製造業、乳製品製造業
- 清涼飲料水製造業
- 水産製品製造業
- 氷雪製造業
- 液卵製造業
- 食用油脂製造業
- みそまたはしょうゆ製造業
- 酒類製造業
- 豆腐製造業、納豆製造業
- 麺類製造業
- そうざい製造業、複合型そうざい製造業
- 冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業
- 漬物製造業
- 密封包装食品製造業、食品の小分け業
- 添加物製造業
届出業種
許可業種と届出不要業種以外の営業が届出業種となります。届出は施設基準の要件はありませんが、食品衛生責任者を設置しなければなりません。また、届出事項に変更が生じた場合や廃業した場合は保健所へ届出が必要です。
- 干し柿・干し芋・切干大根などの製造業
- いわゆる健康食品の製造業
- 精穀・製粉業
- 合成樹脂製の器具・容器包装製造業
- 弁当販売業
- 野菜果物販売業
- 米穀類販売業
- 食肉販売業で包装済の食肉のみの販売
- 魚介類販売業で包装済の魚介類のみの販売
- 集団給食(委託の場合は飲食店営業の許可)
- 調理機能を有する自動販売機で高度な機能を有して屋内設置のもの
許可届出不要業種
- 食品または添加物の輸入業
- 食品または添加物の貯蔵または運搬のみをする営業(冷凍または冷蔵倉庫業は届出が必要)
- 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品または添加物の販売業(カップ麺や包装されたスナック菓子など)
- 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
- 器具・容器包装の輸入または販売業
学校や病院等の営業以外の給食施設のうち1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家や漁業者が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調製等)は、営業届出は不要です。許可を受けるための施設基準ですが、滋賀県食品衛生基準条例によって定められ、各営業共通基準、営業別基準、生食用食肉またはふぐを扱う営業基準、特定簡易営業基準の4つに区分されています。
飲食店営業許可の手続きの流れ
- 管轄の保健所と事前相談
- 申請書類の提出
営業開始予定日の10日~14日前には管轄保健所へ申請するかオンライン申請 - 施設検査の打ち合わせ
- 施設の検査
内装を含め完成している必要があります - 許可証の交付
- 営業開始
許可証を見やすい場所に掲示します
飲食店営業許可の必要書類
- 営業許可申請書
- 営業施設の大要(施設の平面図)
調理場、製造場を詳細に記載します - 営業許可申請手数料
滋賀県収入証紙で17,600円 - 水質検査成績表(6か月以内のもの)
井戸水や貯水槽の場合に必要です - 食品衛生管理者の資格を証する書面
栄養士・調理師・製菓衛生士・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士の資格証。資格がなければ食品衛生責任者養成講習の修了が一般的です
食品衛生法
第五十五条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
② 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第五十九条から第六十一条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
③ 都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。引用元: e-Gov 法令検索
古物商許可とは
古物商許可とは、中古品の売買を業として行う場合に必要な許可です。古物商許可は、都道府県の公安委員会から許可を得なければならず、その申請は営業所がある管轄警察署に対して行います。
無許可で古物売買を行った場合、古物営業法に違反し、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。古物商許可が必要なのは「業」として古物を売買するケースです。古物の営業には様々な品目があり、リサイクルショップはもちろんのこと>中古車を扱う自動車販売店にも必須の許可です。
古物商の種類
- 古物商
古物の売買や交換をする古物営業は、古物営業法に基づき都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。自身で(法人含む)売買するので、リサイクルショップなど多くのケースはこの許可です。 - 古物市場主
古物商同士での売買や交換のための古物市場を営む場合です。 - 古物競りあっせん業
インターネットを利用して古物を売却しようとする者と、買い受けようとする者との間でオークションが行われるシステムを提供する営業です。オークション主催者に必要な許可です
古物商許可の欠格事由
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は古物営業法に規定する罪もしくは窃盗、背任、占有離脱物横領、盗品有償譲り受け等に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為で国家公安委員会規則に定めるものを行う恐れがあると認められる者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律や規定による命令又は指示を受けた者であって、3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法の規定により古物営業許可を取り消され、5年を経過しない者(許可を取り消された法人の公示日前 60 日以内に当該法人の役員であった者を含む)
- 古物営業法の規定による許可の取消しに係る公示日から当該取消しを決定する日までの間に古物営業を廃止したとの理由により許可証の返納をした者で返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 心身の故障により古物商又は古物市場主業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、相続人で一定の場合を除く
古物商許可申請の必要書類(個人)
- 申請書
- 略歴書
- 住民票の写し(本籍地記載で3か月以内のもの)
- 本籍地の市町村長が発行する身元保証書(3か月以内のもの)
- 管理者が申請者と異なる場合は管理者についての2・3・4
- ホームページ上で古物の取引をする場合、URLの使用権原を示す書類
- 誓約書(個人用)
- 誓約書(管理者用)
- 営業所の土地・建物の登記簿謄本
- 営業所の土地・建物の使用権原を示す書類(所有者が申請者と異なる場合)
法定手数料は収入証紙で19,000円です。書類確認後に貼付しましょう。
古物商許可申請の必要書類(法人)
- 申請書
- 法人登記上の役員全員(監査役含む)及び管理者についての(1)2・3・4・7の書類。管理者が申請法人の役員なら(1)7のみ
- 法人登記に係る記載事項証明書
- 法人の定款
- ホームページ上で古物の取引をする場合、URLの使用権原を示す書類
- 誓約書(個人用)
- 誓約書(管理者用)
- 営業所の土地・建物の登記簿謄本
- 営業所の土地・建物の使用権原を示す書類(所有者が申請者と異なる場合)
法定手数料は収入証紙で19,000円です。書類確認後に貼付しましょう。
古物営業法
(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
4 この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。引用元: e-Gov 法令検索
解体工事業登録とは
解体工事業登録とは、解体工事業を営もうとする場合、管轄する都道府県知事に対してする登録です。登録を受けた都道府県に限り施工が可能となります。
よって、解体工事業登録をせずに解体工事を行うことはできません。解体工事業登録の有効期間は5年なので、期間満了日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。
建設業許可を取っている方で、業種が土木工事業、建築工事業、解体工事業であれば解体工事業登録は不要です。ただし、請負金額500万円以上の解体工事を行う場合は解体工事業の建設業許可が必要です。
解体工事業登録の方法
- 申請先
解体工事業登録は、滋賀県土木交通部監理課建設業係(県庁新館5階)の窓口申請で解体工事業登録申請書に必要書類を添付して申請します。なお、郵送の方法や電子申請も可能です。 - 手数料
手数料は滋賀県収入証紙で納めます。新規の場合は31,000円、更新の場合は25,000円ですが、事前に購入して消印をせずに持参します。電子申請の場合はクレジットカードかペイジーのみです。 - 標準処理期間
内容審査はおおむね2週間です。
解体工事業登録の要件
下記の欠格要件に該当しないことが求められます。
- 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
- 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
- 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下暴力団員等。暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号規定の暴力団員)
- 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき
- 解体工事業者が法人の場合、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき
- 法第31条に規定する者(技術管理者)を選定していない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
解体工事業登録の必要書類
- 解体工事業登録申請書(第1号)
- 誓約書(第2号)
- 技術管理者の実務経験証明書(第3号)
- 合格証明書、卒業証明書、講習修了書の写し
添付書類として必要な場合 - 申請者の略歴書(第4号)
- (法人の場合)申請者の登記簿等本および役員全員の住民票抄本(本籍地記載不要)
- (個人の場合)申請者の住民票抄本(本籍地記載不要)
- 技術管理者の住民票抄本(本籍地記載不要)
技術管理者の要件
実務経験については、解体工事の施工を指揮・監督、施工に携わった経験をいい、雑務や事務は実務経験とは認められません。実務経験者は実務経験証明書が必要で以下のとおりです。
- 大学・高専で土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学等を修めて卒業
【通常】2年【講習会受講者】1年 - 高校で土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学等を修めて卒業
【通常】4年【講習会受講者】3年 - 上記以外
【通常】8年【講習会受講者】7年
平成13年12月1日以降の実務経験は、証明者が建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)または解体工事業登録を受けていない場合は認められません。但し、平成28年5月31日時点のとび土工はOKです。
なお、有資格者は実務経験証明書は不要です。
- 建設業法による技術検定
一級建設機械施工管理技士、二級建設機械施工管理技士(第一種・第二種)、一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(建築、躯体) - 技術士法による第二次試験
技術士(建設部門) - 建築士法による建築士
一級建築士、二級建築士 - 職業能力開発促進法による技能検定
一級とび・とび工、二級とび+解体工事経験1年、二級とび工+解体工事経験1年 - 国土交通大臣の登録を受けた試験
登録試験合格者
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(解体工事業者の登録)
第二十一条 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。)を受けた者が、第一項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。引用元: e-Gov 法令検索
電気工事業者登録とは
電気工事業者登録とは、電気工事業を営むために必要な登録です。登録申請を都道府県知事に対して行い許可を受けます。登録の有効期限は5年で、5年ごとに更新手続きが必要です。
登録を受けずに電気工事業を営んだ者または虚偽の申請により登録を受けた者は1年以下の拘禁刑若しくは10万円以下の罰金に処せられまたはこれを併科されます。
なお、請負代金500万円以上の電気工事を請け負う場合には、建設業許可を受ける必要があります。電気工事業者登録の種別、電気工事業者の登録が必要となる者は以下のとおりです。
- 一般用電気工作物にかかる電気工事を施工する場合
600V以下の低圧の電気を使用する一般家屋、商店、50kW未満の小工場の電気工作物 - 自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事を施工する場合
自家用電気工作物のうち、最大出力500kW未満の需要設備の電気工作物をいい、一般的に中小ビルの需要設備です
電気工事業者の登録区分
- 登録電気工事業者
一般用電気工作物・自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得していない事業者です。当サイトでは主に登録電気工事業者について記述しています - みなし登録電気工事業者
一般用電気工作物・自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得している事業者です。なお、登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合には、みなし登録電気工事業者の届出を行う必要があります - 通知電気工事業者
一般用電気工作物にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得していない事業者です - みなし通知電気工事業者
一般用電気工作物にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得している事業者です
電気工事業登録の申請ですが、主任電気工事士の設置(法第19条)要件がありますので、営業所ごとに主任電気工事士を設置しなければなりません。複数の営業所で兼任できません。なお。電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反したことがない者でなければなりません。
(1) 主任電気工事士の資格(下記のいずれか)
- 第一種電気工事士免状を取得している者
- 第二種電気工事士免状を取得している者
(2) 主任電気工事士の職務等(法第20条)
- 配線図の作成及び変更。関与しない場合はチェックする
- 電位関係法規に違反しないように管理
- 立入検査を受ける場合の立会い
- 一般用電気工事の検査結果の確認
- 帳簿の記載上の管理監督
- その他一般用電気工事に関する一般的な管理監督
電気工事業の必要書類(個人)
※申請者が主任電気工事士
- 申請書 様式第1
- 誓約書 様式第1-(1)
- 主任電気工事士の電気工事士免状の写し 様式第1-(4)
- 主任電気工事士の実務経験証明書 様式第1-(5) ※第一種電気工事士の場合は不要
- 手数料 滋賀県収入証紙22,000円
電気工事業の必要書類(個人)
※申請者が主任電気工事士を雇用
- 申請書 様式第1
- 誓約書 様式第1-(1)
- 主任電気工事士の誓約書 様式第1-(2)
- 主任電気工事士の雇用証明書 様式第1-(3)
- 主任電気工事士の電気工事士免状の写し 様式第1-(4)
- 主任電気工事士の実務経験証明書 様式第1-(5) ※第一種電気工事士の場合は不要
- 手数料 滋賀県収入証紙で22,000円
電気工事業の必要書類(法人)
※代表者が主任電気工事士の場合
- 申請書 様式第1
- 誓約書 様式第1-(1)
- 商業登記簿謄本
- 主任電気工事士の電気工事士免状の写し 様式第1-(4)
- 主任電気工事士の実務経験証明書 様式第1-(5) ※第一種電気工事士の場合は不要
- 手数料 滋賀県収入証紙で22,000円
電気工事業の必要書類(法人) ※代表者が主任電気工事士を雇用
- 申請書 様式第1
- 誓約書 様式第1-(1)
- 商業登記簿謄本
- 主任電気工事士の誓約書 様式第1-(2)
- 主任電気工事士の雇用証明書 様式第1-(3)
- 主任電気工事士の電気工事士免状の写し 様式第1-(4)
- 主任電気工事士の実務経験証明書 様式第1-(5) ※第一種電気工事士の場合は不要
- 手数料 滋賀県収入証紙で22,000円
電気工事業者登録の申請方法
- 申請先:滋賀県電気工事工業組合
- 草津市青地町299番1号:電話番号:077-562-2069
- 受付時間 9:00~17:00(土日祝、年末年始除く)
- 申請方法:持参又は郵送(書留または簡易書留)
- 処理期間:申請受理から約10日間程度で登録電気工事業者登録証が郵送される
電気工事業登録の更新
電気工事業登録の更新についても記述しておきます。登録電気工事業登録の有効期限は5年ですので、5年ごとに更新の手続きをしなければなりません。
更新の手続きは有効期限の約1か月前から可能ですので忘れず手続きをしましょう。有効期限が切れた後の申請は新規登録申請と同じ手続きになってしまいます。登録電気工事業更新の必要書類は新規登録申請と同様ですが、異なる点は以下のとおりです。
- 申請書の様式は、様式第2を使用する
- 主任電気工事士の実務経験証明書は不要
- 登録電気工事業者登録証の原本を提出
- 手数料は滋賀県収入証紙で12,000円
電気工事業の業務の適正化に関する法律
(登録)
第三条 電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。引用元: e-Gov 法令検索
金属屑行商届出とは
金属屑とは、半製品を含む金属製品その他廃品を含む金属類であって、次の1と2に該当しないものをいいます。
- 正常な生産工程により生産されたもので、その生産の目的に従って売買・交換・加工され、または使用されるもの
- 古物営業法第1条第2項に該当する古物
これら金属屑を売買等する場合、許可・届出が必要となります。金属屑商と金属屑行商の2通りに区別されていますので、両方をご紹介いたします。
金属屑商
金属屑商は、営業所を設けて金属屑を売買・交換、または委託を受けて売買・交換することを業とする者で、営業所ごとに滋賀県公安委員会の許可を受けなければなりません。自ら管理せずに営業所を設けようとするときは、その営業所の管理者を定めなければなりません。
金属屑商許可申請の必要書類
- 金属屑商許可申請書(様式第1号)
- 申請者の履歴書 ※法人の場合は代表者及びその業務を行う役員について
- 申請者の戸籍抄本または住民票写し ※法人の場合は代表者及びその業務を行う役員について
- 6か月以内に撮影した写真 上半身、たて2.5cmよこ2cm
- 管理者を定めるときはその者の履歴書及び戸籍抄本又は住民票写し
- 委任状
許可後、発生事由により許可証再交付、記載事項異動、営業所移転、管理者設置、許可証返納につき届出等が必要となります。また、欠格要件も定められており、すべてを満たす必要もあります。
金属屑行商届出
金属屑行商届出は、営業所を設けないで、個々の取引を相手方に求めて金属屑を売買・交換し、または委託を受けて売買・交換することを業とする者で、管轄の警察署に届出が必要です。届出は新規、異動、返納が発生した場合に必要で、必要書類等は以下のとおりです。
金属屑行商届出(新規)
- 金属屑行商届出書
- 6か月以内に撮影した写真2枚(上半身、たて2.5cmよこ2cm、裏面に氏名を記入)
- 住民票写し(本籍地記載)
- 委任状
金属屑行商届出(異動)
- 金属屑行商の証 記載事項異動届書
- 金属屑行商の証
- 住民票写し(本籍地記載)
- 委任状
金属屑行商届出(返納)
- 金属屑行商の証 返納届書
- 金属屑行商の証
- 委任状