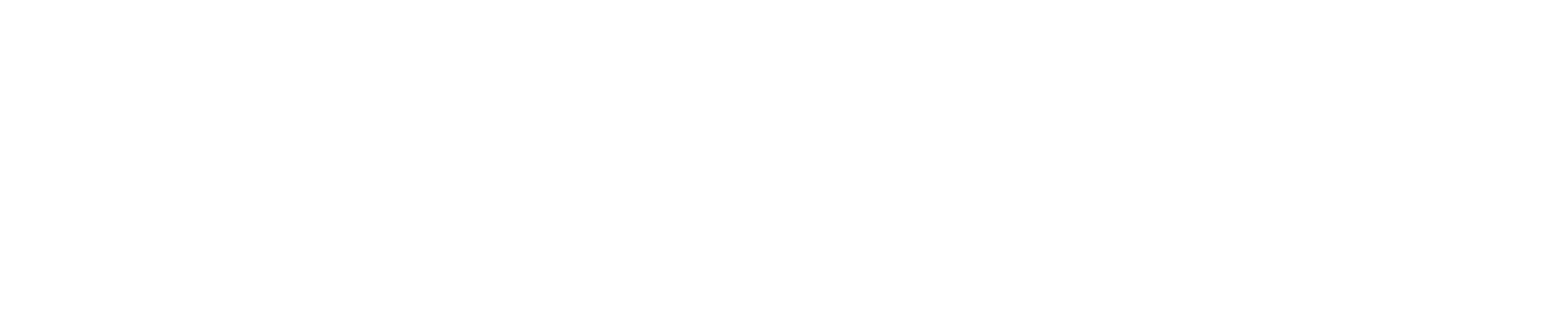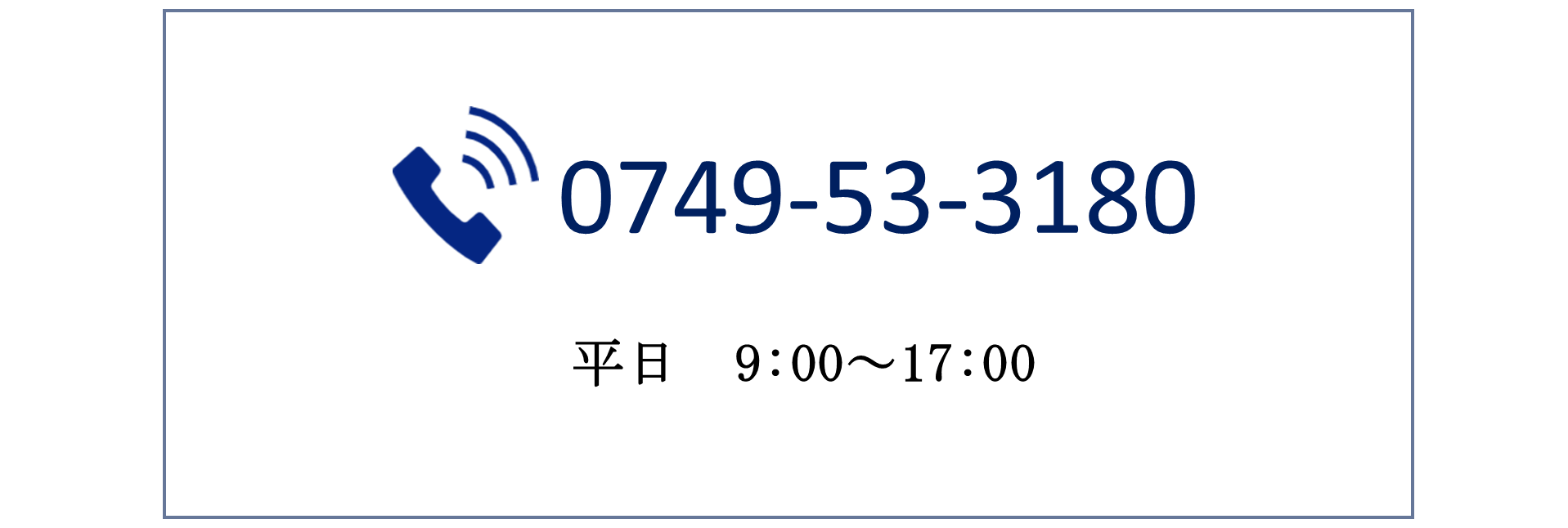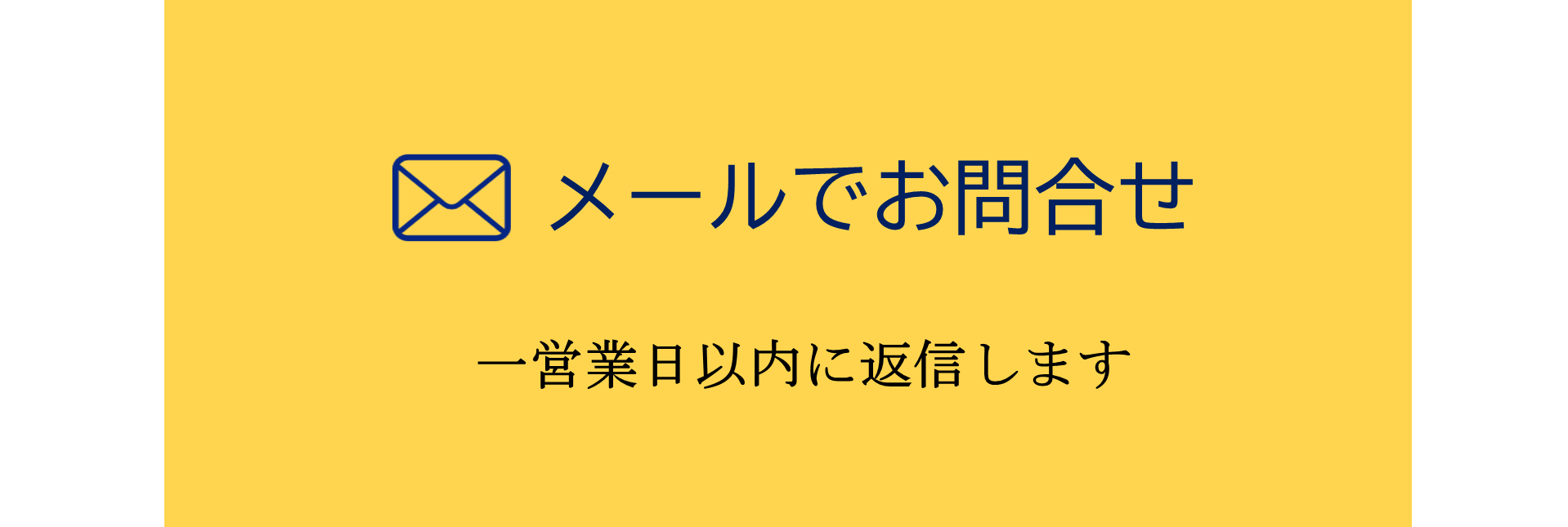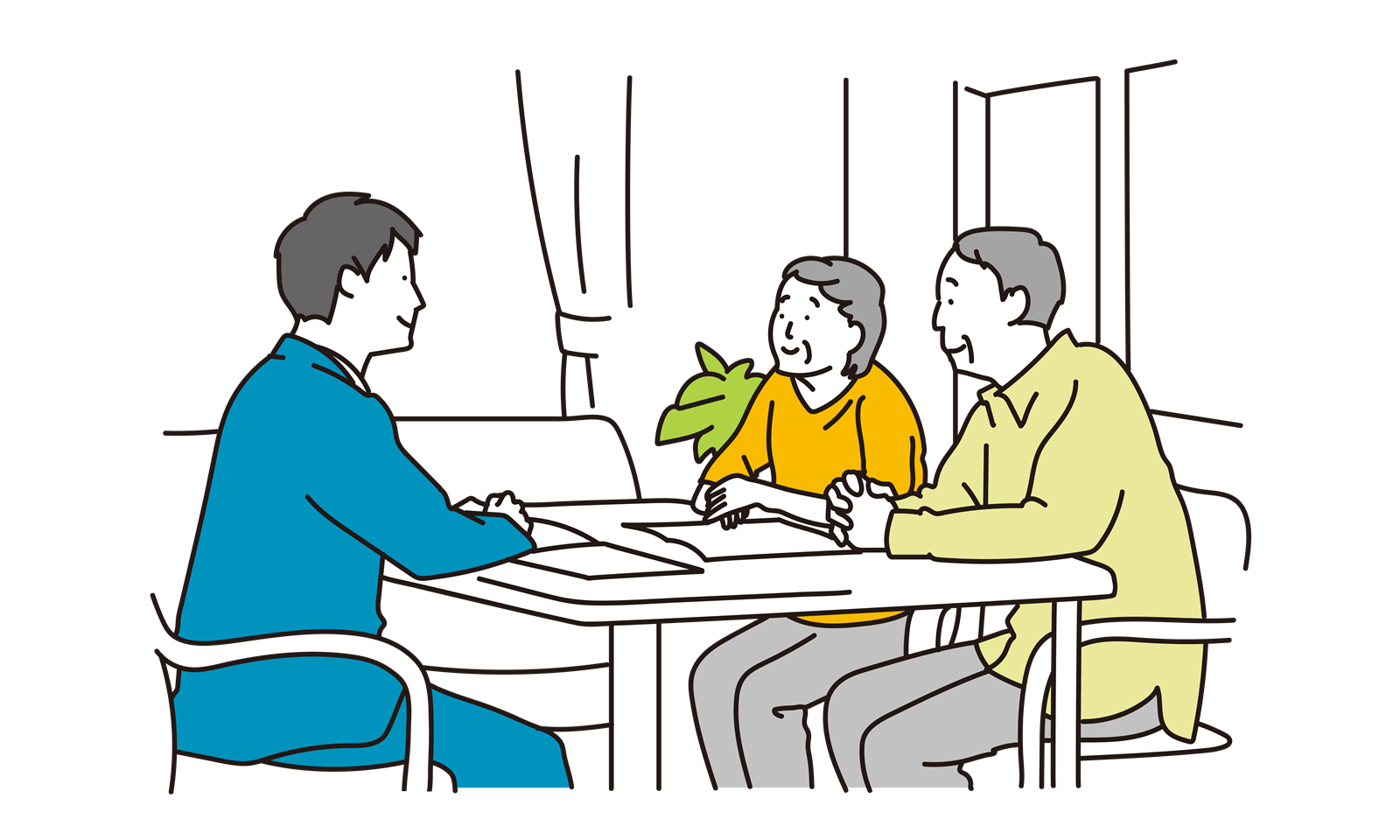遺言書に関する業務
- 自筆証書遺言の作成
自筆証書遺言は遺言者本人の自書で作成します。法律に照らして揉めないような遺言書の原案を作成します。特に遺留分を無視した遺言書は紛争の原因になるので注意が必要です。 - 遺言書保管制度と緩和策利用
自筆証書遺言の場合に利用します。作成した遺言書を法務局で保管して、検認の手続きも不要です。緩和策は財産目録部分を通帳コピー等に代えることができ、労力を大幅に減らせます。 - 公正証書遺言の作成
公正証書遺言は公証役場で作成する方式の遺言書です。公証役場は解説や指導をするところではないので、事前に法的に間違いのない原案を作成しておくことが必要です。
遺言書に関する業務は、ピンポイント解説ブログでもご紹介していますのでご覧ください。
遺言書の専門家

当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。
初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。
| 事務所名 | 行政書士かわせ事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 特定行政書士 川瀬規央 |
| 所在地 |
〒526-0021 滋賀県長浜市八幡中山町318-15 |
| TEL | 0749-53-3180 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 |
カレンダー通り(役所と同じ) 12/29~1/3は休業 |
| 所属 |
登録番号:第16251964号 |
|
会員番号:第1292号 |
|
|
行政書士 付随資格 |
特定行政書士(不服申立て代理) |
| 入管申請取次行政書士(ビザ申請) | |
| CCUS登録行政書士(建設業許可) | |
| 著作権相談員 |
長浜市・彦根市を中心に滋賀県が受任エリアです
遺言書のお問合せ
遺言書のよくある質問
相続の方法は大きく2通りあり、それは遺言書がある場合と無い場合です。遺言書があれば、遺言書に記載されたとおりに遺産分割をすればいいので揉める可能性は低くなります。一方、遺言書が無い場合は相続人全員で遺産分割協議を行って遺産分割方法を決めます。
なお、きちんと法律に沿って遺言書を作成しなければ、遺言書があるからこそ余計に揉めることになってしまいます。遺言書が無効になったり、遺留分を無視した遺言書を作成することはとても危険が大きくなりますので、必ず専門家に相談・依頼をすることを強く推奨します。
遺産に不動産を含む場合、その不動産を特定できるように記載しなければなりません。例えば、「長浜市八幡西町にある畑を二男幸四郎に相続させる」と記載してもどの畑なのか第三者に判断できません。
不動産の記載は、登記簿謄本(全部事項証明書)の通りに記載して特定します。遺産に多くの不動産を含む場合で自筆証書遺言を作成しようとすると絶対に間違えることがないように全ての不動産情報を欠くことになり大変です。
そこで、自筆遺言書の緩和策を利用することを推奨します、この緩和策は、遺言書本文の末に登記簿謄本の写しを添付することができるので遺言書本文に自書で書く必要はありません。
検認手続きは遺言書を発見した場合に開封せず(開封すると罰せられます)、相続人全員の前で家庭裁判所にて開封する手続きです。申請してから完了するまで日数がかかり相続人の負担になってしまいます。
この検認手続きが不要になるのは2通りの方法があります。まずは公正証書遺言にすることです。公正証書遺言は公証役場で作成しますが、原案を事前に作成しておかないと、揉めるような内容だったり法的におかしい内容だったりしてもそのまま公正証書遺言になってしまいます。
もう一つの方法は自筆証書遺言を作成して、自筆証書遺言書保管制度を利用することです。この制度は、自分で書いた遺言書を指定の法務局へ持参して保管してもらうものです。遺言書を改ざん、紛失する可能性もありませんし、検認手続きも不要ですので、当事務所ではこの方法を推奨しています。
遺言書の基礎知識
ここからは遺言書に関する基礎知識をご紹介しています。また、行政書士かわせ事務所ブログでも遺言書に関するピンポイント解説をしておりますので、こちらもご覧ください。
遺言書作成を推奨するケース
- 法定相続分とは異なる配分で相続させたい
遺言書が無ければ、遺産分割協議によって分割方法が決まります - 遺産の種類や額が多い
遺産が多いケースでは遺産分割協議が難航することが予想されます - 相続人以外にも遺産を与えたい
これは遺贈といいますが、遺言書がなければ不可能です - 相続人が配偶者+兄弟姉妹
疎遠になっている状況も多く、遺産分割協議が大変です。揉め事になることも多く要注意です - その他の例
先妻と後妻にそれぞれ子がいる、婚外子がいる、不仲であるというようなケースです
遺言書を作成していなければ実現不可能なこともあります。また、遺言書は「有効な遺言書」である必要があります。言い換えれば法律に適合していなければいけないので専門家に依頼されることを推奨します。
遺言書の種類とは
遺言書の種類とは、以下の2つの種類があります。それぞれの形式に従って書きます。他にも遺言書の種類はありますが(危急時遺言)割愛します。本当は秘密証書遺言という方式もありますが割愛します。
- 自筆証書遺言
全文をご自身で書き上げる形式です。法令改正があり作成しやすくなりました - 公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう形式で、手数料が必要です。事前に遺言書案を作成します
遺言書は、自身の意思として分割の方法である「誰に・何を・どれだけ」を指定する書面です。よって、口頭ではなく、法に沿った形式で書面でしなければ、法的な効力は発生しません
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く方式による遺言書です。パソコンや代筆は不可です。遺言書の作成は単独行為が必須であり、ご夫婦での連名は不可となっています。
遺言書は法的効果は発生する文書なので、文案作成は専門家への依頼を推奨します。自筆証書遺言は、相続手続きの前に家庭裁判所で検認という手続きをしなければなりません。
自筆証書遺言の緩和策とは
自筆証書遺言の緩和策として、遺言書に記載する財産目録の部分を、不動産登記簿謄本や通帳コピー、パソコン入力が認められるようになりました。
遺言書を書き直す場合でも財産目録はそのまま添付できます。つまり、本文だけを書き直せばいいので、遺言者の負担が大幅に軽減されます。
自筆証書遺言書保管制度とは
また、自筆証書遺言書保管制度も利用できます。作成した遺言書を、法務局で保管できて、さらに検認の手続きも不要となる制度です。自筆証書遺言書保管制度は当事務所も推奨しています。
法務局における遺言書の保管等に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第一項において同じ。)における遺言書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。
(遺言書保管所)
第二条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。引用元: e-Gov 法令検索
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。検認が不要のため、すぐに手続きを開始できます。遺言書は公証役場でも保管しますので破棄や変造などの危険がありません。
公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと、公証人が間違いがないか徹底的に確認して作成し、財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払います。
公正証書を作成する前に、その遺言書の内容を専門家に相談して決めておく必要があります。公証役場は指導やアドバイスをするところではありません
令和7年10月以降(順次指定される指定公証人の公証役場のみ)、インターネットによる嘱託が可能になります。ウェブ会議リモート方式を利用して公正証書を作成し、電子データで受け取ることもできます。
遺言書の書き方
遺言書の書き方で重要なことは、法に沿った要式で作成することです。自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自筆し、最後に印を押さなければ効力は生じません。
日付は年月日で記載しなければならず、押印は、認印でも拇印でも構いません。遺言書が書けたら、封をして封筒にも同じ印鑑で押印します。
このような形式も重要ですが、遺言書の内容も重要です。言葉の選択を誤ると法的に異なる意味になってしまうこともあり、遺産の分割の方法も法の定めを理解していなければ間違ってしまう可能性もあります。
遺言書の作成は、専門家に相談することが必須だといえます。遺言書は、エンディングノートのように、自分の想いを書けばよいというものではありません。
自筆証書遺言書保管制度を利用の際は封筒の封はせずに持参します
遺言事項とは
遺言事項とは、遺言の中で法的な効力がある部分をいいます。遺言事項以外は記載しても法的効力は発生しません。よく記載する項目は以下のとおりです。
- 遺産の分け方の指定
- 遺産分割方法の指定
- 遺言執行者の指定
- 相続人の廃除および取消し
- 遺贈
- 祭祀承継者の指定
最後の部分に「付言」というものも書けます。この「付言」には家族への感謝の言葉や最後のお願いなどを書きます。付言には法的効力はありません。
遺留分とは
遺留分とは、遺産を取得できる最低限の権利です。また、遺留分が侵害されたら、自分の遺留分を奪った人に対して、現金で支払うよう請求できますが、これを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分侵害額請求は裁判上で請求せずとも効力が発生し、実務としては内容証明で請求することがほとんどです。遺留分の放棄は、相続開始前でも可能です。
兄弟姉妹に遺留分は認められません
個々の遺留分の算出は、法で定められており、「法定相続分」×「遺留分の割合」で算出できます。遺留分の割合は、直系尊属のみの場合は「3分の1」、それ以外の場合はすべて「2分の1」です。個々の遺留分を一覧にすると以下のとおりです。
| 配偶者のみ | 配偶者 | 1 | 2分の1 | 2分の1 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者と子2人 | 配偶者 | 2分の1 | 2分の1 | 4分の1 |
| 子 | 2分の1ずつ | 8分の1ずつ | ||
| 子2人 | 子 | 2分の1ずつ | 2分の1 | 4分の1ずつ |
| 配偶者と父・母 | 配偶者 | 3分の2 | 2分の1 | 3分の1 |
| 父・母 | 6分の1ずつ | 12分の1ずつ | ||
| 配偶者と兄弟2人 | 配偶者 | 4分の3 | 2分の1 | 2分の1 |
| 兄・弟 | 8分の1ずつ | なし | ||
| 父母 | 父・母 | 2分の1ずつ | 3分の1 | 6分の1ずつ |
| 兄弟2人 | 兄・弟 | 2分の1ずつ | なし | なし |
民法
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。引用元: e-Gov 法令検索
遺贈とは
遺贈とは、残された遺言書に従って、遺産の一部または全部を特定の人に譲ることです。遺贈は、遺言書に記載しておかなければすることができません。
また、譲る相手が病院や地方自治体などの人(自然人)以外の団体や法人でも構いません。遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
- 包括遺贈
遺産の内容を特定せずに全部、あるいは遺産の●分の●というように割合を指定する遺贈 - 特定遺贈
あらかじめ遺産のうちの特定のものを指定する遺贈
検認とは
検認とは、自筆証書遺言の場合に家庭裁判所でする手続きです。相続人が申立人となり、最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。
申立人及びすべての相続人立会いの下で、家庭裁判所で遺言書が開封されます。ちなみに勝手に開封、執行すると5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。
検認は遺言書が有効か無効かを判断するような手続きではありません。家庭裁判所に申し立てをしてから期日まではおよそ1か月かかります。検認が不要となる方法は以下のとおりです。
- 自筆証書遺言書保管制度を利用する
- 公正証書遺言を作成する
民法
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。引用元: e-Gov 法令検索
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実際に実現する権限を持つ人です。相続人を代表して登記や金融機関での手続きができます。簡潔に言うと、相続手続きを行う人です。遺言執行者を選任するメリットは以下のとおりです。
- 認知や相続人廃除を被相続人死亡後にできる
- 不動産の所有権移転登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請が原則であり、登記義務者は相続人全員です。遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者のみが登記義務者となり、受遺者と登記申請ができます
遺言執行者の任務は以下のとおりです。
- 財産目録の調整
財産目録を調整し、これを相続人に交付します - 財産の管理・執行
遺産の管理その他、遺産の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します - 遺言による認知の手続き
遺言執行者は就職の日から0日以内に認知の届出をしなければなりません