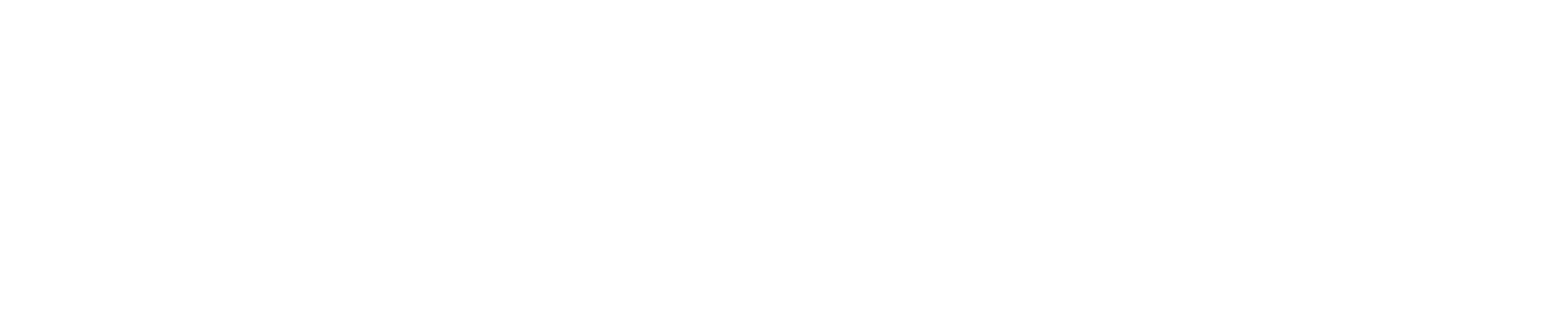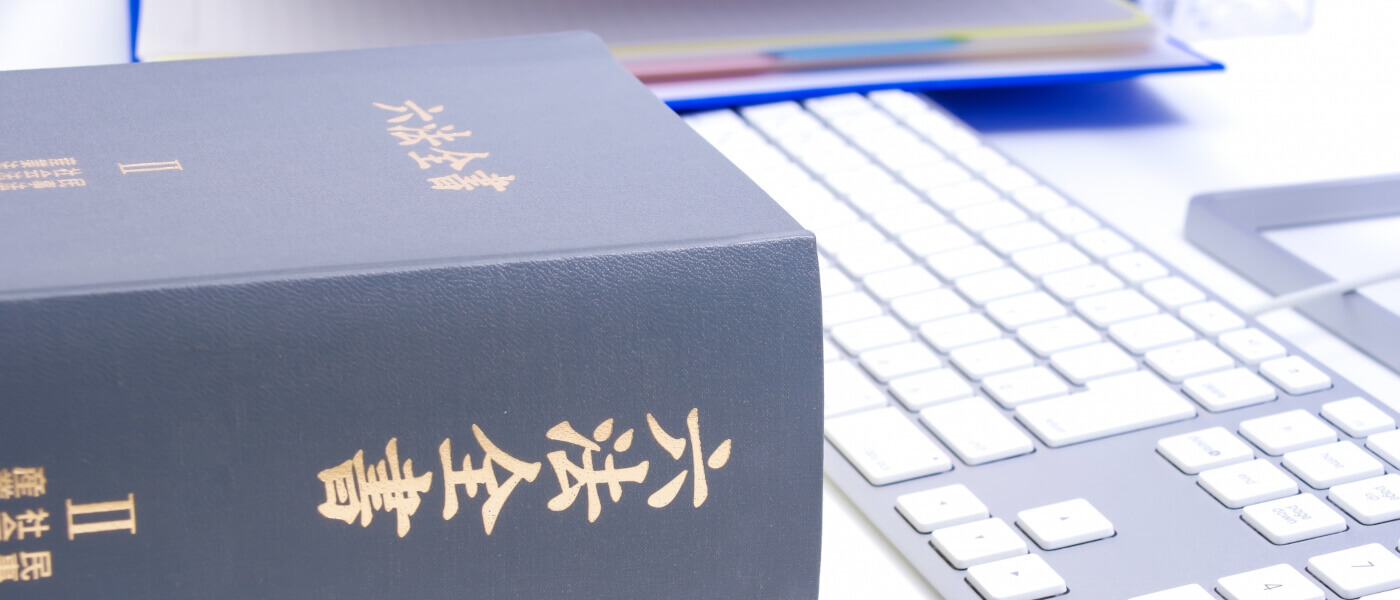Caseケース別該当業務のご案内
どのようなケースのときにどのような業務が該当するのか、当事務所の代表的な業務を例としてご案内しています。行政書士の業務は多岐にわたりますので、こちらに記載がない場合もご相談ください。
離婚の業務案内
【ケース】協議離婚をしたいが、どのように進めればいいか
離婚を決意したが、まだ配偶者には切り出していない。離婚の知識が全くないし、この先どうすればいいのか教えてほしい。裁判所の手続きは利用せずに解決したいと思っているので計画的に協議離婚をすすめていきたい。
【該当業務】離婚相談(初回無料)
離婚を決意したものの、ここから先はどうすればよいかわからないことも多いです。当事務所の離婚相談は初回無料ですが時間制限はありませんので、しっかりご説明いたします。ネット検索や知人の助言では得ることができない「正しい知識」が得られます。
【ケース】離婚に伴う取り決めを法的効果がある書類にしたい
離婚は人生の中でもとても大事なこと。離婚届を提出してしまうと「赤の他人」になるので、その前に離婚に伴う様々な取り決めを法的効果があるきちんとした書類にしておきたい。
【該当業務】離婚協議書の作成
離婚協議書は、離婚に伴う取り決め(財産分与、養育費など)の合意を証するために書類にしたものです。離婚協議書は離婚届を提出する前に作成します。当事務所独自の「かわせ式離婚協議」なら円滑に離婚協議をすすめることができ、モレがない離婚協議書を作成することが可能です。この離婚協議書には法的効果がありますが、署名押印をして初めて法的効果が発生します。
【ケース】離婚することになったがローン中の自宅をどうすればよいか
離婚することになったが、財産分与にローン中の自宅があり、離婚後は妻と子が自宅に居住することを望んでいるがどのように取り決めをすればよいか。
【該当業務】離婚協議書の作成
ローン中の自宅は売却しても債務が残るオーバーローンがほとんどです。裁判所手続きでは双方が納得できない結果になることも多く、協議離婚なら互譲すれば双方が納得できる結論に至る可能性があります。オーバーローン住宅がある財産分与はとても難解ですが豊富な実務経験による多彩な選択肢をご提案いたします。
【ケース】離婚には合意したが、何をどのように取り決めすればいいかわからない
夫婦間で離婚自体には合意できているが、財産分与や養育費など法律の知識が無いので、何をどのように取り決めすればいいかわからない。弁護士に相談したが、聞いたことにしか答えてもらえず面倒くさそうな対応だった。
【該当業務】離婚協議書の作成
当事務所なら法律知識ゼロでも、「かわせ式」により間違いがない離婚協議書を円滑に作成できますのでご安心ください。離婚といえば弁護士のイメージですが、実際には離婚の約90%は協議離婚のため裁判所手続きは不要です。「裁判になったら来てください」という弁護士のスタンスも理解できますが…。
【ケース】養育費の支払いが滞った際はすぐに強制執行をしたい
離婚協議書を作成して、離婚に伴う取り決めをきちんと書類にしたい。子供がまだ小さく、養育費の支払いが長期間になるので、養育費の支払いが滞ったときにはすぐに強制執行ができるようにしたい。
【該当業務】離婚給付等契約公正証書の作成
離婚協議書を公正証書で作成すると、調停や訴訟を経なくともすぐに強制執行(いわゆる差押え)をすることが可能です。公正証書は公証役場で作成しますが、事前に離婚協議書を作成しておくことが肝要です。
【ケース】配偶者と協議が難しい
配偶者と離婚協議をしたいが、お互いに冷静になって話すことができず、取り決めをして書面にしたいと思っているが、何についてどのように決めて行けばよいかわからず、先に進めていない。
【該当業務】離婚協議の立会い
当事務所の「かわせ式」であれば離婚協議が円滑になります。ご自身で取り決め事項をどのようにするかを考えることはとても困難です。また、当事務所で当職が立会いのもと、離婚協議をしていただくことも可能です。当職はどちらか一方のお味方になるわけではなく、司に終始します。法律により相手方との交渉はいたしかねます。
【ケース】離婚調停が始まった
離婚協議をしていたが難航し、配偶者から離婚調停を申し立てられた。自分でやるのは自信がないので代理人として行って欲しい
【該当業務】受任不可
離婚調停は紛争性が成熟したと判断されます。離婚調停は家庭裁判所の手続きにつき、代理人となれる資格は弁護士に限られます。なお、離婚訴訟(裁判)の代理についても弁護士に限られますので受任いたしかねます。
男女問題の業務案内
「男女問題」ページへ戻る
【ケース】籍は入れずに夫婦として暮らしたい
籍は入れずに、いわゆる事実婚としてやっていきたいと考えている。婚姻届を出してする法律婚にはいろんな夫婦としてのメリットがあるが、事実婚には認められていないと聞いた。事実婚でも出来る限り法律婚のような権利を得たい。
【該当業務】事実婚契約書を作成
夫婦には法律で認められた様々な権利や義務があります。しかしこれらは婚姻届出をした法律婚の場合です。何もしなければ事実婚では認められませんが、契約書にすることによって法律婚に近付けることが可能です。
【ケース】内縁関係を解消するが後で揉めないようにしたい
籍は入れずに内縁関係を続けていたが、関係を解消することになった。離婚をするときに近い内容で色んな取り決めができると聞いたし、後で揉めないように解決したい。
【該当業務】内縁関係解消の合意書を作成
内縁関係を解消する場合、法律婚ではないものの離婚に関する定めを適用できることがあります。これらは離婚の際に作成する離婚協議書に準じた書類として作成をすることができます。
【ケース】婚約を解消したい
婚約中だが、諸事情により解消したい。両親も激怒しており、損害の賠償もして欲しいし、後で揉めるようなことがないように綺麗に関係を解消したい。
【該当業務】婚約解消の合意書を作成
単に付き合っている男女カップルではなく、婚約をしている場合にこれを解消することになった場合は権利と義務が発生することになります。これらを証するものとして合意書の作成を推奨します。
【ケース】別居することになったが何か書面にした方がよいか
離婚を前提とした別居をすることになった。役所へ届け出るようなことはないと知ったが、何か書類にしておいた方がよいか。友人に「婚姻費用というものを請求できる」と聞いているが。
【該当業務】別居に関する合意書を作成
別居は特に役所に届出るものはありませんが(住民票除く)、別居によって発生する婚姻費用分担請求の権利や義務などを証するものとして合意書を作成することは、将来に離婚へ発展した場合にも役立ちますので、作成を強く推奨します。
【ケース】夫の不倫が発覚したが離婚はしたくない
夫が不倫をしていることが発覚し、不貞行為も認めている。まだ子供が小さくすぐに離婚は出来ないが、不倫関係を終わらせたいし、相手方にはきちんと慰謝料を払ってほしい。
【該当業務】誓約書の作成+不貞行為の示談書を作成
不貞行為が発覚した場合、夫婦関係を継続する場合には、不貞の相手方との関係解消や慰謝料請求などが一般的です。そのためには配偶者に対する誓約書、不貞行為の相手方との示談書(三者間での示談書も可)を作成します。
【ケース】夫の不倫が発覚し、離婚することになった
夫が不倫をしていることが発覚し、これが原因となって離婚することになった。夫にも不貞の相手方にも慰謝料を請求したい。
【該当業務】離婚協議書の作成+不貞行為の慰謝料請求
ご主人とは離婚をするので、離婚協議書を作成します。離婚協議書に慰謝料を条項として記載しますが、財産分与などほかにも重要な条項がたくさんあります。一方、不貞行為の相手方には慰謝料を内容証明で請求します。この2種類の書類作成は、関連性があります。
相続手続きの業務案内
「相続手続き」ページへ戻る
【ケース】相続手続きをしたいが、誰が相続できるかわからない
父が亡くなったが、誰に相続できる権利があるのかわからない。また、相続手続きには戸籍謄本が必要だと聞いたことがあるが、なにを取ればいいのかもわからない。【該当業務】相続関係説明図を作成
相続人が誰なのかは相続順位によって決まりますが、相続人に応じた戸籍謄本等を取得して相続人を確定させる必要があります。確定後、図にしたものが相続関係説明図です。
【ケース】亡き父の銀行口座が多く、その手続きが大変だ
亡き父は、事業をしていたので銀行口座がたくさんあり、解約手続きが大変そうだ。一気に手続したいがどのようにすればよいか。【該当業務】法定相続情報一覧図を作成
相続関係説明図を添付して法務局に作成してもらう書類です。戸籍謄本等の束ではなく1枚の一覧図になるので(しかも無料で何枚でもOK)、同時に相続手続きを進めることが可能になります。
【ケース】遺産を分けるときに、わかりやすく協議したい
亡き母の遺産を兄弟で分けることになったが、遺産をわかりやすくして揉めずに円滑に話し合いができるようにしておきたい。【該当業務】財産目録を作成
遺産の内容や金額等を目録にしたものが財産目録です。これをどの相続人がどれだけ取得するかを遺産分割協議で決めることになります。
【ケース】遺産分割の結果を証する書類を提出するよう言われた
相続手続きを始めたが、相続人の誰が何を相続するかを協議した証としての書類を作成して提出するように言われている。後で揉めたくないので、きちんと書類にして残しておきたいとも考えている。【該当業務】遺産分割協議書を作成
相続人全員で遺産分割協議をし、整ったことを証するものとして作成するのが遺産分割協議書です。これは各種相続手続きにも必要となる最も重要な書類といえます。
【ケース】亡き父の土地を相続したが、正直いらない
亡き父が所有していた土地を相続したが、自分は滋賀県に住んでいるわけでもなく、固定資産税も払いたくないし、管理や修繕も大変だ。正直言うと要らないが売れない土地だから困っている。【該当業務】相続土地国庫帰属制度の申請
不要な土地を国庫に帰属させることができる制度です。要件と申請が複雑なため専門家に依頼することを推奨します。かなり難解な制度なので事前にご相談されることをおすすめします。
遺言の業務案内
「遺言書」ページへ戻る
【ケース】遺言書を作成したい
遺言書を作成したいが、将来的に書き換える可能性が高く、費用をかけず手軽に作成したい。遺言書は相続手続きに必要な法的効果があるものなので専門家に任せた方がよいと知人に教えてもらったが。
【該当業務】自筆証書遺言を作成
自筆証書遺言とは全文を自書する方式で、完成した遺言書は自身で保管します。相続手続きの際にはまず遺言書を家庭裁判所に持ち込み、相続人全員の前でする「検認」という手続きが必要です。遺言書は自分のためのみならず、相続人のために作成するものです。遺言書は法律の要件を満たしていなければ無効ですので、内容によりますがご自身だけで作成できるケースは稀です。
【ケース】遺言書を書きたいが不動産が多くて大変だ
遺言書を作成したいが、畑など所有している不動産が多く、書くのが大変だ。将来的に内容を変更して書き換えるときにも手間がかかってしまう。
【該当業務】遺言書の緩和策を利用して自筆証書遺言を作成
全文を自書しなければならない自筆証書遺言の緩和策として、財産目録の部分については預金通帳や登記簿謄本の写しを添付することが認められるようになりました。これなら本文だけを書き換えればよいので負担の軽減になります。
【ケース】遺言書は相続のときに検認という手続きが必要らしいが
遺言書を作成しておこうとしているが、相続のときに家庭裁判所で検認という手続きが必要だと聞いた。息子たち相続人には迷惑を掛けたくないので、検認が不要な公正証書遺言も考えてはいるが。
【該当業務】自筆証書遺言書保管制度を利用して自筆証書遺言を作成
自分で保管し、相続開始時には検認が必要な自筆証書遺言ですが、本制度を利用すると、作成した遺言書は法務局で保管してくれて、検認手続きも不要となります。公正証書遺言のメリットを実現できる画期的な制度だといえます。
契約書作成の業務案内
「契約書の作成」ページへ戻る
【ケース】近所の人に畑を売るが口約束だけでは怖い
不要になった畑を近所の人に売ることになった。知っている人とはいえ、口約束では怖いので書類にしておきたい。役所で農地売買の手続きもしなければならないが契約書を見せてくれと言われている。
【該当業務】土地売買契約書(農地)を作成
農地を売買する際の契約書です。約束を書面にするのは売主と買主の双方を保護するためです。手続きによっては売買契約書を役所に提出する必要がある場合もございます。
【ケース】月極駐車場を始めるが契約書を作りたい
物置小屋を潰してそこで月極駐車場を始めたい。知らない人にも貸すことになるので、きちんとした契約書を作成しておきたい。
【該当業務】駐車場賃貸借契約書を作成
月極駐車場を始める場合、口約束では非常に不安定で紛争の危険すらあります。契約に関しての定めを書類にしておくことが肝要です。
【ケース】友人にお金を貸すので借用書を作っておきたい
友人にお金を貸すことになったが、きちんと返してもらえるように借用書を作ってから貸したい。
【該当業務】金銭消費貸借契約書を作成
友人や知人にお金を貸すことがありますが、きちんと返してほしいのであれば契約書にしておくことが必須です。口約束で貸してしまうと、「借りていない」と言われたときは打つ手がありませんし、滞納にも対応できません。
【ケース】大工だが請負工事には契約書締結が義務付けられている
大規模な工事ではないが、建設請負工事には変わりないので契約書を取り交わす必要がある。小規模な工事のときに使い回せるような契約書を作成しておきたい。
【該当業務】建築工事請負契約書を作成
建設工事を請負う際には請負契約書を作成することが建設業法で義務付けられており、施主を保護するためでもあります。建設業法はとても厳しい法律ですので遵守することが大切です。
【ケース】フリーランスだが、業務委託契約書を作成したい
フリーランスで業務委託を受ける際に、依頼主から契約書を用意するよう言われている。立場上はこちらが弱いので権利を守れるような書類にしておきたい。また、フリーランス新法にも対応している契約書を作成しておきたい。
【該当業務】業務委託契約書を作成
業務委託される場合の契約書です。不利な立場で受託することが多いフリーランスを保護するためには契約書が必須です。なお、フリーランス新法に対応できる契約書を作成することも可能です。
【ケース】従業員を雇うことになったので契約書を作りたい
従業員を雇うことになったので、契約書を作らなければならないが難しくてわからない。雇用後にハローワークへ駈け込まれるような事態は避けたいので法的に間違いがない契約書を作成したい。
【該当業務】雇用契約書を作成
雇用主に義務付けられているのは「労働条件通知書の交付」ですが、雇用契約書に労働条件の条項が含まれるので雇用契約書の取り交しをすることが多いです。雇用契約書は、就業規則の有無によって大きく内容が異なります。
告訴状作成の業務案内
「告訴状の作成」ページへ戻る
【ケース】居酒屋で他の客から「殺すぞ」と執拗に脅された
よく行く居酒屋で隣にいた客が因縁をつけてきて、「殺すぞ」「ボッコボコにしたろか」と1時間近くも執拗に脅された。お気に入りの居酒屋なので今後も通いたく、許せないので逮捕して欲しい。
【該当業務】脅迫罪の告訴状を作成
脅迫罪にあたる可能性が高いです。脅迫罪は、命・身体・自由・名誉・財産に対して害悪を与えると告げられることです。脅迫とは一般的に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
【ケース】上司から「土下座して謝れ」などと言われている
会社の上司から毎日のように「土下座して謝れ」、「クビにするぞ」、「お詫びにサービス残業しろ」と言われている。これは指導を超えてもはやパワハラなので許せない。罰を与えて辞めさせたい。
【該当業務】強要罪の告訴状を作成
強要罪は、暴行や脅迫によって人に義務のないことを行わせる行為です。パワハラやセクハラも該当するケースがあります。強要罪で告訴となると、もはや社内の問題ではなく刑法上の問題になります。
【ケース】財布の中身をよこさないと殴るぞと脅された
帰り道の公園で若い男から、「財部の中身を全部よこさないと殴るぞ」と胸ぐらを掴まれて脅された。すごく怖かったので有り金全部を渡した。
【該当業務】恐喝罪の告訴状を作成
恐喝罪は、暴行や脅迫により、怖がらせて金銭や品物を交付させることです。見ず知らずの者から恐喝された場合、出来る限り犯人の特徴を覚えておく必要があります。また、暴力や脅しを用いたいわゆる「踏み倒し」は、「財産上不法の利益」を得たことになるので恐喝罪に問われる可能性があります。
【ケース】飲み会の席でウソの悪口を言われた
飲み会の席で、同僚が「こいつ、20歳になってもおねしょしてたんやぞ」などと皆に聞こえるように大きな声で言いふらした。そんな事実はもちろんないが、周りのみんなは信じきった様子だった。いつも人の悪口を言う奴だが、今回は絶対に許すことができない。
【該当業務】名誉毀損罪の告訴状を作成
名誉毀損は、公然と事実を摘示し、人の名誉を傷つける行為です。事実の摘示は、真実か否かはどうでもよく、具体的な事実を示すことで足ります。「公然と」なので自分だけに言われたケースは該当しませんが、SNSへの投稿は該当します。SNS投稿の場合、犯人の特定がネックになることが多いです。
【ケース】客が大声で怒鳴り散らしてテーブルを蹴飛ばした
飲食店を営業中、客の一人が些細なことが理由で、大声で怒鳴り散らしてテーブルを蹴飛ばし、周りの他の客を怖がらせた。この客は時々このように店で悪態をつくので、このままでは客が寄り付かなくなる。厳罰に処して欲しい。
【該当業務】威力業務妨害罪の告訴状を作成
威力業務妨害は、暴行や脅迫、怒号などの「威力」を用いて業務を妨害した場合に成立する可能性があります。「お客様は神様やろ、言うこと聞けや!」はこのような客の常套句ですが、現代ではただの迷惑客です。
【ケース】肩がぶつかった相手から3発殴られてケガをした
飲み屋街を歩いていると、男と肩がぶつかり、その男が因縁を付けてきていきなり殴りかかってきた。やめろと言ったが言うことを聞かず、顔面を3発殴られて全治10日のケガを負った。処罰を希望する。
【該当業務】傷害罪の告訴状を作成
故意の暴行で、傷を与える結果があれば傷害罪となります。傷害とは、人の生理機能を害することです。軽微な負傷については暴行罪に変更されることもありますが、傷害罪は暴行罪よりも罪が重いです。
建設業許可の業務案内
「建設業許可」ページへ戻る
【ケース】元請から建設業許可を取れといわれた
建設業を営んでいる個人事業主だが、元請から「建設業許可を取ってくれないと下請けに出せない」と言われた。事業をはじめて6年経ち、500万円以上の仕事も請負いたいので建設業許可を取りたい。
【該当業務】建設業許可 新規許可申請
新たに建設業許可を取得したい場合は新規許可申請です。大きく6つの許可要件を満たす必要があるので、まずは要件確認から始めて参ります。より迅速なオンライン申請にも対応しています。
【ケース】建設業許可をすぐに取りたい
500万円以上の仕事が舞い込む予定なので建設業許可をすぐに取りたい
【該当業務】建設業許可 新規許可申請
そもそも6つの要件を満たせなければ申請をしても不許可になりますので、まずは要件確認から始めます。申請は迅速なJCIP(電子申請)で行いますが、事前に「gBizIDプライム」のアカウントを取得しておいてください。なお、審査には30日ほど要しますのでいかに早く動き出すかにかかっています。
【ケース】建設業許可を取ってから事業を始めたい
どうせなら建設業許可を取ってから事業(建設業)を始めたいと考えている。やはり許可業者であることは施主からも信頼してもらえるので、仕事がたくさんくると思う。
【該当業務】建設業許可 新規許可申請
建設業許可の許可要件は大きく6つあります。要件を満たせなければ許可は取れませんし、要件を満たしていることを書面で「証明」しなければなりません。当該ケースでは相当厳しいと考えられますが、絶対無理だとは言い切れませんので、まずは初回無料相談の中で確認いたします。
【ケース】許可後もうすぐ5年になるので更新したい
建設業許可を取って営業しているが、もうすぐ許可後5年を迎える。仕事も順調なので更新手続きをして、このまま建設業を継続して営みたい。【該当業務】建設業許可 更新許可申請
更新の許可申請です。これは有効期限までにするものではなく、有効期間の30日前までに更新の申請を完了させなければなりません。また、決算変更届を欠けることなくすべての年度分を届出していることが必要です。
【ケース】板金工事業を営んでいるが屋根工事業の許可も欲しい
板金工事業の建設業許可を取って板金工事を営んでいるが、太陽光パネル工事の需要が増えたので、屋根工事業の許可も取りたい。屋根工事で500万円以上の請負工事もする予定がある。
【該当業務】建設業許可 業種追加
すでに建設業許可を取得している方が、同じ種別の許可で別の業種についても許可を取る場合の手続きです。その業種について要件を全て満たす必要があり、手続き自体は新規許可とほぼ同様です。営業所技術者等の要件を満たせるかどうかがポイントです。
【ケース】決算変更届の財務諸表が全くわからない
昨年、建設業許可を取ったが、決算変更届をしなければならず、そのなかでも財務諸表の作成が難しいのですべて任せたい。しかも毎年決算後に届出しないといけないので忙しくて無理だ。
【該当業務】決算変更届
決算変更届は、変更が生じた場合の届出ではありません。毎年決算後4か月以内に必ずしなければならない届出です。これが1回でも欠けると更新許可申請ができません。添付書類にある財務諸表は、決算書類をそのまま添付することはできず、建設業法に沿った財務諸表に作り替える必要があります。
【ケース】常勤役員等が退職し、他の者に入れ替えたい
株式会社として建設業許可を取ったが、常勤役員等をしていた者が退職することになり、他の社員を役員に入れて常勤役員等にしたい。要件を満たすのであれば変更の届出まで任せたい。
【該当業務】変更届(2週間以内)
建設業法で定められた変更事項が生じた場合は、内容により発生から2週間以内にするものと30日以内にするものとがあります。期間が短いので、予めどんな変更が該当するのかを理解しておくことが必要です。怠ると建設業法違反となり許可を失う恐れがありますし、5年間は許可の取り直しもできません。
農地転用の業務案内
「農地転用」ページへ戻る
【ケース】許可を取らずに畑に倉庫を建てている
亡き父が建てた倉庫だが、売ろうと思い登記簿を見たら地目が畑で売れないことが判明した。知人に聞くところによると違法行為だと言われ、困っている。
【該当業務】農地転用4条許可申請(届出)
現状、無許可転用になっており、確かに違法行為(農地法違反)で罰則もあります。しかしながら亡き父が建てたとのことで、直ちに罰則ということにはならないことも少なくありません。当事務所ではこのようなケースでも顛末案件申請として承ります。
【ケース】耕作しなくなった田んぼを太陽光発電として売りたい
市街化区域外にある自分の田んぼだが、もう耕作をしないので太陽光発電の会社に売ろうと思うが、農地転用の許可を取らなければ売買できないと役所に言われたので許可を取ってほしい。
【該当業務】農地転用5条許可申請
市街化区域外にある農地を、農地以外の使用目的にし、所有者が変わる場合には農地法5条許可申請の手続きが必要です。農地は売買が難しく、太陽光発電にするケースが多くなります。
【ケース】畑をつぶして二世帯住宅を建てたい
大阪で仕事をしていた息子が実家に帰ってくるが、現在の住居では手狭なので、市街化区域外にある自宅の隣の畑をつぶして二世帯住宅として建て替えをしたい。
【該当業務】農地転用4条許可申請
市街化区域外にある農地を、農地以外の使用目的にし、所有者が変わらない場合なので農地法4条許可申請の手続きが必要です。許可を取ってから新居の計画を立てるのではなく、図面まで出来上がってから申請をします。なお、所有者が息子さんになる場合は5条許可申請になりますが、必要書類はほぼ同じで譲渡人と譲受人の共同申請になります。
【ケース】耕作していない畑を駐車場として活用したい
市街化区域にある自分が所有している畑だが、もう何年も耕作していないので、月極駐車場として活用したい。近所の方からも駐車場にしてくれたら契約したいとよく言われている。
【該当業務】農地転用4条届出
市街化区域にある農地を、農地以外の使用目的にし、所有者が変わらない場合なので農地法4条届出の手続きが必要です。許可申請と比べると添付書類が少なく簡易的な手続きです。転用目的が駐車場の場合、意外と難しい場合があります。事業場で事業用車両を駐車する場合は面積がネックとなり、いわゆる月極駐車場の場合は契約台数見込を証明する必要があります。
【ケース】畑をお隣さんに売りたいが許可がいると言われた
畑を少々持っているが、高齢になったので、畑を売ってほしいと言われていたお隣さんに売ることにした。農業委員会に相談したら、農地売買にあたるので許可が必要だと言われた。
【該当業務】農地法3条許可申請
農地を農地のままで売買し、その後もその農地で耕作をする場合は農地法3条許可申請の手続きが必要です。買主が売買後も耕作ができることを示す書類を作成しなければなりません。買主が認定農業者であれば、農地中間管理機構の農地売買制度を利用できる可能性もあります。
【ケース】亡き父から相続をした田の相続手続き
父が亡くなり、田を相続によって取得した。農地なので許可が必要だと思い農業委員会に問い合わせたら、許可は不要だが届け出るように言われた。
【該当業務】農地法3条の3届出
農地の所有者が変わることになります。売買なら農地法3条許可申請が必要ですが、相続による取得の場合、簡易的な届出でよいことになります。事前に相続登記をしておかなければなりません。
【ケース】新築住宅のための土地を探したが青地だった
新築住宅のためのとちを探したが青地だということで、農地転用は無理だと業者に言われた。
【該当業務】農振除外+農地転用
青地は原則として農地転用は不可です。青地を白地にする農振除外という手続きをし、青地から脱して農地転用の許可がおりれば住宅建築も可能です。しかし、農振除外はかなりハードルが高い手続きで、年に2回しか受付してもらえず、さらに審査には半年以上かかります。できることなら青地は避けた方が賢明だと考えられます。
ビザ申請の業務案内
「ビザ申請」ページへ戻る
【ケース】外国人をエンジニアとして日本に呼び寄せて雇用したい
母国にいる外国人をエンジニアとして雇用したい。彼は大学で工学を学んで卒業しており、日本語も話せるので即戦力だが、どんな手続きが必要かわからないので任せたい。
【該当業務】在留資格認定証明書交付申請
ビザ申請の手続きとしては、母国にいる外国人を呼び寄せて日本に在留させることが目的なので、在留資格認定証明書を取得し、3か月以内に入国することです。このケースの在留資格は「技術・人文知識・国際業務」が該当します。
【ケース】留学の在留資格から他の在留資格に変更したい
留学ビザで在留する大学4年生を新卒で雇用したいと考えている。すでにビザを持っているがこのまま卒業後に雇用することは可能か。可能なら必要なビザ申請をお願いしたい。
【該当業務】在留資格変更許可申請
すでに在留資格を所持して日本に在留中の外国人が、他の在留資格をもって日本に在留する場合に必要な手続きです。申請のためには、新しく取得しようとする在留資格の要件を満たす必要があります。留学からの在留資格変更(技人国への変更)の場合、卒業後だと変更ではなくなるので卒業見込証明書を大学に発行してもらい、先に在留資格変更許可申請をすることになります。
【ケース】フィリピン人の妻のビザを更新して欲しい
フィリピン人女性と結婚したが、そのときに妻が取得したビザがそろそろ有効期限が近づいているので更新の手続きをして欲しい。
【該当業務】在留期間更新許可申請
現在所持している在留資格の有効期間が過ぎる前に更新の手続きをしなければオーバーステイになってしまいます。更新しても同じ有効期間になるとは限りません。
【ケース】台湾人の妻の永住許可を取ってほしい
台湾の女性と結婚し、日本で一緒に暮らしていたが、永住ビザを取ると今後は面倒な更新をしなくてもよいと聞いた。永住ビザはとても難易度が高くて難しいと聞いているので任せたい。
【該当業務】永住許可申請(タイミングにより在留期間更新許可申請も必要)
永住許可は、在留しながら要件を満たしたときに許可申請をすることができるようになります。永住許可は在留期間更新の必要が無く、就職やローンによる購入などにも有利になるケースもございます。永住許可は要件がとても厳しいので不許可の可能性もあります。所持している在留資格に余裕がある時点で永住許可申請することを推奨します。
【ケース】外国人の知り合い10名分のビザ更新をしてほしい
外国人の知り合い10名分のビザ更新をしてほしい。本人たちは仕事があるので、私が必要書類を取りまとめて持参する。
【該当業務】受任不可
当職は申請取次行政書士なので本人の入管への出頭は不要です。しかし、依頼人は本人または入管が指定する代理人です。当該ケースは受任できませんし、一切の不正申請は絶対的にお断りさせていただいています。